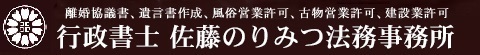離婚協議書の作成
・離婚法律相談支援
・離婚心理カウンセリング
全国対応!電話,メール,Zoomで打合せします!
離婚協議書,不倫示談書,公正証書,内容証明,実績多数有!
まずはお気軽にお電話を!

離婚協議書の作成
かしこい離婚
それは「法律」と「相手の真の姿」を知ることで実現します!
弊所ではその豊富な実務経験から、離婚協議書作成支援において、『離婚法律相談支援』だけでなく、弊所が独自に築き上げた『離婚心理カウンセリング』も実施し、依頼者に対して、離婚における法律的問題への理解と、離婚心理カウンセリングを行うことによって相手の真の姿(なぜモラハラをするのか、なぜ浮気をするのか、なぜコミュニケーション不全が生じてしまったのかについての相手の深層心理)を理解する支援を行い、金銭面や条件面で離婚後の生活がスムーズにいくように、そして離婚後の「気持ち」が前向きになるように、『かしこい離婚』の実現について全面サポートしています。
親権・養育費・面接交渉・財産分与・慰謝料問題等々、離婚問題は一人で悩まず守秘義務を持つ法務家の行政書士へご相談ください。
離婚問題について相手とうまく合意できるまで、離婚問題をあなたがうまく乗り切るまで、そしてあなたが本当の幸せをつかむまで全面サポートします。
下記に離婚協議書の作成についての詳しい記事があります。どうぞご覧ください。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
☎059-389-5110
(電話受付9:00~20:00 年中無休)
※現在、相談の電話が込み合っており、電話がつながりにくくなっています。必ずかけなおしますのでしばしお待ちください。
★平日の18時以降や土日でも『面談対応』OK!
※電話アポ必要です
『かしこい離婚』とは
・金銭面や条件面で離婚後の生活がスムーズにいく離婚であり、
・離婚後の「気持ち」が前向きになる離婚です!
●離婚の話し合いは口頭で行っても感情が先走りまとまりません
●口頭では養育費・慰謝料・財産分与等の重要事項もお互い把握しきれません
●離婚の話し合いがうまくいかない大きな理由がこれです
このような場合には
●具体的な内容が記された書類(離婚協議書の第一稿)を手元に置いて話し合いましょう●書類を見ながら話し合えば、決めるべき事柄が明確になります
●書類を見ながら話し合えば、離婚における重要事項を落ち着いて考えることが出来ます
●相手の真の姿を理解することによって、合意点を見出すことが出来ます
●結果、離婚の合意がスムーズに行なえます
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
☎059-389-5110
(電話受付9:00~20:00 年中無休)
弊所の離婚協議書作成サポートとは、離婚協議書という書類を用いて、
あなたが「離婚の合意をスムーズに行う手助け」をすることです。
<弊所が提供する離婚協議書作成サポート>
1.まずは面談にて、あなたのご意向をお聞きし、法的立場をご説明いたします
2.次にあなたのご意向にそった離婚協議書(第一稿)を作成し、お渡しします
3.相手の真の姿を理解するために、弊所が編み出した「離婚心理カウンセリング」を実施します。
4.その後、離婚協議書(第一稿)をもとにして、お二人で話し合っていただきます
5.その話合いの結果を受けて、離婚協議書を修正いたします(第二稿)
6.お二人の話し合いがまとまるまで、何度でも修正いたします
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
☎059-389-5110
(電話受付9:00~20:00 年中無休)
●弊所が提供する離婚における『法律相談支援』とは
離婚はとてもつらいです。
それまで一心同体であった夫婦が、まさに身も心も、そして契約や法律関係(生命保険等)においても離れ離れになる作業だからです。財産分与、養育費、親権監護権、離婚後の生活についてあらゆることを想定して考え、話し合い、合意しなければなりません。
そのためにはやはり離婚にかかる法律知識を学ぶ必要があります。権利の上に眠るものは保護されないからです。
離婚におけるあたなの法的立場を知ることは、つまり離婚におけるあなたの法的な権利と義務を知ることです。法的な権利と義務を知ることで、離婚におけるあたなの取るべき態度(離婚における財産分与)が明確に見えてきます。
その支援を当職が全力をもって支援いたします。これが弊所が提供する離婚における『法律相談支援』です。
弊所は離婚協議書作成支援に特化した行政書士事務所です。
その豊富な業務経験から得た「離婚に関する法律知識を依頼者様へ惜しみなく提供させていただきます。
依頼者様に寄り添い、離婚後のあなたの人生が光り輝くために、離婚後にお互いが困らないための予防法務に徹した離婚協議書作成を全力でサポートさせていただきます。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
☎059-389-5110
(電話受付9:00~20:00 年中無休)
●弊所が提供する『離婚心理カウンセリング」 とは
当事務所では、その豊富な離婚協議書作成支援の経験において心理学を学び、独自の「離婚心理カウンセリング術」を構築しました。この「離婚心理カウンセリング」を用いて、相手の真の姿を理解する支援をしています。
離婚においては、「結婚後あいつは冷たくなった」や「結婚してからモラハラがひどい!」とか「不倫をしておいて許してれと懇願してくる夫が理解できない」とか「離婚するなら財産は全部くれるって言っていたのに、離婚する今になったら『俺には半分権利がある』みたいなことを言って前言翻すのです!」等等・・・・「相手が何を考えているかわからない=コミュニケーション不全の状態」であることがほとんどです。
この状態で、つまり相手の真意をつかむことなく、ただご自身の主張(権利)を相手にぶつけても、相手も納得しません。
コミュニケーション不全の夫婦が離婚における財産分与で合意するためには、相手方の真の姿を認識し、離婚というコミュニケーション不全がなぜ起きたのかを理解することにより、離婚にかかる諸問題の裏に隠れるお互いの真意にコミットする必要があります。
弊所ではその豊富な離婚協議書作成業務の中で心理学を学び、弊所独自の『離婚心理カウンセリング術』を構築しました。
そのカウンセリング時においては、相手方の生い立ちにまで遡ってお話しを聞かせていただき、あるいは依頼者様の生い立ちに遡ってまでお話しを聞かせていただき、お互いが現実をどのように認識する傾向があるかについて知っていただく支援をします。つまりお互いがどのような人間であるのかを知るプロセスを通過するのです。
己を理解し、相手を理解することによって、おのずととるべき道は見えてきます。その心理状態で、現実の問題(離婚における財産分与や親権監護権等の問題)についての解決策を依頼者自身により決定していただく支援を行っています。これが弊所が実施している「離婚心理カウンセリング」です。
その豊富な業務経験から得た「離婚に関する法律知識を依頼者様へ惜しみなく提供させていただきます。依頼者様に寄り添い、離婚後のあなたの人生が光り輝くために、離婚後にお互いが困らないための予防法務に徹した離婚協議書作成を全力でサポートさせていただきます。
公正証書離婚協議書も
お任せください
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
☎059-389-5110
(電話受付9:00~20:00 年中無休)
あなたの離婚問題を解決するため
法律面と心理面の両面において
全力サポートします!
行政書士・佐藤のりみつです
どうぞお気軽にご連絡ください
- 当事務所は行政書士事務所であり弁護士事務所や公的機関等ではないため「法的紛争の発生がほぼ不可避である事案」については受任できません。裁判外での「常識的な法律知識に基づく整除的な事項」を記載する書面での和解を考えている事案につき受任します。
離婚協議書で知っていてほしい情報
離婚するなら絶対に知っていてほしいこと
文字の上でクリックしてください。題名の記事へリンクします。
・親権者、監護者について
(親権者の決定要素、親権者の変更等)
・養育費と面会交渉権
(どちらが支払うべきなのか、養育費の額の計算、養育費をしっかり受け取るには等)
・離婚での財産分与について
(財産分与の対象、財産分与請求権の時効、離婚話中に自宅を売却された等)
・離婚での慰謝料について
(慰謝料額の算定、慰謝料請求権の時効、慰謝料をしっかり受け取るには等)
・協議離婚について
(協議離婚で決めるべきこと、離婚の話し合いで注意すること等)
・不当に離婚届を提出された場合
(離婚無効の確認、不受理申出等)
・別居にはご注意ください
(別居中の婚姻費用、同居義務違反、別居合意書等)
・離婚での荷物の処分、銀行預金、生命保険、自動車の財産分与、学資保険
・離婚後の親子の姓と戸籍、そして親権と監護権と相続権について
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
離婚届けってどこに出せばいいの?
離婚届を出す場所は婚姻中の本籍地か現住所の役場、別居をしている場合は夫婦どちらかの住民票がある役場です。
本籍地以外の役場に離婚届を提出する場合は、戸籍謄本も出さないといけません。
提出は夫婦二人がそろっていなくてもかまいません。
郵送や第三者に提出を頼んでも受け付けてもらえます。
しかし協議離婚の場合は後々のトラブル防止の観点からやはり二人で提出するか、もしくはお互いの代理人とともに提出したほうが無難です。
その際、内容の確認はしっかりしておきましょう。
提出しても、役場の戸籍課で合法と判断され受理されなければ離婚は成立しません。
ちなみに、協議離婚の場合は離婚届だけを提出すれば足りますが、他の離婚方法(後述参照)では、離婚届けの他にも提出しなければならない書類があります。
・調停離婚 調停証書の謄本
・審判離婚 審判書の謄本と確定証明書
・裁判離婚 判決書の謄本と確定証明書
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
離婚届ってどう書いたらいいの?
離婚届には届出人2人の署名押印(認印でOK)が必要です。
署名は必ず本人が行います。
(ちなみに仮に代筆されたものでも受理されてしまいますのでご注意ください)
協議離婚の場合、成人2人の証人が必要です。成人であればだれでも構いません。生年月日、住所、本籍の記載、そして署名押印をしてもらいます。
婚姻で戸籍が変わった側は、婚姻前の戸籍に戻るか、それとも新しい戸籍を作るのかを選んで記載します。
ちなみに戸籍謄本は、本籍地以外の役場へ離婚届を提出する際のみに必要です。
未成年の子どもがいる場合、両親のどちらが親権者になるかを決めて記載します。複数の子がいる場合はひとりずつ子の名前を記載します。
届出は第三者でも可能です。
ちなみに郵送の場合は役場の戸籍係に届いたときが届出日となります。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
親権者についての基礎知識
親権者とは子の身上監護権と財産監護権を持つ者です。
実子(嫡出子)については原則父母が親権者となります。
養子については原則養親が親権者となります。
協議離婚の場合、父母のどちらか一方を親権者と定めなめれば離婚できません。
裁判上での離婚の場合、裁判所は父母の一方を親権者と定めます。
ちなみに子の出生前に父母が離婚した場合の親権者は原則母です。
<参考1>
非嫡出子の親権者は母です。
その後父が認知した場合、父母の協議により父を親権者とすることもできます。
なお認知により父に親権や監護権が当然に生じるわけではありません。
<参考2>
離婚後の親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。調停手続を利用する場合には、親権者変更調停事件として申し立てます。
調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して審判をすることになります。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
親権って、何なの?
親権は、身上監護権(身の回りの世話等)と財産管理権(法律行為の代理等)から成り立つ、子供を無事大人へ育てる義務(親の子に対する扶養義務)を言います。
離婚後は、父母のどちらかが親権者とならなくてはなりません。離婚届に親権者を記載しなければならないので、親権者を決めないと離婚できない、ということになります。
子どもが成人している場合には、親権者の取決めは必要ありません。(未成年者でも、その子が結婚しているならば、成年擬制が認められ、親権者の取決めは必要ありません。)
離婚時に、妻が妊娠中だった場合の生まれた子供の親権は、自動的に母親となります。
この場合、父親が親権者となることを望むのであるならば、裁判所へ申し立てる必要があります。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
親権者の決定要素って何?
裁判所が親権者を定める判断基準は、子供の年齢、親の状況(家庭環境、居住条件、職業等)、子供の意思です。子どもの将来を見据えて、子どものために、どちらが親権者としてふさわしいかを公平に見定めます。
一般的に、10歳ぐらいまでは、子どもは母親の元で育てられる方が良いとする傾向があります。
子どもの意思とは「お父さんとおかあさんのどちらと一緒に暮らしたいか」という子どもの主張です。その子どもにしっかりとした意思能力があることが条件です。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
監護者って何?
監護者とは、親権者の権限のうち、身上監護権のみを所持する者のことです。つまり、子どもの世話や身の回りの事をすることができます。
ちなみに、監護権者は第三者でもなることができます。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
親権者を変更するのはどうしたらいいの?
親権者変更の申立書を家庭裁判所へ提出します。
しかし、その申立には「親権者が病気になり子どもを育てることが出来なくなった」等の理由が必要で、「離婚のときは親権はいらなかったけど、やっぱりこどもといっしょにいたい」等の理由ではダメです。それを許せば、子どもに混乱を招くからです。
ちなみに、親権者が死亡した場合は、家庭裁判所もしくは親族等一定の者の請求によって、子どもの後見(未成年後見人)が選任されます。もちろんこの場合でも、もう一方の親は、親権者変更の申立を行うことができます。ちなみん、親権者が遺言書を残しており、後見人の指定がある場合は、それが優先されます。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
離婚後の戸籍と姓はどうなるのか?
まず第一に、離婚をするとは、婚姻関係の終了だけでなく、相手側の両親、兄弟との親戚関係も終了します。
そして戸籍、財産、慰謝料、子供の親権、養育費等の問題が生じます。
さらに、離婚後の生活をどう成り立たせていくのかも考えなくてはなりません。
離婚とは、一度作り上げたものを解体して、そこからの再出発であるのです。
このことを肝に銘じて、ご自身の人生の岐路を選択なさるようにしてください。
■離婚後の戸籍について
婚姻届を出すと男女二人の新しい戸籍が作られます。
これが離婚することにより2つに分かれます。
つまり、一方配偶者の戸籍に入った(入籍した)者(つまり婚姻で姓が変わった者)が、離婚によってその戸籍から除外(これを除籍といいます)されるのです。
その後、除籍された一方配偶者は、結婚前の戸籍に戻るか、もしくは新たに戸籍を作ることになります。
■離婚後の姓について
夫婦どちらかの戸籍から除籍された側は、基本的には元の姓を名乗ることになります。
ただし、婚姻中の姓を引き続き名乗りたいという場合は、離婚成立から3か月以内に市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば、婚姻中の姓を名乗ることができます。
なお、子どもの戸籍は変わらないので、姓も変わりません。
子どもの姓を変えたい場合は、「子の氏変更許可申立書」を家庭裁判所に申し立てなくてはなりません。
※子どもが15歳以上の場合、本人が姓の変更を拒否すると変更できません。
子どもの戸籍を移すときは、「子の氏変更許可」の審判が下りた後、入籍届に審判所を添付して市区町村役場の戸籍係に提出します。
ちなみに、子どもの姓だけ変えて、子どもが元配偶者の戸籍に残ることはできません。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
養育費はどっちが払うの?
養育費は、子どもと暮らさない親が支払います。ですので、必ずしも父親が支払うものではありません。
養育費は、親の子に対する生活保持の義務から生じていますので、子どもと離れて暮らす親は、たとえ経済的に苦しくても、自分の瀬活費を削って支払う義務があります。
ちなみに、養育費の範囲は、食費、服代、教育費、医療費、娯楽費、保険料等に渡ります。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
養育費の額ってどうやって決めるの?
養育費の額は、夫婦の話合いで決定します。
決定出来ない場合は、家庭裁判所で決めてもらいます。
では、家庭裁判所ではどのようにして養育費の額を算出するのでしょうか?
①実費方式
これまで子供にかかった費用、これからかかる費用(不定期にかかる費用も含む)、夫婦の収入や財産と今後の見通し、等を具体的に列挙し、妥当な額を決める方式。
②生活保護基準方式
厚生省が定める基準です。しかしこれは最低限の生活を満たす金額がベースになります。
③労働科学研究所方式
昭和27年の消費単位100あたりの最低生活費を7000円として、現在の消費者物価指数に応じて修正し算出する方式。
④東京・大阪養育費等研究会発表の養育費・婚姻費用の算出方式・算定式から導き出された早見表
相手と自分の収入、子どもの年齢と人数(二人まで)を早見表に当てはめると、養育費や婚姻費用の目安が出ます。
※「養育費・婚姻費用早見表」を見たい方は、弊所へご連絡ください。
☎059-389-5110
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
養育費の額って増減できるの?
特別な事情があれば、養育費の増減は可能です。
増額の例は、
・子供が病気やけがで入院したり、進学等で、離婚時に決めた養育費以上のお金がどうしてもひつようになった場合等
・子どもを育てている親が病気をしたり、失業して収入が減った場合等
減額の例は、
・養育費を支払う親が、経済的に困難な状況に陥った場合等
・子供を育てている親の収入が増えて、離婚時に決めた養育費がなくても、経済的安定を得られる場合等
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
養育費を確実にもらうにはどうしたらいいの?
協議離婚の場合は、養育費の取決め事項を、強制執行認諾約款付公正証書に記載することです。
そうすれば、養育費の支払いが滞った場合、強制執行をかけ、相手の財産や給料を差押えることが出来ます。
なお、民事執行法の改正によって、養育費については、滞納分だけでなく、将来分を含めた額まで差し押さえができるようになりました。給料の差し押さえは、手取り額の1/2まで差押えることが出来ます。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
面会交渉権について
面会交渉権(面接交渉権ともいいます)は、未成年の子のいる夫婦が離婚した場合等に、親権者もしくは監護権者でない親が、その未成年の子と面接し交渉する権利をいいます(有斐閣「法律用語辞典第3版」参照)。
この面接交渉権について、直接的に規定した法律は、実はありません。
民法766条1項の「監護について必要な事項」、同法同条2項の「監護について相当な処分」等が、面接交渉権の法根拠になると考えられています。
また、判例でも「親権もしくは監護権を有しない親は、未成熟子と面接ないし交渉する権利を有し、この権利は未成熟子の福祉を害することがない限り、制限され又は奪われることはない」(東京家庭裁判所昭和39年12月14日審判)と判示されています。
これだけみると、親だけの権利と思いがちですが、実は、面会交渉権は、親の養育を受ける子の権利であり、だから親には養育義務があり、その義務を全うするためには、親は子に会わなくてはならないので、親にも面会交渉権がある、という理屈です。
離婚時に、夫婦の話合いによって、面会回数、場所、日時、運動会・入学式、手紙や電話、SNSでのやりとり等を決めておきましょう。
親の一方が面会交渉を絶対に認めないような場合、家裁へ面接交渉の調停を申立てます。
また、諸所の事情により、面接交渉権の制限を求めているのに相手側が認めないような場合は、面接交渉制限の申立てを家裁へすることができます。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
離婚での財産分与の対象
夫婦どちらか一方の名義で購入した不動産などは、名義がどちらになっているかにかかわらず、夫婦が協力して得た共有財産とみなされ財産分与の対象となります。
婚姻前に自分名義で購入したものや貯金、相続によって取得した財産は特有財産(夫婦それぞれに所有権がある財産)となり、財産分与の対象とはなりません。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
離婚における財産分与の詳細
財産分与とは、婚姻中に夫婦で取得した財産を離婚するときに精算し、互いの寄与分に応じて分けることです。
仮に夫名義、妻名義の財産であっても、婚姻中に取得した財産であれば夫婦の共有財産とみなされます。
婚姻中に取得した財産は互いの協力があったから得られたとの考えから、妻に収入が無くても財産分与請求権は当然に認められます。
とにかく離婚したいからといって財産分与について何も取り決めず、または財産分与請求権を放棄すると記載された離婚協議書にサインして離婚した場合で、その後相手が財産を処分してしまったら、財産を全くもらえない結果となる可能性もあります。
負の財産(ローンなど)も財産分与の対象となるので注意しましょう。
財産分与を取り決める際は、不要的要素も考慮します。離婚後の妻の生活保障等が例です。
婚姻期間中に別居期間がありその間生活費を入れてもらっていなかった等生活費の未払い期間がある場合は、財産分与で調整できます。
なお財産分与は慰謝料とは別扱いです。
しかし財産分与に慰謝料を含めることも出来ます。
この場合、提示された額が不十分と考えられるのならば別途慰謝料を請求できます。
財産分与に慰謝料を含めるか否かはトラブルの原因となりかねませんので、互いがきちんと把握した上で財産分与を取り決めることが必要です。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
離婚における財産分与請求権の時効
離婚後2年以内に申し出ないと消滅してしまいますのでご注意ください。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
離婚における財産分与の対象になる財産って何?
・婚姻してから貯めた預貯金。
・婚姻後に取得した不動産。
・婚姻後に取得した株券、国債、社債等の有価証券、ゴルフ会員権等
・個人事業を営んでいてその事業を手伝っている場合はその収益。
・夫の退職金(後述参照のこと)
・年金(後述参照のこと)
・負債
※夫婦どちらか一方が借金をしている場合は他方が負債を負うことはありません。しかし相手の負債の連帯保証人になっている場合はたとえ離婚しても連帯保証人の立場は変わりませんのでご注意ください。
これらを夫婦の共有財産といいます。
では離婚時における財産分与の対象とならない財産(特有財産といいます)はどのようなものがあるのでしょうか?
・婚姻前から所有している財産
・婚姻中に親から相続した財産
・夫婦の一方が経営している会社 ※株券は財産分与の対象となります
・婚姻後に取得した資格
※医師免許や弁護士、税理士等高収入を見込める資格を取得した場合は財産分与の対象となる可能性があります。
・日用品 ※高額な家電製品などは財産分与の対象となることもあります。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
ヘソクリは離婚における財産分与の対象になるの?
ヘソクリも夫婦の共有財産となりますので、財産分与の対象となります。
しかし「ヘソクリは妻の小遣いにしてよい」などの合意があれば、それは夫から妻への贈与となり、そのようなヘソクリは妻の特有財産となりますので財産分与の対象とはなりません。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
退職金は離婚における財産分与の対象になるの?
退職金は賃金の後払い的性格をもつと考えると、婚姻期間中に給料を貯めた預貯金とみなすことができ、この理論で考えると、退職金も「離婚時における財産分与の対象と言えます。
しかし、退職金は将来もらえるかどうか不確かなお金です。会社が倒産したり、懲戒解雇を受けたりなど、退職金が全く支給されないケースも考えられます。
また、世情の変化により、退職金の増減は十分あり得る話です。
ですので、離婚時に将来もらえるはずの退職金を分けることは、分け与える側にとってはかなり「酷」な話でもあります。
では裁判所はどう判断しているのかというと「既に支給された退職金が離婚時における財産分与の対象となるのは当然である。しかし将来の退職金については、近い将来に受け取る可能性が高い場合には財産分与の対象となる」としています。つまり、数年後に定年退職が見込まれるような場合に認められる、ということです。
最期に、その分け方のパターンを説明します。
①将来の定年時の退職金を基準として、婚姻期間中に相当する額の1/2を、離婚のときに支払う
②将来の定年時の退職金を基準として、子人期間中に相当する額の1/2を、退職金の支給時に支払う
③離婚のときに退職したと仮定して算出した退職金の額を基準にして、婚姻期間に相当する額の1/2を、退職金の支給時に支払う
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
専業主婦でも財産分与の請求はできます!
妻が家事労働をしながら家庭を支えてきたので、夫は働いて収入を得て、きちんと預貯金できた(財産構築出来た)、ということであり、妻も財産構築に寄与していますので、婚姻期間中、妻に全く収入がなくても、財産分与請求は可能です。これを、精算的財産分与といいます。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
離婚における財産分与と慰謝料の税金について
現金預貯金の場合は税金はかかりません。ただし社会通念上相当額を超える額の財産分与や慰謝料があった場合、所得税がかかる場合があります。
土地、建物、有価証券等については、離婚における財産分与をすると「売買行為があったとみなす」となり、財産分与の時の時価と取得時の時価との差額に対して、分与した側に所得税がかかります。
不動産の財産分与を受け取った側には、不動産取得税がかかります。それと、土地や建物の変更登記をする際の免許税もかかります。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
離婚協議中、夫が自宅を売却しようとしている!
離婚話をしている最中に、自分名義の財産を相手に渡すくらいなら売ってお金に換えてしまおう、と考え行動に起こす人も中にはいます。
これを実行されてしまうと財産分与を請求しても取りようがありません。
こんな場合は民事保全法による仮処分を裁判所へ申し立て、不動産、預貯金、退職金等を差押えておくことができます。※保証金が必要になります。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
慰謝料についての基礎知識
浮気、暴行、虐待等の不貞行為により精神的・肉体的に苦痛を与え離婚の原因を作った方に対して請求できるのが慰謝料です。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
離婚における慰謝料請求について
慰謝料は、離婚の原因(不貞行為・DV等)を作った側が支払う金銭賠償ですので、有責性が五分五分の場合や、性格の不一致等の場合は、慰謝料を請求することはできません。
では、浮気をしたのは夫だが、そもそも夫が浮気をしたのは妻が夫につらく当たる(甚だしい侮辱をするなどのDV行為)場合などはどうなるのかというと、これは、どちらに有責性がどれだけあるのかを見極めなくてはなりません。協議で解決できなければ、残念ながら調停、裁判で決着をつけることになります。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
離婚慰謝料を請求できない場合ってあるの?
有責性が五分五分の場合や、性格の不一致等の場合は、慰謝料を請求することはできません。
また、夫婦関係の破たんが明らかであって、破たんの後に配偶者の不貞行為があった場合も、不貞行為が直接の離婚原因ではないとして、慰謝料を請求できません。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
離婚慰謝料請求権の時効
離婚後3年を過ぎると時効で離婚慰謝料請求権は消滅してしまいます。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
慰謝料の金額ってどうやって割り出すの?
浮気、暴力、家庭放棄等の離婚原因(有責性)の程度、慰謝料を請求する側の精神的苦痛の程度、慰謝料を請求する側及び支払う側の生活力、経済力、さらには婚姻にいたる経緯、婚姻期間、別居期間、婚姻期間における夫婦生活の態度、子供の人数・年齢、親権・監護権の問題等々を考慮して決定します。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
財産分与や慰謝料を確実にするためにはどうすればいいの?
口約束だけでも契約は成立します。
しかし、言った言わないの問題となればそれまでですし、口約束で訴訟を起こしても、その立証は難しく、つまり、口約束に強制力はないに等しいのです。
ですから、離婚協議書の作成をお薦めします。
これ、養育費を支払う側は作りたくないと思います。
でも違うのです。
離婚協議書には、精算条項を必ず入れます。つまり、離婚協議書の内容以外には一切の請求をお互いにしないと合意する文章を入れることで、離婚後の慰謝料や財産分与請求権を消すことができます。
また、財産分与や慰謝料を一括ではなく、分割で支払ってもらうような場合には、公正証書化することをお薦めします。
公正証書は債務名義ですので、強制執行が可能となるからです。
これを強制執行認諾約款付公正証書といいます。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
協議離婚ってなに?
協議離婚とは、夫婦が互いに離婚に合意して離婚届を市区町村役場へ提出し受理されて成立する離婚です。
離婚の90%以上が協議離婚です。
離婚届を提出するにあたって明確にしておかなければならないのは夫婦の離婚の意思と、子供の親権者はどちらがなるのか、の二点です。
協議離婚は手続きが簡単で時間も費用もかかりませんが、その分慎重に事を決めて行く必要があります。離婚を焦っても感情的にならず冷静に離婚協議を進めなければ、不利な条件で離婚をする結果になります。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
協議離婚する前に決めておくことがあります!
離婚届に判を押すのは最後の最後と覚えておいてください。
協議離婚をする前には決めておかなければ後で後悔することが多々あります。
・親権者を決めておく。そもそも親権者を決めないと離婚できません。
・離婚後、新しい戸籍を作るのか、それとも婚姻前の戸籍に戻るのかを決めておく。
・財産分与を決めておく。住宅ローン等はその支払方法や分割方法を決めておきましょう。
・子供の養育費を決めておく。どちらがいくらをいつどのように支払うのかを明確にしておきましょう。またいつまで支払続けるのかも決めておきましょう。
・子供との面接交渉権を決めておきましょう。親権者でなくても愛する子供へ面会する権利はあります。いつどこで何時間、どのようにして会うのかを決めておきましょう。
・年金分割についても決めておきましょう。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
離婚協議書ってどうして書いた方がいいの?
協議離婚の場合、夫婦の合意だけで重要な事項を約束します。
財産分与の支払、慰謝料の支払、養育費の支払、子どもとの面会、ローンの支払等々。
これらの約束が実行されなかった場合、口約束だけでは言った言わないの問題となりかねません。
ですから法的証拠として離婚協議書を書面として作成しておくことが重要なのです。
しかし離婚協議書だけでは法的に強制力はありません。
もし強制力を持たせたいのなら、離婚協議書を公正証書化し、強制執行認諾約款を盛り込む必要があります。
そうすればお金の支払に関しては強制執行力を持たせることが出来ます。
公正証書は、まずは離婚協議の内容を二人で決めて、その内容を持って公証役場へ赴き、公証人に作成してもらいます。
作成する際は夫婦双方の署名、実印、印鑑証明書、戸籍謄本が必要となります。
夫婦の一方が出向けない場合は委任状を持った代理人をたてます。
また、離婚協議書に盛り込むのが適当でないような事項については念書を取るなどして、とにかく離婚に際して約束したことを書面に残すことが重要です。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
協議離婚を進めるにあたっての注意事項
離婚の話し合いをする際には、とにかく冷静になりましょう。
そしてある程度の時間をかける気で話し合いましょう。
話合いの場はできたら外の方がお互い冷静になれると思います。
法的な疑問点などは専門家に相談しましょう。
また、これは私見ですが、離婚の話し合いに子どもを巻き込むのはやめた方がいいと思います。子どもの心にトラウマを残すだけです・・・・
それと、お互い主張するばかりでなく、どこかで着陸点(妥協点)を見出すようにしましょう。
相手が離婚しない!っと心変わりしてしまったら、離婚の話し合いすら出来なくなってしまうからです。
とにかく、感情がもつれすぎないようにすることが肝心です・・・・
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
不当に離婚届を出されてしまった!
相手から不意打ちで離婚届を提出されてしまった場合でも、すぐに役場の戸籍係に連絡して戸籍に記載される前であれば、「それは無効な離婚届です!」っと言えばその離婚届は受理されずに差し戻されます。
不運にも戸籍に記載されてしまったら、家庭裁判所へ離婚無効の確認を求める調停を申立てなくてはなりません。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
離婚届けの不受理申出書について
不当に離婚届を作成されて届けられる可能性がある場合、市区町村役場の戸籍係に不受理申出書を提出しておけば、相手から離婚届が提出されても受理されずにすみます。
申し出を撤回する場合は取下書を提出します。(取り下げるまでは有効のままです)
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
別居にはご注意を!
夫婦仲が悪くなったからといって、相手に何も告げずに家を飛び出してしまうことはやめておきましょう。
夫婦には同居義務があります。違反しても罰則規定はありませんが、同居義務違反は離婚原因とされ、有責配偶者とされる可能性が高いです。
こんなときは、別居を相手側と話し合って、別居合意書を取り付けておきましょう。
なお、DVを受けていたような場合は正当な理由有りとして無断で家を飛び出しても有責配偶者とされることはありません。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
別居中の婚姻費用って請求できるの?
別居していても、夫婦には夫婦の生活費と子どもの養育費(これらを婚姻費用といいます)を分担する義務があります(民法760条)。
別居する際には婚姻費用の金額と支払条件を決めておきましょう。
別居合意書にきちんと記載しておきましょう。
もし相手側が支払を滞納した場合は婚姻費用の分担調停を家庭裁判所に申し立てることも出来ます。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
民法における離婚原因
民法770条に定められているのが離婚原因です。
裁判離婚では、下記の離婚原因に当てはまらなければ離婚できません。
しかし協議離婚の場合には、離婚することに合意があり、離婚届けが行政に受理されれば離婚が成立します。
・不貞行為があったとき
不貞行為とは配偶者のある者が自由意志で別の異性と性的関係を持つことです。
しかし一回だけの浮気でしかも反省を十分にしているような場合は婚姻関係を破たんさせたまでとはいいがたいので不貞行為とは認められません。
でも一回限りの浮気を何人もの人としていたような場合は明らかに不貞行為です。
プラトニックな関係でも婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるような場合は離婚原因となる可能性があります。
・悪意の遺棄
夫婦は同居しお互いに協力扶助しなければならない(民法752条)と定められているので、この義務に違反すると悪意の遺棄とされます。つまり、夫婦関係が破たんするとわかっていながら夫婦の協力義務を怠ることです。愛人の家にいりびたりであったり、生活費を稼がなかったり、家出を繰り返したり、相手を家に入れなかったり、といったことがあげられます。
・相手の生死が3年以上不明の時
生死不明となった原因は問われませんが、離婚する際には警察に捜索願を出したというような証拠が必要となります。
・回復見込みのない強度の精神病
精神障害によって夫婦生活における役割や協力が十分に果たせない場合です。強度の精神病とは統合失調症、麻痺性認知症、躁うつ病等が該当します(最終的には精神科医の鑑定に委ねられます)。アルコール依存症、ヒステリー、ノイローゼは該当しません。
・婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
とても広範囲な条文です。
具体的には、性格の不一致、性の不一致、性交渉の拒否、異常な性交渉を強要する、配偶者の親族との不和、暴行虐待、宗教活動等が挙げられます。 つまり夫婦関係が修復不可能なまでに破たんし、離婚はやむを得ないと判断されるような事由のことです。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
離婚の原因を作った方からの離婚請求ってできるの?
離婚原因を作った方を有責配偶者と言います。
結論から言うと、有責配偶者からの離婚裁判請求も可能です(最高裁判例S62.9.2)。
しかし条件があります。
①夫婦間に未成熟子(親から独立して生計を営むことが出来ない子)がいないことが必要
②長い別居生活が存在し、夫婦関係が破たんしていることが必要
※6年の別居期間が判例上最短ですが、別居期間が長ければいいのかというとそんなことはなく、有責配偶者に誠意があるか等も判断材料となります)
③配偶者が離婚によって精神的、社会的、経済的に苛酷な状態におかれないことが必要
例えば離婚にさいして十分な財産分与や慰謝料が確実に支払われ、離婚後の生活を問題なく送ることが出来るような場合です。
このように有責配偶者からの離婚請求には高いハードルがあるのが事実です。
しかしこの判例を逆から見てみると、内縁者と別宅を持っている夫と長年別居しているが離婚は絶対にしないという妻が、有責配偶者である夫から離婚を請求された場合、離婚せざるを得ない可能性もあるということです。
ただし、協議離婚や離婚調停に関しては、有責配偶者であろうと、一方配偶者に離婚を請求することになんら規制はありません。
また、話は変わりますが、上記の場合、夫の遺族年金が内縁者に持っていかれる場合も条件次第ではあります。
正妻と長期間別居していて、生活費の負担等夫婦の扶養被扶養の関係が存在せず、婚姻関係の修復努力を怠り結果婚姻関係の実体がなくその修復の余地もない場合で、さらに内縁者との関係が夫婦生活同然であり、男性(不倫をしている夫)の収入で生活を維持しており、内縁者が男性の死まで看護し続けた場合、遺族年金を内縁の妻に支給するとした判例があります。
お気を付けください。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
離婚における年金分割について
平成19年4月からはじまった離婚時の年金分割制度は、期間中の厚生年金(共済年金)の保険料納付記録(夫婦合計)をもとにして話し合いにより按分を決めます。
合意しない場合は、一方の請求により裁判手続きにより分ける割合を求めることができます。この請求は、原則離婚した時から2年以内にしなければいけません。
調停でまとまらなければ審判、裁判へと移行し、最終的に判決や和解で按分率が決定されます。
夫婦が揃って年金事務所に赴いて手続するのでない限り、私的な協議書だけでは手続きは出来ません。年金分割の合意の書面については、公正証書、もしくは合意書に公証人の認証(私署証書認証)を受けたものが必要です(私署証書認証とは、合意書の署名押印が本人のものであるということを証明する手続を経て作成された文書。公正証書作成より簡単な手続で費用も安い)。
公正証書の場合には原則的に夫婦揃って公証役場に出向かなければならないが、私署証書認証ならたいてい代理人でも手続きが可能です。
※公正証書を作ったとしても、2年以内に年金事務所で手続しなければ年金分割はされない。
・年金分割の際の按分割合の決め方
婚姻期間中の夫婦の標準報酬総額の合計を100%とした場合、分割を受ける側(たいていは妻)がそのうち何%を受け取れるかということで、最大50%ということになります。下限はケースバイケース。
妻がずっと専業主婦だった場合には下限が0%となるが、妻も働いて厚生年金に加入していた期間があれば既に何%か持分があるので、その分は確保される。
つまり、年金分割の合意をする場合には、按分割合を何%から何%の間で決めたらよいのかを事前に確認しておく必要があるということです。
そのためには年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出する必要があります。
用紙は年金事務所にあるので、それに記入して提出することになります。このときに免許証などの本人確認書類や年金手帳、認め印のほか、婚姻期間を確認するための戸籍謄本が必要です。
なお、請求してから回答がくるまでだいたい3週間程度かかります。
離婚前であれば請求した本人のみに通知書が送られ、離婚後であれば請求者本人と元配偶者の双方に送られます。また、原則郵送で送付されますが、離婚前で配偶者に年金分割を準備していることが知られたくないという場合は、年金事務所での窓口受取りや送付先の住所を指定することも可能です。
・年金分割をした場合の年金見込額の通知
「年金分割のための情報提供請求書」を出す際、請求者が50歳以上の場合、希望すれば年金分割をした場合の年金見込額も一緒に知らせてくれます。
具体的には、年金分割をしなかった場合の年金見込額と、上限50%で年金分割した場合の年金見込額、それ以外の按分割合で分割を希望するならばそれに対する年金見込額を教えてもらえます。
これを見ると、一目瞭然で、年金分割をした場合としなかった場合の年金額の違いがわかります。
なお、「年金分割のための情報提供請求書」は夫婦二人一緒に出すことも、一人だけで出すこともできます。ちなみに、一人だけで請求した場合、離婚前には本人に関する情報しか教えてもらえない。
・年金分割(合意分割・離婚分割)の手続き
具体的には「標準報酬改定請求書」という改定請求書類を提出します。年金分割の手続きは離婚が成立した後でなければ手続きをすることができません。
按分割合の決定方法は通常「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」の4種類。それぞれの決定方法でどういった年金分割の請求手続きが必要なのかは下記を参照してください。
○「協議離婚」の場合
原則双方が年金事務所に一緒に行き、年金分割の改定請求を行ないます。どちらか一方が手続きをすることはできず、必ず2人一緒に行かなければいけません。必要な書類は「年金分割の合意書」、双方の戸籍謄本、双方の年金手帳が必要。
しかしながら、離婚した後に一緒に年金事務所に行くというのは嫌だという人も少なからずいるかと思います。その場合は、代理人が請求手続きをすることもできます。ただし、代理人が手続きをする場合でも、元夫の代理人と元妻本人、元夫本人と元妻の代理人、元夫の代理人と元妻の代理人というように必ず2人で一緒に行かなければなりません。
なお、代理人が手続きに行く場合は、必ず年金分割専用の委任状が必要となります。
このほか、協議離婚で公正証書、公証人の認証を受けた証書がある場合は、「年金分割の合意書」に代えてこれらの証書を添付すれば、2人一緒に行く必要はなく、どちらか一方が手続きすることが可能です。
○「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」の場合
調停、審判又は裁判で按分割合が決定された場合は、どちらか一方が年金事務所に行って手続きを行うことができます。その際に必要な書類は、調停等で決定された謄本、双方の戸籍謄本、年金手帳です。これで離婚時の年金分割の手続きは完了です。後日郵送で年金分割が決定した案内が年金機構から送付されます。
■3号分割
平成20年4月から施行された離婚時の第3号被保険者期間の年金分割制度(3号分割)は、名前の通り離婚した場合に当事者一方の請求により自動的に2分の1に分割することができます。
3号分割の請求はいつでもできます。
ただし、自動的に分割されるのは、同法施行後の第3号被保険者期間のみに限定されます。つまり平成20年4月より前について、または共働き期間については、当事者の合意による按分決定が必要ということです。
年金を受給するために必要な加入期間は、公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)制度全体を通じて25年以上です。
3号分割の手続きは、住所地の年金事務所(旧社会保険事務所)に第三号年金分割の請求をします。
また、相手との協議なしに按分割合は自動的に二分の一となるので、公正証書などを提出する必要はありません。
必要書類は標準報酬改定請求書(社会保険事務所に備え付けています)、請求者の国民年金手帳、年金手帳、又は基礎年金番号通知書、戸籍謄本、戸籍抄本等の婚姻期間等を明らかにできる書類です。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
離婚公正証書作成にかかる公証役場への費用について
●手数料制度の概要
公証人が、公正証書等を作成した場合の手数料は、政府が定めた「公証人手数料令」という政令により定められています。 |
手数料は、原則として、証書の正本等を交付する時に現金で支払います。 |
金銭消費貸借契約、土地の賃貸借契約、土地の売買契約等には、公正証書に印紙税法による印紙の貼付が必要となります。 |
|
●法律行為に関する証書作成の基本手数料
契約や法律行為に係る証書作成の手数料は原則その目的価額により定められます。
目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。
贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、交換契約のように、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。 | ||||||||||
数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。法律行為に主従の関係があるとき、例えば、金銭の貸借契約とその保証契約が同一証書に記載されるときは、従たる法律行為である保証契約は、計算の対象には含まれません。 | ||||||||||
| ||||||||||
法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
具体例を下記に記します。
|
交付送達・離婚公正証書を作成したら手続きしましょう
裁判所で強制執行の手続をするためには、債務者(養育費等の支払い義務者)へ公正証書が渡されていることを証明する送達証明書が必要になります。これを交付送達といいます。
送達は、当事者が配達証明などで郵送しても証明とはなりません。
どこの公証役場からでもかまいませんので、送達の申請をして、公証人の名前で債務者へ公正証書謄本等を特別送達という手段で郵送し、証明書を受取る必要があります。
離婚公正証書を作成する意義として、養育費の支払い等が滞ったときに、強制執行を裁判所へ申し立てやすくなる、ということがありますが、この交付送達をしておかないと、強制執行の申立てが出来ません。
ですので、離婚公正証書を公証役場で作成したら、その場で交付送達の手続きをすることをお薦めします。なぜかというと、後述しますが、債務者(養育費等の支払い者)の所在が分からなくなると、送達手続きが出来ない、もしくは所在を突き止めるのに時間がかかり、交付送達が出来ない=強制執行の申立てが出来ない、という事態になりかねないからです。
公正証書作成当日に、債務者本人が公証役場に出向き調印する場合は、公証人からの交付送達という手続ができます。
後日、謄本の送達をされる場合は郵便代がかかりますが、離婚公正証書を作成したのと同時に手続きすれば、手渡しで送達しますので郵便代がかかりません。
また、支払が滞ってからの送達ですと、債務者の方の住所が不明になるなどして送達がなかなかできないということがあります。交付送達をされていれば、後日の手続に心配がありません。
交付送達を希望する場合、公正証書を依頼際にその旨を公証人へ伝えておく必要があります。
連帯保証人などにも送達される場合は、それぞれに謄本を作成しますので、手数料の他に謄本代が加算されます。
※交付送達を行うには、公正証書作成当日に、債務者が出席していることが必要です。
※公正証書作成当日に債務者が出席しない場合(債務者が代理人を立てたような場合)、特別送達を続きすることは可能ですが、債務不履行を起こしているわけではないので、執行文は記載されません。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
離婚での不動産の財産分与における税金
●贈与税について
離婚での財産分与では、原則、贈与税は課税されません。
離婚での財産分与請求権に基づき「自分の持分」を受け取ったものと考えます。ですので、不動産を離婚での財産分与として分配する場合、原則、贈与税は課税されません。
しかし、次の場合には贈与税がかかります。
①分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮しても、なお多すぎる場合
→多すぎる部分に贈与税がかかります。
②離婚が贈与税や相続税を不当に免れるために行われたと認められる場合
→離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
(注意)
財産分与として不動産を分配する場合でも、税務署へ「離婚での財産分与」と説明できない場合、贈与税が課税される可能性があります。よくある例ですと、「離婚から数年後、住宅ローンが完済した後に所有権の移転登記をおこなう」という場合は注意が必要です。この場合、税務署に「○年前における離婚での財産分与が登記原因である」と、客観的証拠をもとに説明する必要があります。客観的証拠としては、離婚協議書もしくは離婚公正証書がベストです。
●譲渡所得税
不動産の場合「財産分与のときの不動産の時価」が「不動産取得時の時価(建物については減価償却後の価額)」よりも大きければ、その差額(=譲渡益)に対し財産分与をした方に譲渡所得税がかかります。(不動産の値段が下がっていて譲渡益がない場合やマイナスになった場合、他の給与所得等と損益通算をして税金が還付される場合もあります)
しかし、譲渡益が存在していても、財産分与をする側の譲渡所得税を抑える方法もあります。これは、登記簿における不動産の所有権移転登記を「離婚前」にするのか「離婚後」にするのかで変わってきます。
譲渡所得税と贈与税には、下記①②の控除制度が存在します。
①居住用不動産であり、譲渡する相手が親族でない場合、時価3000万円までの譲渡益が非課税となる
②婚姻期間20年以上の夫婦が居住用資産を贈与する場合、贈与税に関して2000万円の配偶者控除がされる
①の制度利用するのならば「離婚成立後」に登記簿における不動産の所有権移転登記をしなければなりません。
②の制度を利用するのならば「離婚成立前」に登記簿における不動産の所有権移転登記をしなければなりません。
※この二つの控除制度は居住用不動産にのみ適用される制度です。つまり、不動産の所有者が実際に居住している不動産を譲渡する場合限定です(別荘等は該当しません)。また、その不動産に居住しなくなって3年以上が経過している場合もこの控除制度に該当しなくなる場合があります。
●不動産取得税
離婚での財産分与で不動産を分配されると、原則「分配された側」に固定資産税評価額の3%(ただし、土地の場合はその1/2)にかかる不動産取得税が課税されます(建物については1200万円を固定資産税評価額から控除される)。
しかし、離婚での不動産取得税は「夫婦の財産の清算」として分配された分に関しては課税されません。これは贈与税の時と同じ理屈で、実質的にはもともと一方配偶者の持分であった所有権の確認であり、実体として財産移転ではない、との考え方からです。
でも「慰謝料として不動産を受け取った場合」や「離婚後の妻の生活保護のため夫が不動産を妻に分配した場合」等においては不動産取得税が課税されます。
不動産取得税は、離婚協議書等に「分配した側が支払う」等の記載をし、夫婦の合意として双方が署名押印等しておけば、不動産を分配された側の支払義務支はなくなります。
●法務局への登記登録免許税
一方配偶者から分配された不動産の所有権移転登記にかかる法務局に対してしはらう税金のおとです。財産分与を受けた側に、固定資産税評価額の2%の登録免許税が課税されます。
離婚協議書等に「分配した側が支払う」等の記載をし、夫婦の合意として双方が署名押印等しておけば、不動産を分配された側の支払義務支はなくなります。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
離婚後の親子の姓と戸籍、そして親権と監護権と相続権について
日本ではよくあるケースを例として挙げます。
男女が結婚し、夫を筆頭者とする戸籍に妻が入籍し、妻は夫の姓(氏)を名乗っています。その戸籍に子どもが一人います。
この夫婦が離婚することとなりました。
この場合、結婚の際に姓(氏)を変更した一方配偶者(妻ですね)が、筆頭者が夫である戸籍から出る(これを除籍といいます)こととなります。
離婚届を出す際、妻は従前の戸籍に復籍するか(たとえば自分の父親が筆頭者である戸籍に戻るとか)もしくは妻単体で一つの戸籍を作るのかを選択します。
この際、妻の姓(氏)は原則旧姓に戻ります(婚姻時に使用していた氏を離婚後も継続して使用したい場合は離婚から3か月以内に「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を役所へ提出すれば、婚姻時に使用していた氏を名乗ることが可能です。しかしこれは離婚時に妻が妻単体の戸籍を選択した場合です。実父の戸籍に復籍した場合は不可能です。なぜならば、同じ戸籍にいる人は同じ氏を名乗らなければならないからです。
離婚時に妻が妻単体の戸籍を選択したとします。
この場合、子どもの戸籍は筆頭者が夫である戸籍に残ります。ということは、子どもの氏は夫と同じということです。監護権も含めた親権を離婚届において妻が持つとした場合、離婚して旧姓に戻った妻と妻が引き取った子供の氏は異なることとなります。
離婚した妻の氏と引き取った子どもの氏を同じにするのなら家庭裁判所へ子の氏の変更許可申請を行います。同じ氏を名乗るなら同じ戸籍に存在する必要があるので、ここで初めて子の戸籍を離婚後に出来た妻単独の戸籍へ移すこととなります。
よく相談を受けるのですが、子どもの戸籍が離婚した夫の戸籍にあろうが、離婚した妻の戸籍にあろうが、親権や監護権の決定とはなんの関係もありません。戸籍とは、日本人の所在を管理する制度であり、親権は制限行為能力者である未成年者を守る制度であり、全く別の目的を持つ制度だからです(戸籍には親権者が記載されますが、それは親権者が戸籍記載事項であるだけの話です)。離婚して旧姓に戻った妻が、元夫の戸籍にある子どもの親権者になることに全く問題はありません(この場合、妻と子供の氏は異なることとなりますが)。
親権者は子ども(未成年者)の財産管理と、子ども(未成年者)の身上監護をする権利を有します。
財産管理は子ども名義の財産を子どもにかわって管理することです。
身上監護とは、子どもの身の回りの世話やしつけをすることです。身上監護をもう少し詳しく説明すると下記に分類されます。
・監護教育権
子供を監督・保護・教育する権利と義務
・居所指定権
子どもの生活の場(居所)を指定できる権利。ただし、子どもがある程度の判断力を持つに至ったとき(12歳程度)は、子どもが親権者の居所指定に従わない場合でも、同居を強制する法的手段はありません。※断能力のない乳幼児等が、親権者以外の者の支配下に置かれているような場合、子の引き渡しを請求することができます。
・懲戒権
しつけとして懲戒をする権利。具体的には「叱責」「軽くたたく」程度の社会常識の範囲内で認られる程度の躾を指します。ということは、社会常識をを超えた制裁は不法行為となる可能性があります。
・職業許可権
子どもが職業に従事することに許可を与える権利。つまり、子どもは親権者の許可なくして就職できないというになります。
婚姻中の夫婦は二人で監護権を含む親権を行使できます。
離婚する場合は、離婚届に子どもそれぞれに親権者を決定し記載します。
離婚時に親権者と監護権者をわけることもできます。
監護権と別々になった親権の範囲は、子どもの身分上の行為の代理権(役所や裁判所への手続き等)と財産管理権等の法律的な手続きにおいて権利を有します。
対して、親権と別々になった監護権の範囲は、実は法律的に明確な規定はありません。一般的には親権の身上監護権から子育て以外の法的手続きを除いた範囲であるとされています。つまり、子どもの世話や教育をする、子どもの住まいを指定する、子どもの職業を許可する等の権利を有するとされています。
親権は子が未成年の間の話です。子どもが成人してしまえば、(成人した)子どもの居所や職業の決定権は(成人した)子どもにあります(憲法で保障されています)。
つまり「子どもはうちの跡取りだから離婚後の子どもの親権は私がもつ!子どもの戸籍が妻単独の戸籍に移すなんてもってのほか」とかの主張は、戸籍や親権の観点からすると、ほとんど意味を持たないのです(もちろん、育ててくれた片親に恩義を感じて「家業を継ごう」等の意志表示を子どもがするという可能性はありますが)。
そして、離婚したとしても、男親は子どもの父親であり続けますし、女親は子どもの母親でありつづけます。つまり、親子には相互に扶養義務が存在し続けます。
また、離婚した夫婦は赤の他人となりお互いに相続権は一切有しませんが、別れた父親と子ども、別れた子どもと母親との間には相続関係がしっかりと存在し続けます。
家を継ぐ、家業を継ぐ、ということは、子どもが相続権を承認するかしないかの問題とも言えます。そしてそれは、子どもの意志ひとつである、ということが言えるのです。
※どうしても子供に家を継がせたいのなら、遺言書で不動産や財産を息子に相続させるとしておくことです。しかしそれも子どもが相続放棄する可能性は消せません。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
別居合意書のかしこい使い方
離婚話がもちあがり、いったん冷静になるために、夫婦のどちらかが家を出るような場合(つまり別居する場合)、別居合意書を夫婦お互いで交わすことをおすすめします。
勝手に家を飛び出してしまうようなことはいないことが得策です。なぜなら夫婦には同居義務があり、勝手に家を飛び出した一方配偶者は同居義務違反を問われ、婚姻関係の破綻原因を作り出したとして、有責配偶者とされる恐れがあるからです。
だから、「お互い冷静になって今後の夫婦生活のことを考える時間を、一度離れて暮らしましょう」という内容の合意文書を作成しておくことが重要なのです。
円満な夫婦関係を回復するための冷却期間、婚姻を続けていくか離婚するかの熟慮期間としての別居、離婚までの暫定的な状態としての別居合意書は有効です。
さらに、別居合意書には、様々な内容を盛り込んで、離れて暮らす一方配偶者が不利にならないようにすることも重要です。
別居していたとしても、夫婦間における扶養義務や子どもの養育費の支払い義務は残ります。
ですので、例えば、妻が家を出るような場合は、夫に対して婚姻費用の請求、子どもがいるなら養育費の請求を、別居合意書の中にきちんと記載しておくのです。
民法760条[婚姻費用の分担]
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
民法760条にかんがみた場合、別居の際に一方配偶者が他方配偶者名義名義となっている預貯金を持ち出す際、その額が実質的財産分与額1/2以下の持ち出しであれば違法性は問われません。最終的な清算は後の離婚協議の中や、もしくは調停、裁判で決定していくこととなります。もちろん、自分名義の預貯金を勝手に引き出されたことで怒った他方配偶者から不法だと追及される可能性も十分にあります。しかし、別居から離婚するまでの期間における生活費等のことを考えると、現金は先に押さえておくべきかもしれません。特に子どもを連れて家を出る場合、ある程度まとまったお金は必要なケースがほとんどです。
これはかなり強引なやり方なのであまりおすすめはしません。できれば別居合意書においてきちんと記載してから家を出る(別居する)ことをお薦めします。
※持ち出した財産が将来の財産分与として考えられる対象、範囲を著しく逸脱していたり、他方配偶者を困惑させる等不当な目的をもって持ち出した場合には、損害賠償の対象となります。
民法第755条(夫婦間における財産の帰属)
1項 | 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 |
2項 | 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 |
別居中でも、夫婦の一方配偶者が他方配偶者に対して、生活上必要な衣類や日用品などの引き渡しを求めることは可能です。他方(家に残った配偶者)は、自分の生活に必要でない限りこれに応じる義務があります。
ですので、例えば妻が家を出る際に、自分や子供の衣類等を一度に運びきれず、家に残しておくような場合、「○○については私の許可なく処分しないでください」等の文面を別居合意書に記載し、家に残る他方配偶者の勝手で処分されないようにしておくのです。
特有財産(婚姻前から有する財産や相続や親族からの贈与によって得た財産、一方配偶者から贈与された衣服等)については、他方配偶者は引き渡しに応じる義務があります。
別居をすることになった場合、子の親権を取りたいのであれば、子供を連れていく方がよい場合がおおいです。別居の後、あなたの生活が落ち着いてから子供を迎えに行っても、他方配偶者が子供の引き渡しにすんなりと応じてくれる保証はありません。
他方配偶者が子供の引き渡しを拒むのであれば、家庭裁判所に子の引き渡しを求める審判及び審判前の保全処分を申し立て、あわせて、子の監護者指定の申し立てをする必要があります。手続きは煩雑で時間もかかります。
ですので、子どもをどちらの親が引受け監護するのかも、別居合意書にきちんと記載しておくことが重要なのです。
そして親権争いでは、実際に子供と暮らしていた期間(監護実績)が長期間であることがとても重要です。家庭裁判所は子供の環境において現状維持を優先させ、子どものストレスを軽減させようとする傾向があります。また、子供自身も別居中に一緒に暮らしていた親と離婚後も暮らしたいと望むかもしれません(子供が10歳以上になると、裁判でも子供の意見が尊重されます)。
別居していると、遺族年金が受給できない場合がありますので注意が必要です。
遺族年金の受給でのポイントは、生計同一であるかどうかです。簡単に言えば、夫婦がひとつ屋根の下で暮らしているかどうかです。通常は住民票で確認されます。
しかし別居して住民票を別々にする場合もあります。熟年離婚の場合、遺族年金のゆくえも当職の相談ではとても多い事案です。生計同一でないという理由で、遺族年金が受け取れません(遺族年金の受給審査は完全なる書類審査です)。
ではどうすればよいのでしょうか?
正当な理由があって婚姻期間中に別居しているような場合で住民票が別々の場合における遺族年金の受給については、実態で証明していきます。
「生計同一関係に関する申立書」という書類に、住民票上の住所が別々な理由やその他必要事項を記載し、第三者(三親等までの親族以外の人)の証明(署名または記名押印)をもらい、遺族年金の支給申請書と一緒に提出します。
同居していたことの証明として、亡くなられた方と遺族年金を請求する方に宛てられた手紙や、年賀状などのコピー、夫婦の名前が連記してある年賀状などは、同居を証明するものとして効果があります。
また、夫から妻へ生活費が振り込まれたこと証明する通帳履歴や、扶養家族であったことの証明である健康保険証の写し等も効果があります。
(別居合意書における注意点)
じつは、婚姻期間中、夫婦間で取り交わした契約は、原則いつでもどちらか一方からこれを取り消すことが出来ると民法で定められています。
民法第754条
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消す事ができる。
ただし、第三者の権利を害する事ができない。
しかし、重要な二つの判例があります。
①夫婦関係が破綻した状態で締結した夫婦間合意契約は取り消せない(最判例S33.3.6)②夫婦関係が良好なときに締結した契約でも夫婦が破綻した後は取り消せない(最判例S42.2.2)
この二つの裁判例の存在により、婚姻した後にした夫婦間での合意契約書(別居合意契約書等)であっても、必ずしも取り消せるというわけではありません。
上記判例を鑑みれば、夫婦関係が円満な時になされた契約で円満な状態での取消しであれば認められますが、夫婦間が円満でない時に取り交わした契約または夫婦関係が破綻となった時の取消しはこれを認めない、という見解が成り立ちます。※もちろん、公序良俗違反であったり窮状に乗じて強迫して書かせた合意書等の場合には、合意書を取り消すことが出来ます。
つまり、離婚前(婚姻中)に取り交わす離婚協議書や離婚公正証書、及び夫婦関係が円満でなくなった場合に取り交わした契約書(今後浮気をしない誓約書・別居合意書等)は、一般的な範囲で特段の問題がなければ充分に有効であるのです。
※ちなみに、単身赴任による別居はあくまでも理由があって別居しているのであって、片方が相手と同居するのが嫌だと離婚前提ではじめたものではないので、裁判所は単身赴任による別居を婚姻生活破たんの兆候とは見てくれない可能性が大きいです。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
離婚後の児童扶養手当
離婚後、妻が子を引き取った場合であっても、実家で親と同居する場合、通常、児童扶養手当はもらえません。
また、養育費の額を決めるとき、児童扶養手当がもらえるかどうかは考慮しません。
逆に、国が児童扶養手当の額を決める際には、養育費の額が考慮されます。つまり、養育費をたくさんもらっている場合、児童扶養手当は減額されます。
もちろん、給料をたくさんもらっている場合も児童扶養手当は少なくなりますし、もらえない場合もあります。国の考え方は「一定の収入基準に足りない部分のみ手当を支払う」というものです。離婚協議書を作成する場合、養育費の額の決定においては注意が必要です。
母子だけで生活している実態がないと児童扶養手当がもらえないならば、実家の親と同居していても、住民票だけ別にすることを考える方もいると思います(世帯分離)。しかし、児童扶養手当の認定は必要書類の提出だけでなく、状況確認調査のあと、その報告書が作成された後に審査となります。不正受給だけは考えるべきでないと思います。
児童扶養手当は、子どもを連れて再婚することになった場合にも、当然もらえなくなります。子連れでの再婚の場合、再婚相手と子どもが養子縁組する場合としない場合がありますが、養子縁組するしないにかかわらず、児童扶養手当がもらえなくなることには変わりありません子も再婚相手と一緒に生活している以上、当然扶養されているものとみなされるのです。※親が婚姻届を出していなくても、相手と同居するようになった時点で児童扶養手当は支給停止となります。児童扶養手当をもらっている状態から子連れでの再婚されるという方は、注意が必要です。
児童扶養手当の額というのは収入によって変わります。収入の多い人は、もらえる額が少なくなります。児童扶養手当額を決める基準となる所得は、前年度または前々年度(1~6月に申請する場合)の所得が対象となります。離婚した時点であまり収入がない方でも、前年度の収入が多かった場合、児童扶養手当はあまりもらえないことになります。
児童扶養手当受給における所得制限での所得制限額は扶養親族等の数によって変わってきます。たとえば、扶養親族1人の場合には、全部支給の所得制限限度額が57万円、一部支給の所得制限限度額が230万円です。※所得というのは、前年度の年間収入額から必要経費等を控除した金額です。たとえば前年度の所得額が30万円で子どもが1人の人であれば、全部支給が受けられると思ってしまいがちなのですが、これも違います。なぜならば、扶養親族の数も前年度が対象となるからです。
離婚前、子どもが税法上夫の扶養親族になっていたという場合だと、離婚直後に妻が児童扶養手当を申請する場合、扶養親族は0人とされます。扶養親族0人の場合の所得制限限度額は全部支給の場合19万円、一部支給の場合192万円ですから、上記の例では全部支給が受けられないことになります。
児童扶養手当は年1回現況届を出して支給額が決定されますので、上記のような場合においては離婚後1年くらい経てば支給額が増えるのかと言うと、そうでもありません。離婚後、別れた夫から養育費を払ってもらった場合、養育費の額が所得に加算されるので、その分手当の金額は少なくなります。
結局、児童扶養手当があるから生活が楽になるということはあまりありません。養育費にしても、別れた夫がきちんと支払ってくれる保証はありません。生活設計は自分の収入で支えられるようにすることが重要なのです。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
養育費請求権の時効
○離婚時に、養育費についての取決めをしなかった場合
抽象的意味での養育費のように一定の親族関係に基づいて法律上当然に生じる債権(民法877条)は、その親族関係が存在する限り時効にはかかりません。したがって例えば離婚後10年経っていても、養育費を請求することは可能です。
また、養育費請求時点より前の養育費についても請求できる余地はあります。※未成熟子に対する生活保持の義務は、請求をまってはじめて発生するものではない(神戸家審S37.11.5)
しかし、一般的見解は「養育費を請求してはじめて要扶養者になる」であり、養育費請求以前の扶養料支払い義務を否定する判例も多々あります。養育費請求以前の養育費が請求できるかどうかは、具体的状況に即して判断されます。
○離婚時に、養育費についての取決めをしたが、養育費の支払いを拒否されていた場合
夫婦間の協議(離婚協議書や離婚公正証書を作成した場合等)で養育費について具体的な取決めをした場合、抽象的な意味での養育費請求権は債権(子が成人するまでの毎月末、養育費として7万円を支払うという債権)となり、最初の弁済期から20年間または最後の弁済期から10年間行使しないときは時効消滅してしまいます(民法168条)。
また、月々の養育費支払請求権も5年間行使しないと時効消滅してしまいます(民法169条)。一方、家庭裁判所により審判ないし調停において養育費が具体化した場合には、10年の消滅時効に服すことになります(同174条の2)。
離婚時に養育費を決めていた場合でそれが離婚協議書等である場合、養育費の不払いを10年間していた元夫が時効を援用すれば、過去5年以前の元妻の養育費支払請求権は時効消滅してしまいます。一方、家庭裁判所の調停ないし審判による養育費の決定であれば、過去10年間の養育費支払請求権は時効にかかっていないので、全額請求することが可能となります。
結論です
・養育費の取決めを具体的に書面に残さず、離婚後数10年過ぎたとしても、子供が自立するまでの間は、いつでも養育費を元旦那に請求することが出来ます。
・しかし、離婚協議書や調停調書などで養育費の取決めをした場合は、時効にかかる。
・養育費を具体的に書面で「毎月5万円の養育費を支払う」など、この様な形式の取り決めを“定期給付債権”という。
・この定期給付債権は離婚協議書(及び公正証書)で取り決めた場合、5年間で時効にかかる。
・裁判所で作成した調停調書や判決書の場合、確定判決によって確定した権利については、10年で時効にかかる。(注)確定の時に弁済期の到来していない債権についての消滅時効は5年です。
・しかし、元旦那が時効制度を知っていない場合(時効を援用しない場合)には請求可能。
(扶養義務者)
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
(定期金債権の消滅時効)
第168条 定期金の債権は、第一回の弁済期から20年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から10年間行使しないときも、同様とする。
2 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
(定期給付債権の短期消滅時効)
第169条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。
(判決で確定した権利の消滅時効)
第174の2 確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
養育費の強制執行
離婚公正証書を作成する際、夫が強制執行に服すると認めている記載があれば(強制執行認諾約款といいます)、養育費は裁判によらずに、裁判所への申立てだけで強制執行することが可能です。
夫がサラリーマンの場合、差押えの対象になるのは一般的にはまずは勤務先から支給される給料や預貯金などの債権です。
では、元夫が養育費の不払いを何度も繰り返すような場合、不払いのたびに強制執行の手続きを取る必要があるのでしょうか?
平成15年の民事執行法の改正で、養育費のほか
・夫婦協力扶助義務に基づく債権
・婚姻費用分担義務に基づく債権
・扶養義務に基づく債権(扶養料)
などの債権(「定期金債権」といいます)に関しては、支払期限の過ぎたものだけでなく、これから支払期限の来るものについても強制執行を開始することができ、将来の給与などを差し押さえることができるようになりました。
つまり、一度強制執行を行えば、将来にわたって義務者の給料から天引きで養育費を受け取れるようになったのです。
では、元夫が養育費の支払いを何度も滞っていた場合、元夫の給料を全額差し押さえることは可能なのでしょうか?
債務者の生活維持という観点から、債務者が勤務先に対して有する給料などの一定の範囲については差押えが禁止されています。例えば、金銭消費貸借などで生じた一般の債権の場合、給料は原則としてその4分の1までしか差し押さえることができません。しかし、養育費などの定期金債権に関しては、原則として御主人受け取る給料の2分の1まで差し押えることができるようになりました。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
婚姻中のセックスレスに関する法律解釈
婚姻期間におけるセックスレスは、裁判離婚における離婚原因となりますが、ではどのような状態がセックスレスなのかを、下記判例から読み解いてみたいと思います。
元妻から元夫に対して、婚姻中に性生活がなかったことを理由として、慰謝料の損害賠償を請求したというケース(東京地裁平成23年 3月15日判決 ウエストロー・ジャパン)
東京地裁の裁判官は、元妻の請求を棄却しました。
<判旨>
「婚姻中の夫婦にとって、性生活は互いの愛情を確かめ子を持つことにもつながる極めて重要な要素であり、夫婦の一方はそれぞれ他方に対し性交渉を行うことに協力すべき一般的義務を負うということができる。したがって、夫婦の一方が性交渉を開始したにもかかわらず、他方が合理的な理由もなくこれに応じないことは上記協力義務への違反であり、不法行為を構成する。」
「しかし夫婦の双方がともに性交渉を開始しない場合においては、原則としていずれか一方にのみ性交渉を開始すべき義務が生じると解することはできず、例外的に夫婦の一方に自ら性交渉を開始することができない客観的事情があり、他方に対して性交渉の開始を求めたにもかかわらず、他方が合理的な理由もなく性交渉を開始しないといった特段の事情が認められる場合に限り、他方が性交渉を開始しないことが上記協力義務に違反するものとして不法行為を構成すると解するのが相当である。」
「この点、原告は妻である原告から性交渉を求めたことがなかったとしても、自ら性交渉を求めなかった被告の責任は肯定されるべきであると主張するが、夫婦間の性生活における役割分担を性別により固定化する見解であり、価値観が多様化し性別にかかわりなくその個性と能力を発揮することが期待される今日社会において到底採用することができないものである。単に女性であることは上記の自ら性交渉を開始することができない客観的事情にも当たらないというべきである。」
要約すると、セックスを開始した後、これを拒否したら慰謝料を認めるが、セックスを開始していない場合(開始を求めただけでは足りません)は、原則として慰謝料を請求できないと読み解くことが出来ます。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
不貞行為の立証はどこまですればいいのか?
不貞行為を理由に裁判離婚の請求する場合、請求する側は配偶者と愛人との「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」を立証する必要があります。裁判所では詐欺や詐称行為を防ぐため、不貞行為の証拠を厳しく制限しています。
不貞行為の証拠が不十分な場合、憶測や推測ととらえられ、離婚請求を棄却され、離婚が認められない場合もあります。協議離婚の場においても、不貞行為の証拠を持たないで配偶者を追及しても、嘘をつき通されてしまいます。
また、配偶者の不貞行為を原因として離婚請求する場合、この不貞行為が婚姻関係の破綻の原因であるという因果関係を立証する必要があります。
※夫婦関係が既に破綻している状態で、その後に配偶者が異性と性的関係を持った場合、この性的関係と、夫婦関係の破綻には因果関係は認められないので、「不貞行為」を理由に離婚請求はできません。
不貞行為の証拠を完全に立証できなくても、離婚請求はすることはできますが、この場合「婚姻を継続し難い重大な事由」を適用して争っていくことになります。
しかし、婚姻を継続し難い重大な事由の場合では、慰謝料請求の行方に大きく影響してしまい、慰謝料が取れなかったり、金額が大幅に少なくなり、愛人にも慰謝料の請求はできません。慰謝料や財産分与、養育費や親権などを有利にするためには、不貞行為の証拠はとても重要なのです。
●裁判の為の「不貞行為」の証拠
裁判の為と書きましたが、協議離婚においても、慰謝料、財産分与等を有利に決定していくには、不貞行為の証拠は必要なものとなります。
写真・ビデオが有効です。
不貞行為の証拠として一番優れているのはやはり写真やビデオ等の映像です。
ここで注意があります。
配偶者が愛人と一緒に何度もラブホテルに出入りしている場面は、「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」となりますが、愛人と2人で旅行している情報や、愛人の部屋へ出入りしているだけといった情報だけでは、肉体関係があることを立証するには不十分と判断されます。
デジタルカメラでの写真は、画像の編集修整が簡単に出来るゆえに証拠能力は弱くなります。ゆえに状況証拠とされてしまう場合がほとんどといえます。アナログ写真が実は有効なのです。しかしデジタルカメラの写真でも、写真に年月日時分が入っていたり、写真に連続性があれば不貞の証拠として認められる場合もあります。
録音テープも有効です。
自宅室内の夫婦の会話の中で、配偶者が不貞の事実を認めるような言葉を述べた場合、それをアナログ方式のテープに録音することで証拠となります。こちらもデジタルカメラと同様にICレコーダー等デジタル関係は編集・ねつ造が簡単に出来てしまうので、証拠能力としては弱いと判断されることが多いです。
電子メール等の場合。
携帯電話・PCメールのやり取りで、配偶者の浮気が発覚することが多いのですが、携帯電話やメールの履歴を見た、またはメールの内容を写真に撮ったというだけでは、配偶者と愛人がメールのやり取りをして交際していたという事実は証明されても、不貞行為の証拠までにはなりません。
不貞の証拠として認められるのは「性交の確認ないし推認」証拠である必要があります。具体的に性行為(肉体関係)を確認できる内容が求められます。ただの履歴だけでは状況証拠とされてしまいます。しかし、状況証拠であるメールのやり取り等を用いて、配偶者が不貞の事実を認めた場合はメールでも証拠となります。調停・裁判では、電子メールはプリントアウトして提出します。
その他の証拠
・友人、関係者、探偵社等の第三者による証言
・不貞行為が認められる手紙やメモ、日記等
・愛人からの手紙や贈り物
・愛人と宿泊した時のホテルの領収書
・不貞行為の裏づけとなるクレジットカードの明細、等々
つまり、一般常識で判断した場合に不貞の事実が客観的に証明できるものです。不貞の証拠になるような物を見つけたらコピーしておくことが重要です。
※証拠は合法的に確保しなければ無効です。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
婚姻関係の破綻の定義
法律論的に「婚姻関係が破たんしている」ことの定義は、
婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがないといえる場合です(不治的破綻)。夫婦としての実体的な協力が見込めない場合が該当します。裁判例では「婚姻関係が修復することが不可能な状態」と表現されることが多いです。単に夫婦関係が冷えているだけでは破綻したとまではいえません。冷えているだけではなく、およそ回復の見込みがなかった、という状況が必要となります。
そもそも民法では、夫婦相互の義務として同居・協力・扶助の義務を定めており、夫婦相互に貞操を守る義務があると考えられています。つまり、夫婦の間には性的な関係が存在することを前提にしてその操を守る義務があると考えられているのです。民法では、夫婦間では、同居・協力・扶助・性的関係があることを前提としているのです。それらの義務の遂行が認められないような状態であれば、実質的に夫婦とはいえないと考え、婚姻関係が破綻していると定義するのです。
この理論を利用するのが、不貞行為をはたらいた一方配偶者です。
婚姻関係が破たんしていたと主張し、婚姻関係が破たんしていた間の不貞行為は不貞行為に該当しないとの理論を展開し、慰謝料請求を避けようとします。
しかし、不貞行為の相手方が不貞行為開始時には婚姻関係が破綻していると主張してきても、その立証はかなり困難であると言えます。
なぜなら、婚姻関係の破綻を立証する物的証拠や目撃証言は、いわば夫婦二人だけが知っている(持っている)ことがほとんどであるからです。
また実際の事例では、その不貞行為が離婚原因となっていることが明らかなケースが多く、不貞行為の前に婚姻関係が既に破綻していた、という弁解はほとんど認められないのが実情です。
では婚姻関係破綻を否定する要素とはどのような事実なのでしょうか?
つまり、どのような事実があると婚姻関係が破綻していないと判断されるのか、ということです。これは過去の裁判例から判断できます。
同居している場合
・妻が家族の食事を用意し、夫もそれを食べている(家事の協力があるという事実)
・一緒に食事をしている
・破綻したと言いながら、離婚に関する具体的な協議をした形跡がない
・性交渉がある
・家族で食事をともにしたり、家族旅行等をしている事実がある。またはそれらの計画を立てていた事実がある
・冠婚葬祭等へ夫婦そろって出席していた事実がある
・夫婦生活のやり直しについて話し合ったり、一方配偶者が謝罪したような事実がある
・一方配偶者が他方配偶者を看病している
・一方配偶者が他方配偶者へ誕生日プレゼントを贈っている
・一方配偶者の親に別居を謝罪したり、夫婦生活をやり直すと発言している
・夫婦間において、まだ親密な関係をうかがわせる電子メール等の履歴がある 、等々
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
面会交流を妨害されたときの間接強制や損害賠償
面会交流を妨害された場合、妨害されたことを理由に、別れた相手方(子どもを監護している元配偶者)へ慰謝料を請求することは可能です。もっとも、妨害されたということだけで請求が認められるわけではありません。子の福祉を第一に考えて、父母双方の事情を総合考慮するという手法を裁判所は採用します。
協議離婚の際、父母間で合意した父と未成熟子との面接交渉権が、母によって妨害されたとして、父子の母に対する慰謝料請求を認めた事例があります(東京地裁昭和63年10月21日)。
1か月に1回(全日)、子どもと面会させるという約束をしていたにもかかわらず、面会させなかったり、面会させても全日という原則を守らなかったりしたという事実により慰謝料が認められました。
ここで注目していただきたいのは、裁判所の慰謝料認定における基準です。
・一部面会ができた場合
午後2時ころから面会がされた場合について 1回あたり金5000円
午後7時から面会がなされた場合について 1回あたり金1万円
・面会の約束がされなかつた場合については、1回あたり金2万円
・面会の約束がされたにもかかわらず、破棄された場合については1回あたり金3万円
という基準が設定されたのです。
これはひとつの裁判例であり、この基準がほかの裁判例で踏襲されてもいませんが、ひとつの考え方として参考にしていただきたいと思います。
また、面会交流権が妨害された場合、面会交流の間接強制はいままで認められることはなかったのですが、平成25年3月28日の最高裁において、面会交流の間接強制についての判断基準を下記のように示しました。
1 面会交流の日時又は頻度
2 各回の面会交流時間の長さ
3 子の引渡しの方法等
が具体的に定められているなど、監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合。
これは札幌家裁の審判で、最高裁が間接強制を認めたケースであり、札幌家裁の審判が認めた面会交流要領は下記のようになっています。
1.面会交流の日程等について、月1回、毎月第2土曜日の午前10時から午後4時までとし、場所は、長女の福祉を考慮して相手方自宅以外の相手方が定めた場所とすること。
2.面会交流の方法として、長女の受渡場所は、抗告人自宅以外の場所とし、当事者間で協議して定めるが、協議が調わないときは、JR甲駅東口改札付近とすること。抗告人は、面会交流開始時に、受渡場所において長女を相手方に引き渡し、相手方は、面会交流終了時に、受渡場所において長女を抗告人に引き渡すこと。抗告人は、長女を引き渡す場面のほかは、相手方と長女の面会交流には立ち会わないこと。
3. 長女の病気などやむを得ない事情により上記1の日程で面会交流を実施できない場合は、相手方と抗告人は、長女の福祉を考慮して代替日を決めること。
4. 抗告人は、相手方が長女の入学式、卒業式、運動会等の学校行事(父兄参観日を除く。)に参列することを妨げてはならないこと
等が定められていました。つまり、これだけ具体的に特定する必要があるということです。これを今後は参考にすべきでしょう。
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
死後離婚(姻族関係終了届)
・配偶者の死後、姻族との付き合いを絶ちたい方
・配偶者の死後、姻族に対する扶養義務を無くしたい方
・亡くなった夫や妻の墓に入りたくない方
・亡くなった夫や妻の実家の墓に入りたくない方
姻族関係終了届の制度を知っていますか?
当事務所では姻族関係終了届のサポートをしております
お気軽にお問い合わせください
TEL:059-389-5110
(電話対応:年中無休 9時~20時)
※姻族の例(義理の両親、義理の曾祖父母、義理の叔父・叔母、義理の兄弟姉妹、義理の甥姪、連れ子、連れ子の子、連れ子の孫)
配偶者が亡くなった後の生活については、様々な事情が生じます。
自分らしく生きるために、熟慮を重ね、姻族関係終了届を決心される方を、
当事務所はサポートさせていただいております。
夫または妻(配偶者)が亡くなった場合、婚姻関係は自動的に解消されるわけではありません。手続きをしない限り、義理の両親、義理の兄弟姉妹等との関係(姻族関係)は継続します。民法では、家庭裁判所は特別の事情があるときは三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができるとされていますので、姻族関係を終了させていなければ、死亡した夫または妻の父母や兄弟姉妹などに対する扶養義務が発生する場合があります。
配偶者が死亡した場合、姻族関係終了届を行うことにより、残った配偶者と死亡した配偶者との姻族関係を終了させることが出来ます。つまり姻族関係終了届により、死亡した夫や妻の親族に対する扶養義務がなくなるのです。
離婚をすれば姻族関係は終了しますが、夫婦の一方の死別の場合には姻族関係終了届手続きをしなければ姻族関係は終了しません。例えば、夫と死別した後再婚した妻は、亡くなった夫の親族との姻族関係を終了させるには、やはり姻族関係終了届手続きをしておく必要があります。
※姻族関係終了届後でも、亡くなった配偶者に対する相続権は残ります。夫と死別した後に妻が婚姻前の氏に戻ろうと、妻が姻族関係終了届を出して前の夫の親族との関係が無くなろうと、また、その妻が再婚しようと、そのようなことは配偶者の相続権には何の影響もありません。
ちなみに姻族関係終了届により姻族関係を終了させても、戸籍が変わることはありません。ですので死亡した配偶者の戸籍と自分の戸籍を分けたい場合は、「復氏届」を提出し婚姻前の戸籍に戻り旧姓を名乗るか、婚姻前の戸籍に戻りたくない場合や旧姓を名乗りたくない場合は、分籍届により自分一人の新しい戸籍に入ることとなります。
姻族関係終了届に必要な書類
・姻族関係終了届出書
※死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載する必要があります
・配偶者の死亡の事実を疎明する戸籍謄本または除籍謄本
・その他自治体が指定した書類
※届出人は原則「配偶者と死別した方」です。
※届出先は届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場となります。
※姻族関係終了届は、配偶者の死亡届の受理後、いつでも提出可能で、期限はありません。
※姻族関係終了届は届出日から効力が生じます。
当事務所では姻族関係終了届のサポートをしております
お気軽にお問い合わせください
TEL:059-389-5110
(電話対応:年中無休 9時~20時)
離婚協議書は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください
059-389-5110
(電話受付時間 9:00~20:00)
離婚協議書の作成・業務一覧
離婚協議書の作成における法務相談フルパック
離婚協議書の作成における法知識についての相談を承ります。
本サービス契約後、一か月間は面談を何度行なっても無料です。
※契約後、離婚協議書の作成等を申し込まれた場合、割引サービスを利用できます。
離婚協議書の作成
親権、養育費、子どもとの面会、財産分与等を法的観点から精査し、離婚協議書の作成をサポートいたします。
離婚公正証書の作成サポート
私的契約書である離婚協議書を公正証書化し公文書化します。
公正証書手続きに必要な戸籍謄本、不動産登記簿等の収集、そして公証人との打合せ等も行います。
別居合意書の作成
夫婦には同居義務がありますので、相手の意思を無視した強引な家出や、相手からの同居要求を拒否し続けると離婚原因「悪意の遺棄」に該当する場合もあり(民法770条)、離婚の際不利な立場に立たされることもあります。慰謝料を請求される可能性すら存在します。
しかし互いに同意した別居の場合は法律違反にはなりません。別居合意書は「互いに同意した別居である」ことを立証する書類であり、弊所はその作成サポートを行っております。
※別居合意書を公正証書化することも出来ます。
年金分割合意書の作成
年金分割制度とは、2007年4月以降に離婚した夫婦の間で、離婚後老齢厚生年金を分割してそれぞれ別個に受け取れるものです。つまり「厚生年金保険料納付記録を夫婦間で分割する」制度です。
年金分割の割合は最大で半分ですが、この割合は夫婦の合意が必要です。
また年金分割の手続きは原則年金事務所へ夫婦そろって出向くことが必要ですが様々な事情がありそれが出来ない場合、その手続きには「年金分割についての記載がある離婚公正証書」又は「年金分割合意書に公証人の認証を受けたもの(私署証書認証)」が必要となります。
弊所では上記のような場合に必要な「年金分割合意書」の作成サポート及び「年金分割合意書の私署証書認証化」サポートを行っています。
協議離婚申し入れ書の作成・養育費請求書の作成 等(内容証明郵便による)
内容証明郵便により協議離婚申し入れ書や養育費請求書を作成し、相手方への意思表示を明確なものにします。
離婚協議書のチェック
相手方から提示された離婚協議書や、ご自身で作成した離婚協議書を法的観点からチェックします。
当事者による離婚協議への立ち合いサービス
※相手方の承諾があり、当事者間で争訟性がない場合に限ります。
※行政書士は交渉代理人となることは出来ません。
公正証書代理人引受サービス
離婚公正証書作成当日は原則としてご夫婦揃って公証役場に出頭する必要がありますが、やむを得ない事情で出頭できない場合に、弊所が代理人をお引き受けするサービスです。
※全ての公証役場で代理人が出頭可能なわけではありません。
示談書の作成
配偶者の浮気相手との示談書等を作成いたします。
死後離婚手続き(姻族関係終了届代行)
姻族関係終了届(通称・死後離婚)とは、夫婦の一方配偶者が死亡した際に、残った配偶者が死亡した配偶者の親族との姻族関係を終了させる届出のことをいいます。
姻族関係終了届を行うと、配偶者の死後、死亡した配偶者の親族の扶養義務がなくなります。
配偶者の死後、配偶者の親族とのお付き合いを絶ちたい場合等に行う手続きです。
↓電話やメールのお問い合わせはこちらをクリックしてください。
お問合せはこちら
↓離婚で注意すべきことの情報はこちらをクリックしてください。
詳細はこちら
手続きの流れ(離婚協議書)
お電話やメールでのお問い合わせ(無料)

皆様から問題の概要をお聞かせいただき、アドバイスをさせていただきます。
※電話やメールですとどうしても実情が把握しずらく、どうしても一般的な解答になってしまうことをご了承ください。
面談(出張面談、OKです)

電話やメールでお問い合わせいただいた後、皆様がお望みならば実際にお会いして相談させていただきます。面談場所は問いません。
弊所でも構いませんし、皆様のご自宅でも構いませんし、皆様のご自宅近くの喫茶店でも構いません。
ただ皆様が保存しておられる資料等を参照したほうがより正確な判断ができますので、皆様の利益のためにも出張面談を弊所ではお薦めしております。
※出張代は原則いただきません。車や電車で片道3時間以上かかるような場合に、高速料金や電車代をご請求させていただくことがあります。柔軟に対応させていただきます。
お見積書の提出

弊所が行う業務を羅列し、費用のお見積書を作成・提出させていただきます。
見積書の内容などにご納得がいかない場合は何度でもお問い合わせください。
お見積書を再提出させていただきます。
業務委任契約書の締結

提案させていただいたお見積書内容にご納得いただいたら、業務委任契約を結ばせていただきます。
業務着手(書類作成)
終業完了
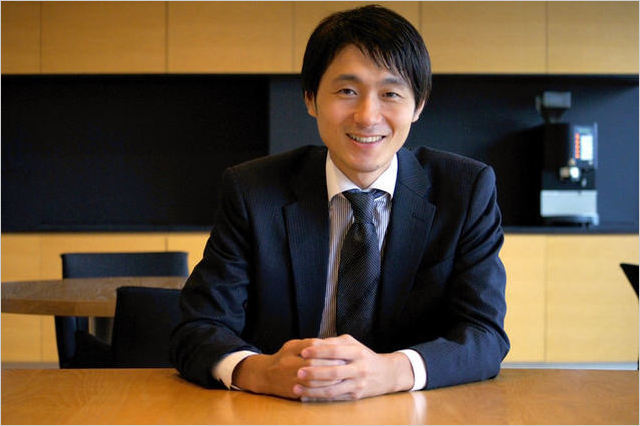
業務完了後に税理士・司法書士・弁護士・社会保険労務士などが必要となった場合にはご相談ください。信頼できる専門家をご紹介いたします。
↓電話やメールのお問い合わせはこちらをクリックしてください。
お問合せはこちら
料金(離婚協議書の作成)
サービス内容 | 基本料金(税抜表記) | 備考 |
|---|---|---|
電話・メールでの お問い合わせ | 無料 | 一般的な解答になってしまいます。 誤解が生じないように、詳細な相談は面談で行わせていただきます。 相談は面談で行わせていただきます。 |
面談 お気軽にご相談下さい! | 1回5,000円 | 時間制限はありません。 出張面談は片道1時間以上の場合に高速代や電車賃等の実費をご請求させていただきます。 |
離婚協議書の 作成サポート | 50,000円~ | 公正証書化はしないサービスです。 |
離婚公正証書の 作成サポート | 100,000円~ | ※6 ※7 ※8 ※1 ※9 ※5 ※2 ※3 |
離婚協議書のチェック | 30,000円 | - |
別居合意書の作成 | 50,000円~ | ※5 |
年金分割合意書の作成 | 35,000円~ | ※6 ※7 ※1 ※9 |
協議離婚 養育費請求書の作成 等(内容証明郵便による) | 50,000円~ | ※5 ※2 |
公正証書代理人 引受サービス | 20,000円~ | 公証役場まで片道1時間以上の場合に高速代や電車賃等の実費をご請求させていただきます。 |
示談書の作成 | 50,000円~ | ※5 |
※1 公正証書の手数料
(目的財産の価額):(手数料の額)
- 100万円まで:5000円
- 200万円まで:7000円
- 500万円まで:11000円
- 1000万円まで:17000円
- 3000万円まで:23000円
- 5000万円まで:29000円
- 1億円まで:43000円
1億円を超える部分については
- 1億円を超え3億円まで:5000万円毎に1万3000円
- 3億円を超え10億円まで5000万円毎に1万1000円
- 10億円を超える部分:5000万円毎に8000円
※協議離婚の届出に際して約定した慰謝料・財産分与の取り決め又は未成年の子の養育料の支払を公正証書にする場合は、慰謝料・財産分与と養育料とを別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。ただし、養育料の支払は、賃料と同じく定期給付に当たるため、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的価額になります。
がそれぞれ加算されます。
注)上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。
- 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して当該遺言書全体の手数料を算出します。
- 遺言加算といって,全体の財産が1億円以下のときは、上記1によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。
- さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
- 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が病院・ご自宅・老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記1の手数料が50%加算されるほか,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。
- 具体的に手数料の算定をする際には、それぞれの公証役場で確認する。
※2 基本料金とは別に住民票や登記簿の交付代、郵便代等を実費としてご請求いたします。
※3 片道1時間以上の場所への出張には、日当(10,800円/日)と交通費をご請求いたします。
※4 表示価格には消費税がかかります。
※5 業務内容によって基本料金は増加することがあります。
※6 弊所による公証人との打合せ費用は含まれております。
※7 公正証書手続きに必要な戸籍謄本、不動産登記簿等の収集等にかかる実費は別途必要となります。
※8 公正証書費用は含まれておりません。別途ご請求申し上げます。※1
※9 証人を弊所が手配させていただく場合、証人一人につき12,000円(税抜表記)が加算されます。
※本料金表はR6.6.26より適用いたします。
ご相談・お問合せはこちら
当事務所について、ご不明点やご質問などございましたら、
お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください
- 離婚協議書の作成で悩んでいる
- 遺言や相続の相談にのってほしい
- 農地に太陽光を設置したい
- 風俗営業許可をとりたい
- 建設業許可をとりたい
どんなお悩みでも構いません。
誠心誠意をもって対応させていただきます。
皆さまからのお問合せをお待ちしております。
お電話でのお問合せはこちら
059-389-5110
営業時間:9:00~18:00(年中無休)
電話受付時間:9:00〜20:00 ※土日祝祭日の電話は15時~20時の間のみ受付
メール受付時間:24時間年中無休 (2〜5営業日以内にご回答)
行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。
三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
出張面談実施中!

当事務所は出張面談を積極的に実施しております。
ご自宅やその近辺に私どもが出向き、直接お会いしてお話をおうかがいいたします。
各種資料をお渡ししたり、具体的な解決策を提示させていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。
059-389-5110
※面談サービスは予約が必要となります。
事務所概要

行政書士
佐藤のりみつ法務事務所
代表者:行政書士 佐藤則充
〒513-0809 三重県鈴鹿市
西条六丁目3番地の1 ポレスター西条四季の道402号
アクセス (地図) はこちら
主な業務地域
三重県(鈴鹿市・津市・
四日市市・亀山市・その他)、愛知県、岐阜県など
ご連絡先はこちら
事務所概要はこちら
営業日・時間はこちら