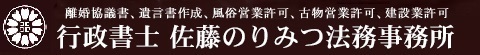内容証明書作成
三重県下で民事法務業務の相談件数トップクラス
内容証明書作成によるトラブル救済支援

クーリングオフ・契約解除・敷金返金等内容証明書送付によって解決の道を支援します!
内容証明を上手く書くには、あなたの請求内容が正しいことを法的根拠にそって主張することです。
事案を精査し、法的根拠に基づいて、有効な内容証明書を作成いたします。
あなたの問題を解決するため全力で支援いたします。
下記に内容証明について詳しい記事があります。どうぞご覧ください。
☎059-389-5110
(電話受付9:00~20:00 年中無休)
あなたの問題を解決するため全力でサポートします
行政書士・佐藤のりみつです
どうぞお気軽にご連絡ください
- 内容証明書の作成 25,000円~(税別表記)
※報酬はご依頼内容や難易度により増加いたします - 内容証明書作成における法務相談フルパック 20,000円/月(税別表記)
(電話、メール、面談が一か月間し放題のサービス)
➡内容証明書作成の料金一覧はこちら
- 貸したお金を返してもらいたいのに、返してもらえないて下さい。
- 悪徳業者に騙されて代金を支払ってしまったが、全く返してもらえない
- アパートを退去する際に、敷金をきちんと返還してもらえず困っている
- アパートの立て替え等の理由で、突然立ち退きを求められて困っている
- 職場でセクハラ、パワハラを受けて精神的にまいっている
- 会社から突然解雇されてしまい困っている
- 会社が給与をきちんと支払ってくれない
- 会社が残業代をきちんと払ってくれない
- 隣人の騒音やたばこの煙等の悪臭に困っている
- 敷地に違法駐車されて困っている
- ストーキング行為をされて恐怖を感じている
- 結婚の約束をしていたが相手に不実行為があり、婚約破棄したい
- 夫(もしくは妻)が不倫をしていた。慰謝料請求したい
- 離婚をしたいのに夫(妻)が全く応じてくれず困っている
- 離婚して養育費を支払ってもらう約束なのに、きちんと支払われず困っている
- 取引業者が未払金を支払ってくれずに困っている
- 子どもの大学進学に際して入学金や授業料を前納したが、入学辞退した。入学金や授業料を返してもらいたい
等々の問題を解決するためには、まず問題解決の意思表示を相手方にすることが必要です。
そこで有効なのが、内容証明郵便の上手な使用です。
内容証明郵便とは、差出人がどのような内容の手紙を誰にいつ発信して、かつ相手がいつ受け取ったのかを郵便局長が証明してくれるサービスです。
しかし、声高にただご自分の意思を主張しても、相手がすんなりと応じるはずもありません。
内容証明郵便の内容には、ご自分の主張(権利)の法的根拠や、相手側の行為が不法行為にあたる法的根拠等を、法条文で明示するなどして盛り込み、ご自分の主張を記載することが大切です
これが内容証明郵便の上手な使用なのです。
内容証明郵便を書くのは簡単ですが、効果を得ることのできる内容を起案するには、各種法令知識が必要となり、簡単ではありません。
- 弊所は、日々法令知識の蓄積と研究をし、人が生きる上でどうしてもぶつかってしまう様々なトラブルを法解釈でもって解きほぐす道を探求しております。
- 民法、消費者契約法、特定商取引法、借地借家法、労働基準法、労働契約法、ストーカー規制法、DV防止法、はたまた国土交通省などの通達やガイドライン、そして重要判例に至るまで、その探求の範囲は及んでいます。
- この獲得した法知識をもって皆様の利益に貢献できるよう、皆様の側に立ち真摯に内容証明郵便を作成させていただいております。
☎059-389-5110(電話受付9:00~20:00 年中無休)
人は生きていれば、様々なトラブルに遭遇してしまいます。
そんなとき、どうぞ一人で悩まないでください。苦しまないでください。
解決の道は必ずあります。
皆様の悩みを苦しみを、どうぞ弊所行政書士佐藤のりみつ法務事務所へご相談ください。
話すことで、心の負担が軽くなることもあります。
私と一緒に解決への道を切り開きましょう。そして笑顔を、幸せを取り戻しましょう。
当事務所は行政書士事務所であり弁護士事務所や公的機関等ではないため「法的紛争の発生がほぼ不可避である事案」については受任できません。裁判外での「常識的な法律知識に基づく整除的な事項」を記載する書面での和解を考えている事案につき受任します。
内容証明書によるトラブル救済業務一覧
内容証明書作成における法務相談フルパック
各種トラブルに対しての内容証明書作成における法知識についての相談を承ります。
本契約後、一か月間は、面談を何度行なっても無料です。
※本サービス契約後、内相証明書作成を申し込まれた場合、割引サービスを利用できます。
内容証明書作成業務
面談、もしくは電話やメールで相談者様の状況を真摯にお聞かせいただき、現状を把握させていただきます。
その上で内容証明書を出すべき事案であるかどうかを判断させていただきます。
※その後見積書を提出させていただき、相談者様の納得を得てご依頼を正式にいただき、業務受任となります。
作成した内容証明書は、内容を依頼者様へご確認させていただいた後、発送いたします。
依頼者様へは発送完了のご案内をさせていただきます。また内容証明の謄本と配達証明のはがきを依頼者様へ提出いたします。
内容証明書を発送した後も、ご相談に応じさせていただきます。
※内容証明書を出すべきでない、もしくは出すのに慎重さを要する場合の例
- 穏便に事案が解決できる可能性がある(相手側に誠意が認められる)場合
- 相手側と親しい間柄にある場合(感情を排し冷静に慎重に熟考しましょう)
※下記内容に該当する場合、ご相談・ご依頼をお受けできません。
- 業務が他の法律に行政書士業務として禁止されている場合
- 事案がすでに調停や訴訟などに発展している場合
- 事案に争訟性あるいは事件性のある場合
- 相談者様の主張が公序良俗に反する場合
- 依頼業務が行政書士業務以外である場合
- 業務が行政書士法に抵触する場合
- その他弊所にて不適切と判断する場合
※内容証明書作成のご依頼をいただいても、相手方と直接交渉(電話や面談)は行政書士法に抵触し行うことが出来ません。あらかじめご承知おきください。
内容証明で知っていてほしいこと
内容証明郵便によるトラブル解決で絶対に知ってほしいこと
文字の上でクリックしてください。題名の記事へリンクします。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
内容証明郵便って何?
内容証明郵便とは、手紙の一種です。
差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、日本郵便が証明してくれる一般書留郵便物のことをいいます。
紛争の事前防止や一定の法律効果の発生の為に利用されます。
配達された日(相手が受け取った日)が重要な意味を持つので、通常は「配達証明」を付けて利用されます。
内容証明に付加して利用出来るサービスは、速達郵便や本人限定郵便、配達日指定、配達証明、引受時刻証明等があります。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
内容証明郵便を出す目的って何?
内容証明郵便は、「いつ、誰が、誰に、何を伝えたのか」を証明してくれます。
これは裁判上の証拠にもなります。
つまり、普通郵便のように「そんな郵便は受け取っていない」とか「そんな内容は書いてなかった」等という言い逃れが、内容証明郵便の場合出来なくなります。
そこで送達された日付が重要な意味を持つクーリングオフや債権譲渡・時効中断などに内容証明郵便を利用し、確定日付のある内容証明として法的効力を持たせ、第三者への対抗力を持たせるのです。
さらに、内容証明郵便にはある種の威圧感があります。
内容証明郵便を受け取ると、受領の押印を求められます。これを拒否するには「受取拒否」と自署しなければならないほどの厳格さです。
中身である内容証明の文章には「平成○年○月○日、第△△△△号 書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。 郵便事業株式会社」 という認証が押印されていますので、さらに威圧感を醸し出します。
また、我々行政書士に内容証明書の作成すると、内容証明書には
「本書通知書作成代理人 行政書士 佐藤則充」と記載されます。
これにより受取人は法務家が介在している事実を知ることになるので、威圧感はさらに増します。
つまり内容証明郵便は、受け取る側にかなりの心理的圧力を与えると言えるのです。
内容証明郵便の証拠力と心理的圧力により、問題をスムーズに解決する、それが内容証明郵便を出す目的であると言えます。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
内容証明郵便を出したほうがいいケースってどんな場合?
・契約取消、契約解除→意思表示をしっかりと証明するため
・時効の援用、相殺の通知、契約の無効の通知→意思表示を相手側へ到達させ自己の権利を守るた
・クーリングオフ、賃貸借契約の更新拒絶→通知が期間内に到達することが法律要件となっているため
・債権譲渡→確定日付のある通知でないと法律上、債権者や第三者へ対抗できないため
・返済期限の定めのない債務の支払請求→支払期限を確定させるため
・DV接近禁止請求、ストーカー行為中止請求→刑事告訴や裁判上の手続きを執る際の要件のため
・遺留分減殺請求、未払賃金の請求、事故の損害賠償→短期消滅時効から自己の権利を守るため
この他にも内容証明郵便を出したほうが、問題解決の道を切り開くケースは多々あります。
ここで申し上げたいのは、内容証明郵便を出すのは目的に対する効果が望めるからだということです。
世の中の問題全てが裁判で争って解決しているわけではありません。裁判外で解決しているケースのほうが、実は圧倒的に多いのが実情です。そこで活用されているのが内容証明郵便です。内容証明郵便を上手に使うことにより、問題解決の切り札とすることが出来るのです。
※内容証明書を出すべきでない、もしくは出すのに慎重さを要する場合もあります
・穏便に事案が解決できる可能性がある(相手側に誠意が認められる)場合
・相手側と親しい間柄にある場合(感情を排し冷静に慎重に熟考しましょう)
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
内容証明書ってどう書くの?
・用紙に制限はありません。紙質、サイズも原則自由です。ただし差出郵便局で5年間保存される為、保存に耐えないもの(感熱紙など)は使用出来ません。
・用紙の枚数にも制限はありません。ただし複数枚にわたる場合は全てホチキスで綴じ、ページの繋ぎ目すべてに割印(契印)を押さなくてはなりません。
・1行あたりの字数と1枚あたりの行数については制限があります。
縦書きの場合 1行に20字以内、1枚につき26行以内
横書きの場合 1行に26字以内、1枚につき20行以内
1行に13字以内、1枚につき40行以内
1行に20字以内、1枚につき26行以内
・使用できる文字に制限があります。
使用出来る文字はひらがな、カタカナ、漢字、句読点、数字、および一般的な記号です。
英字は固有名詞(人名・地名・会社名・商品名、など)でのみ使用が可能です。
記号や句読点も1字として数えます。
、 。 % + などは使用可能です。
kg、㎡なども使用可能です。(2文字として数えます)
ただし、「」(かっこ)のみ、合わせて1字として数えます。
※初めのかっこ「のみ1文字として数え、とじかっこ」は数えません。
①は○と1で2文字として数えます。
(1)や(2)、(一)や(二)は、2文字です。
ただし、これらが文中の序列を示す記号として取り扱われている場合は1文字として数えます。
・表題は自由でありつけてもつけなくても全く問題ありません。
・差出人と受取人の住所・氏名は必要事項ですので、必ず記載しなければなりません。
・相手方が個人である場合は自宅住所へ送付、相手方が法人である場合は本店所在地に送付するのが原則です。
・相手方の自宅住所で無い場所に送付する場合には、プライバシーの侵害や名誉毀損となる危険があるので注意が必要です。
・相手方の勤務先住所に送る場合であれば、最低でも、
「○○県○○市○○町○−○ ○○○○株式会社 気付 ○○○○殿」等とし、封筒に「親展」と記載するようにします。
・特に秘密にしたい事項であれば、「本人限定受取郵便」などを理由するのが確実です。または、「郵便局留」で発送し、相手に発送した旨を伝えて、窓口に受け取りに行ってもらう方法もあります。
・文面中、差出人の氏名の横(または下)に押印すること一般的ですが、これは決まりではありません。押印するもしないも任意です。
・時候のあいさつ文なども不要であり、要件のみを書くことが一般的です。ただし離婚や内縁関係解消等特別な場合には、内容証明のもつ威圧感を緩和させるために、あえて時候のあいさつ文をつける場合もあります
・内容証明郵便の場合、手紙以外のもの(資料やコピー等)は同封することが出来ません。「別郵便で○○書を送付しましたのでご確認下さい」等と記載しておくのが一般的です。
・文面や内容に「○日以内に支払がない場合刑事告訴します」や「要求に応じなければ貴殿の勤務先や家族に通報する」等の表現をすることは脅迫になりかねません。文面や内容は冷静になって決める必要があります。
・差出人が複数いる場合は連盟で送付できます。この場合、差出人(通知人)の欄に住所・氏名を各人が記載します。ページの繋ぎ目の契印や訂正印は差出人全員が押すことになります。配達証明のハガキを受け取る差出人の住所・氏名の前に”(送達先)”と書き加えます。
・受け取り人が複数いる場合
受取人が違うだけで差し出す内容が同じであれば、1回の内容証明郵便で差し出すことが出来ます。
これを、「同文内容証明郵便」といいます。「同文内容証明」は二種類あります。
①完全同文内容証明郵便
2名以上の相手に差し出す内容証明郵便で、その文面の内容のみならず、日付や差出人・受取人の記載がすべて同一のものを「完全 同文内容証明郵便」といいます。受取人の住所・氏名を連記します。この場合、通常の内容証明の通数(1人だと3通)に、受取人の数が増えた分だけ通数を増やして作成します。
例)2名に差し出す場合→4通。3名に差し出す場合→5通。
②不完全同文内容証明郵便
完全同文内容証明とは異なり受取人を連記しません。受取人の住所・氏名のみ個別に書いて作成します。日付や文面の内容は同一でなければなりません。この場合、作成する内容証明の通数は通常の通数(1人だと3通)に受取人の数が増えた分だけ足した通数を作成します。しかしここで注意点があります。郵便局が保管する分と、差出人が保管する分の計2部だけは、受取人全員が連記してなければなりません。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
内容証明書を書く際のポイントって何?
・内容証明書内で記載されている内容が読み取れるよう、つまり表題と内容が一致していてかつ出来る限り簡潔なタイトル(標題)を付けましょう。
・差出人と受取人の記載内容に間違いがあると送信不能となり再度送付する必要が出て無駄な費用がかかります。また回答を求めていた場合などは回答を受け取ることも出来なくなります。間違いのないようにしましょう。
・事実や経緯の記載内容に間違いがあると後々争いの元となります。正確な内容のみを記載するようにしましょう。
・主張や請求を明確に記載しましょう。
・その主張や請求に法的根拠を求めましょう。また主張や請求に違法性がないかも確かめましょう。その際「○○法第○○条に基づき~」等の表記をして、出来る限り法令を特定して記載しましょう。
・相手に回答を求める場合や金銭の支払いを請求する場合等は、その期限を明確に記載しましょう。
・その期限が経過した場合にどのような手段をとるのかを出来る限り明確に記載しましょう。
・法令上の罰則や類似事案での判例等も記載しましょう。余計な紛争を事前に防ぐ可能性が高まります。
・民事上の請求だけでなく、刑事事件に該当するならば被害届や刑事告訴・告発、行政処分の可能性があるならばその監督官庁への申立等の準備があることも記載しましょう。
・適正な差出日かどうかを確認しましょう。差出日がすでに消滅時効にかかっていたらせっかくの内容証明書の内容も無効となってしまいます。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
内容証明の封筒って?
封筒の種類やサイズに制限はなく、普通の郵便で利用出来る封筒であればなんでも構いません。
封筒の表に受取人の住所・氏名を記載し、封筒の裏、または下に差出人の住所・氏名を記載します。
住所と氏名の記載は、内容証明書文中の「通知人」欄と「被通知人」欄の記載と同じように記載します。
複数の相手に差し出す場合には、封筒は受取人1人1人それぞれの住所・氏名を書いた 封筒を各々つくります。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
内容証明差出郵便局
差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局及び支社が指定した郵便局です。
すべての郵便局において差し出すことができるものではありませんの確認が必要です。
内容証明郵便の差出方法
郵便窓口に次のものを提出します。
(1)内容証明3通(差出人・受取人ともに1名の場合)
1通は相手への送達用。
1通は郵便局保管用。
1通は差出人保管用。
(2)封筒1枚(差出人・受取人の住所氏名を明記したもの)
送達する相手方の住所・氏名を記入してあるもの
封筒は、封をしない状態で持っていくこと
(3)印鑑
訂正がある場合、必要となります。
(4)内容証明の加算料金を含む郵便料金
※念のため、差出人の印鑑をお持ちいただくことをお勧めいたします。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
内容証明の本人控えをなくしてしまった!
内容証明の本人控え(謄本)をなくしてしまったら?
差し出した郵便局において、保管されている内容証明の正本の閲覧または謄本の再交付を受けること(謄本の再度証明)が可能です。
※内容証明の謄本の閲覧または再度証明を受けられる期間は、謄本の保存期間「差し出してから5年間」です。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
内容証明郵便が差出人のもとへ戻ってきてしまった!?
受領拒否で戻ってきた場合、判例は、意思表示は到達したと認定しています。
「その気になれば受け取ることはできたはず」「中身がわかっているからこそ受け取りを拒絶したんでしょ」という理屈です。
では、相手方が不在のために戻ってきた場合はどうなるか?
このような事態を解決するため、内容証明郵便とは別に特定記録郵便を利用します。
特定郵便は普通郵便と同じようにポストに投函されますので、相手方に必ず配達されます。
そして、ネットで配達状況を確認できますので、相手方に配達されたことを確認することができます。
「そんな郵便物は届いていない」と抗弁されたときは、配達状況書類を見せて、「いや、届いているはずだ」と対抗するのです。
もっとも、送るのは内容証明の“写し”ですから、内容証明と同等の効果を期待することはできません。
あくまでも、内容証明を補強する存在です。
慎重を期して、内容証明を送るときには、あわせてその写しを特定記録郵便で相手方に送付しておき、内容証明には「同じ内容のものを同時に特定記録郵便で送っている」旨を記載しておくという方法を用いるのです。
ちなみに内容証明の留置期間は7日です。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
クレジット契約における支払い停止の抗弁
クレジット契約での割賦購入あっせん(消費者と販売店と信販会社の三者間契約で、消費者が、販売店で商品等を購入する際、信販会社が消費者に代わって販売店に代金を支払い、その信販会社が立て替えてくれたお金を、消費者が後日分割で信販会社に支払う仕組みのもの)には、いくつか種類があります。
・包括クレジット(包括信用購入あっせん)
あらかじめ信販会社の審査を受けて会員になることにより、販売店(加盟店)でカードを提示するだけで、利用限度額の範囲内で何度でも、商品等を購入することができるタイプ。いわゆる普通にクレジットカードを使うタイプです。クレジット会社発行のカードを使用した場合は、この包括クレジット(包括信用購入あっせん)です。
・個別クレジット(個別信用購入あっせん)
販売店(加盟店)で商品等を購入するたびに審査を受けて契約するもの。浄水器の販売などで、クレジットローンを組んで購入する場合などに用いられるタイプです。当該商品に限りクレジット契約を締結する場合は、この個別クレジット(個別信用購入あっせん)です。
割賦販売法においては、
・虚偽説明で勧誘したり、過量販売などで結ばれたクレジット契約が解約されると、信販会社は既払い金を消費者に返し、販売業者は立替金を信販会社に返済しなければなりません。
・消費者の支払い能力を信販会社が調査することが法律で義務づけられ、もし支払い能力を超えていれば、与信契約は禁止されます。
・販売業者の勧誘行為を信販会社が調査することが法律で義務づけられ、もし不適正な勧誘があった場合、与信契約は禁止されます。
また、クレジット契約で商品等を購入したが、商品が約束どおりに引き渡されないなど、消費者と販売店との間で下記のような問題が生じたときは、これを理由として、信販会社に対する支払いを停止することができます。
・販売業者に債務不履行等があったとき
商品の引渡がない
商品が見本・カタログと違う
商品が不良・欠陥品
商品の引渡しが遅れて、目的が達成されなかった。
その他販売業者に債務不履行がある。
・契約が成立していない場合
・契約が無効の場合
・契約が取り消された場合
・契約が中途解約された場合
・販売業者が倒産したとき 等
上記のように、販売店に商品欠陥の給付その他債務不履行があれば、消費者は代金の支払を拒むことが出来ます。そして消費者が販売店に対して支払を拒める事由を抗弁事由といいます。
割賦販売法において、販売業者に対して抗弁事由があれば、クレジット会社の請求に対してもこの抗弁事由により支払を拒み得るとしています。この消費者の権利を支払停止の抗弁権(抗弁の接続)といいます。
割賦販売法では支払停止の抗弁を行使する為の要件を、以下の通り定めています。
・割賦購入あっせん契約(クレジット契約)であること
・指定商品・指定権利・指定役務であること
・2カ月以上の期間にわたる3回以上の分割払いであること
・原則、全ての商品に適用されますが、クーリングオフなどに馴染まない商品は政令で適用除外とされます。
※適用除外商品の例
・書面の交付及びクーリング・オフが適用除外となる役務(キャッチセールスによる飲食店・マッサージ・カラオケボックス・海上タクシーの契約等)
・クーリング・オフが適用除外となる商品(自動車販売、自動車リース、電気・ガス・熱の供給契約、葬儀の契約、化粧品、配置薬、3000円未満の現金取引等)
・金融商品など取引ルールを定めた別の法律があるもの
・販売業者に対して抗弁事由があること。
・支払い総額が4万円以上であること(リボルビング方式なら3万8千円以上)が必要です。
・割賦販売法の適用除外でない取引であることが必要です。
※割賦販売法の適用除外取引
・営業のため若しくは営業として締結されたもの
・外国にある者に対して行うもの
・国又は地方公共団体が行うもの
・次の団体が構成員に対して行うもの (特別の法律に基づいて設立された組合、連合会、中央会、国家公務員法108条の2、地方公務員法52条の団体、労働組合)
・事業者がその従業員に対して行うもの
・不動産を販売する契約に係るもの
※法人契約、事業者の契約であれば直ちに商行為になるのではなく、「営業の為に若しくは営業として」締結した契約のみが商行為になります。
支払停止の抗弁権行使の方法ですが、まずは信販会社に支払停止の抗弁を主張する旨の通知を内容証明等で行ないます。
そして、販売業者に対しては、販売業者の債務不履行等の抗弁事由かつ契約解除などの意思表示を内容証明で通知します。
支払停止の抗弁は、信販会社に対し、販売会社に対して抗弁できる事由を信販会社へ行い、その支払を停止するだけのものです。売買契約が存続している以上、クレジット契約も存続しています。トラブルの源である販売会社とのトラブルを解決しなければ、つまり販売店との売買契約の解除等を行なわない限り、クレジット契約もなくならないのです。
ですので、浄水器等を個別信用クレジットで購入した等の場合、信販会社への支払停止の抗弁よりも、販売会社への内容証明によって、いかにして売買契約を打ち切るのかが、大きなポイントとなってくるのです。
※支払が自動引き落としの場合、信販会社がすぐに引き落としを停止してくれるとは限らないので、そのような場合は預金を引き出すか、口座を解約するか等の手段を講じる必要も出てくることがあります。
販売店との間で売買契約が解除され、販売店と信販会社との間で解約処理が行われれば、以後、信販会社からの請求は止まりますし、契約解除の原因が、販売店側にある場合には、既に支払ったお金も取り戻すことができます。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
特定商取引法の概要
特定商取引法は、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めている法律です。
つまり、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守るための法律であると言えます。
特定商取引法の対象となる取引類型は7つあります。
・訪問販売
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、商品、権利の販売又は役務(サービス)の提供を行う取引、キャッチセールス、アポイントメントセールス等のこと。
・通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「インターネット・オークション」も含みますが、「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。
・電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。
・連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと。
・特定継続的役務提供
長期・継続的な役務(「えきむ」と読み、いわゆるサービスを意味します)の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象です。
・業務提供誘引販売取引
仕事を提供するので収入が得られる、と消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
・訪問購入
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと。
特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じ、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令の行政処分、または罰則の対象となります。
・氏名等の明示義務
勧誘開始前に事業者名や、勧誘目的であることなどを消費者に告げるよう事業者に義務づけています。
・不当な勧誘行為の禁止
不実告知(虚偽の説明)や、重要事項(価格・支払い条件等)を故意に告知しなかったり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
・広告規制
事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
・書面交付義務
契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務づけています。
また、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取り消しなどを認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどの下記ルールを定めています。
・クーリングオフ
クーリングオフとは、申込みまたは契約後に法律で決められた書面を受け取ってから一定期間、消費者が冷静に再考して、無条件で解約することです。
訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間のクーリングオフ期間が設けられています。
ちなみに、通信販売には、クーリングオフに関する規定はありません(しかし通信販売には返品特約事項記載義務等が設定されています)。
・意思表示の取消し
事業者が不実告知や重要事項の故意による不実告知等の違法行為を行ったため、消費者が誤認し、契約の申込み、またはその承諾の意思表示をしたときには、消費者は、その意思表示を取り消すことができます。
・損害賠償等の額の制限
消費者が中途解約する際等、事業者が消費者へ請求できる損害賠償額には上限額が設定されています。
※ご自分の取引がどの類型に該当し、事業者にどのような違反があるのかを確認し、どのような法根拠にてどのようなことが請求できるのかを検討してみてください。わからなければ、弊所までご連絡ください。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
クーリングオフはいつまでにすればいいのか?
クーリングオフは、「法律で決められた事項がきちんと記載された書面を受け取った日から数えて○日間以内」に行なえばよいと、特定商取引法に定義されています。
ということは、書面を受け取っていなければ、クーリングオフの最初の日が起算していないことになるので、書面が届くまでは、いつまででもクーリングオフが可能ということです。
※もちろん、書面が届けば、その日がクーリングオフの起算点となります。
また、「法律で決められた事項がきちんと記載された書面」でなければ、法的に無効なので、このような書面が届いても、クーリングオフの最初の日は起算しません。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
ネットの個人オークションとクーリングオフ
個人が単に自分の所有物をネットオークションに出品するだけの場合で、かつ反復継続性が認められない場合には、特定商取引法の適用はありませんので、この場合、クーリングオフの適用はありません。しかも、返品特約の表示義務もありません。
しかし、営利意思をもち反復継続して取引を行う意思が客観的に認められる場合、特定商取引法上の「販売業者」に該当しますので、特定商取引法の規制対象となります。この場合、特定商取引法に基づき販売業者としての表示義務があり、返品特約についても表示する義務が生じることとなります。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
特定商取引法 訪問販売
●「訪問販売」とは、販売業者または役務提供事業者が、
店舗等以外の場所(例えば、一般消費者の自宅等)で行う商品、権利の販売または役務(サービス)の提供のことをいいます。
最も一般的な訪問販売は、消費者の住居をセールスマンが訪問して契約を行うなどの販売方法です。
そのほか、喫茶店や路上での販売、またホテルや公民館を一時的に借りるなどして行われる展示販売のうち、期間、施設等からみて、店舗に類似するものとは認められないものも訪問販売に該当します。
また、特定の方法によって誘った客に対して、通常の店舗等で行う商品、権利の販売や役務の提供のことも意味します。
※営業所等で行われた契約であっても、「訪問販売」に該当する場合があります。たとえば、路上等営業所以外の場所で消費者を呼び止めて営業所等に同行させて契約させる場合(いわゆるキャッチセールス)や、電話や郵便等で販売目的を明示せずに消費者を呼び出したり、「あなたは特別に選ばれました」等、ほかの者に比べて著しく有利な条件で契約できると消費者を誘って営業所等に呼び出したりして契約させる場合(いわゆるアポイントメントセールス)が該当します。
「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者を意味します。
「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。なお、営利の意思の有無については、その者の意思にかかわらず、客観的に判断されることになります。
●以下の場合、特定商取引法は適用されません。
・事業者間取引の場合
・海外にいる人に対する契約
・国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
・特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
・事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合
・株式会社以外が発行する新聞紙の販売
・他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの
●事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して以下のことを告げなければなりません。
・事業者の氏名(名称)
・契約の締結について勧誘をする目的であること
・販売しようとする商品(権利、役務)の種類
●事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければなりません。
●消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することが禁止されています。
●事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を結んだときには、以下の事項を記載した書面を消費者に渡さなければなりません。
・商品(権利、役務)の種類
・販売価格(役務の対価)
・代金(対価)の支払時期、方法
・商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
・契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
・契約の申込み又は締結の年月日
・商品名、商品の商標または製造業者名
・商品の型式
・商品の数量
・商品に隠れた瑕疵(一見しただけではわからない不具合)があった場合、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容
・契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
・そのほか特約があるときには、その内容
●消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリングオフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
●訪問販売において以下のような不当な行為は禁止されています。
・売買契約等の締結について勧誘を行う際、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
・売買契約等の締結について勧誘を行う際、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、故意に事実を告げないこと
・売買契約を締結させ、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること
・勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、売買契約等の締結について勧誘を行うこと
●訪問販売の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)できます。
●なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、クーリングオフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリングオフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリングオフできます(クーリングオフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも内容証明郵便等で行うことをお薦めします)。
●クーリングオフを行った場合、消費者は、すでに商品もしくは権利を受け取っている場合には、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことや、権利を返還することができます。
また、商品が使用されている場合や、役務がすでに提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。
消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、すでに頭金等の対価を支払っている場合には、すみやかにその金額を返してもらうとともに、土地または建物そのほかの工作物の現状が変更されている場合には、無償で元に戻してもらうことができます。
ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品等)を使ってしまった場合や、現金取引の場合であって代金または対価の総額が3,000円未満の場合には、クーリングオフの規定が適用されませんので注意が必要です。
●訪問販売の際、消費者が通常必要とされる量を著しく超える商品(役務・指定権利)を購入する契約を結んだ場合、契約締結後1年間は、契約の申込みの撤回又は契約の解除ができます。(消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは除く。)
●クーリングオフ期間の経過後、消費者の債務不履行を理由として事業者から契約が解除された場合に、事業者から法外な損害賠償を請求されることがないよう、事業者は以下の額を超えて請求できません。
・商品(権利)が返還された場合、通常の使用料の額(販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常の使用料の額を超えているときにはその額)
・商品(権利)が返還されない場合、販売価格に相当する額
・役務を提供した後である場合、提供した役務の対価に相当する額
・商品(権利)をまだ渡していない場合(役務を提供する前である場合)、契約の締結や履行に通常要する費用の額
※これらに法定利率年6%(商法)の遅延損害金が加算されます。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
特定商取引法 通信販売
●「通信販売」とは、販売業者または役務提供事業者が「郵便等」によって売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売または役務提供をいいます。
たとえば新聞や雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネットオークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、チラシ等を見た消費者が、郵便や電話、ファクシミリ、インターネット等で購入の申込みを行う取引です(ただし「電話勧誘販売」に該当する場合は除く)。
「郵便等」には、郵便または信書便、電話機、ファクシミリ装置そのほかの通信機器または情報処理に用いられる機器を利用する方法、電報、預金または貯金の口座に対する払込みのいずれかであれば該当します。
●通信販売では、以下の事項を広告で表示しなければなりません。
・販売価格(役務の対価)※送料についても表示が必要
・代金(対価)の支払い時期、方法
・商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
・商品(指定権利)の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品の特約がある場合はその旨。
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
・事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
・申込みの有効期限があるときには、その期限
・販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
・商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
・いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
・商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
・請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額。
・電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
※消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面
(インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供で きるような措置を講じている場合、上記の広告表示事項を一部省略することができます。しかし、通信販売における返品特約(返品の可否、返品期間等の条件、返品の送料負担の有無)、申し込みの有効期限、電子メールアドレス(電子メールで広告する場合)の広告表示は省略できません。
●表示事項等については、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」は禁止されています。
●さらに、消費者があらかじめ承諾しない限り、事業者が電子メール広告を送信することは原則禁止されています。しかし次の場合は対象外です。
・「契約の成立」「注文確認」「発送通知」などに付随した広告
・メルマガに付随した広告
・フリーメール等に付随した広告
●「前払式」の通信販売の場合、事業者は、代金を受け取り、その後商品の引渡しに時間がかかるときには、その申込みの諾否等、以下の事項を記載した書面を渡さなければなりません。
・申込みの承諾の有無(承諾しないときには、受け取ったお金をすぐに返すことと、その方法を明らかにしなければならない)
・代金(対価)を受け取る前に申込みの承諾の有無を通知しているときには、その旨
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
・受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときには、その合計額)
・当該金銭を受け取った年月日
・申込みを受けた商品とその数量(権利、役務の種類)
・承諾するときには、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)(期間または期限を明らかにすることにより行わなければならない)
●売買契約の申込みの撤回後、契約当事者双方に原状回復義務が課された場合、事業者は代金返還などの債務の履行を拒否したり、遅延したりすることが禁止されています。
●インターネット通販においては、下記のような顧客の意に反して契約の申込みをさせることは禁止されています。
・クリックすれば、有料の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していないこと
・申込みをする際、消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ訂正できるように措置していないこと
通信販売では、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、その契約にかかる商品の引渡し(指定権利の移転)を受けた日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます(これはクーリングオフではありません。クーリングオフは無条件解除なので、消費者の送料負担はありません)。しかし、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、その特約によります。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
特定商取引法 電話勧誘販売
●「電話勧誘販売」とは、販売業者または役務提供事業者が、消費者に電話をかけ、または特定の方法により電話をかけさせ、その電話において行う勧誘によって、消費者からの売買契約または役務提供契約の申込みを「郵便等」により受け、または契約を締結して行う商品、権利の販売または役務の提供のことをいいます。
●電話をいったん切った後、郵便、電話等によって消費者が申込みを行った場合でも、電話勧誘によって消費者の購入意思の決定が行われた場合には、「電話勧誘販売」に該当します。
●さらに、事業者が欺瞞的な方法で消費者に電話をかけさせて勧誘した場合も「電話勧誘販売」に該当します。電話をかけさせる方法については、下記が定められています。
・当該契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること
・他の者に比して著しく有利な条件で契約を締結できることを告げ、電話をかけることを要請すること
●事業者は、電話勧誘販売を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して以下の事項を告げなければなりません。
・事業者の氏名(名称)
・勧誘を行う者の氏名
・販売しようとする商品(権利、役務)の種類
・契約の締結について勧誘する目的である旨
●事業者は、契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘することを禁止されています。
●事業者は契約の申込みを受けたとき、または契約を締結したときには、以下の事項を記載した書面を消費者に渡さなければなりません。
・商品(権利、役務)の種類
・販売価格(役務の対価)
・代金(対価)の支払い時期、方法
・商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
・契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項(クーリング・オフができない部分的適用除外がある場合はその旨含む。)
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・契約の締結を担当した者の氏名
・契約の締結の年月日
・商品名、商品の商標または製造業者名
・商品の型式
・商品の数量
・商品に隠れた瑕疵(一見しただけではわからない不具合)があった場合、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容
・契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
・そのほか特約があるときには、その内容
●このほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字および数字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
●「前払式」の電話勧誘販売の場合、事業者は、代金を受け取り、その後商品の引渡しに時間がかかるときには、その申込みの諾否等、以下の事項を記載した書面を渡さなければなりません。
・申込みの承諾の有無(承諾しないときには、受け取ったお金をすぐに返すことと、その方法を明らかにしなければならない)
・代金(対価)を受け取る前に申込みの承諾の有無を通知しているときには、その旨
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
・受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときには、その合計額)
・当該金銭を受け取った年月日
・申込みを受けた商品とその数量(権利、役務の種類)
・承諾するときには、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)(期間または期限を明らかにすることにより行わなければならない)
●電話勧誘販売においては、以下の不当行為を禁止されています。
・売買契約等の締結について勧誘を行う際、または締結後、申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
・売買契約等の締結について勧誘を行う際、または締結後、申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、故意に事実を告げないこと
・売買契約を締結させ、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること
●電話勧誘販売において、消費者が契約を申込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)することができます。
●なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、クーリングオフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリングオフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリングオフできます。
●クーリングオフを行った場合、消費者がすでに商品もしくは権利を受け取っている場合には、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことおよび権利を返還することができます。
また、役務がすでに提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。
消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、すでに頭金等対価を支払っている場合にはすみやかにその金額を返してもらうとともに、土地または建物そのほかの工作物の現状が変更されている場合には、無償で元に戻してもらうことができます。
●ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品等)を使ってしまった場合や、現金取引の場合であって代金または対価の総額が3,000円未満の場合には、クーリングオフの規定が適用されません。
●クーリングオフ期間の経過後、消費者の債務不履行を理由として事業者から契約が解除された場合に、事業者から法外な損害賠償を請求されることがないよう、事業者は以下の額を超えて請求できません。
・商品(権利)が返還された場合、通常の使用料の額(販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常の使用料の額を超えているときにはその額)
・商品(権利)が返還されない場合、販売価格に相当する額
・役務を提供した後である場合、提供した役務の対価に相当する額
・商品(権利)をまだ渡していない場合(役務を提供する前である場合)、契約の締結や履行に通常要する費用の額
※これらに法定利率年6%(商法)の遅延損害金が加算されます。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
特定商取引 マルチ商法等(連鎖販売取引)
●「連鎖販売取引」とは、物品の販売(または役務の提供等)の事業で、再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を、特定利益が得られると誘引し、特定負担を伴う取引をするものです。
●例えば、「○○会に入会すると、○割引で商品を購入できます!人を誘ってその人に商品を売れば、あなたにお金を還元します!」等の取引を指します。いわゆるマルチ商法やネットワークビジネス(商品を買って販売組織に参加した会員が、友人・知人を組織に加入させ、新たに会員になった人がさらに新しい会員を加入させ組織を拡大していく商法)等と呼ばれるものです。
●統括者(連鎖販売取引を実質的に掌握している者)、勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)または一般連鎖販売業者(統括者または勧誘者以外の連鎖販売取引を行う者)は、連鎖販売取引を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して、下記の事項を告げる必要があります。
・統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)(勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む)
・特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
・その勧誘にかかわる商品または役務の種類
連鎖販売取引においては、下記の行為が禁止されています。
・勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、商品の品質・性能など、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。
・勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること。
・勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。
●連鎖販売取引の広告には、下記の事項を表示しなければなりません。
・商品(役務)の種類
・取引に伴う特定負担に関する事項
・特定利益について広告をするときにはその計算方法
・統括者などの氏名(名称)、住所、電話番号
・統括者などが法人で、電子情報処理組織を使用する方法によって広告をする場合には、当該統括者などの代表者または連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
・商品名
・電子メールによる商業広告を送る場合には、統括者などの電子メールアドレス
●もちろん、誇大広告は禁止されていますし、未承諾者に対する電子メール広告の提供も原則禁止です。
●連鎖販売取引を行う者が連鎖販売取引契約をする場合、下記事項が記載された書面を消費者に渡さなければなりません。
・契約の締結前
・統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
・商品名
・商品の販売価格、引渡時期および方法そのほかの販売条件に関する重要な事項(権利の販売条件、役務の提供条件に関する重要な事項)
・特定利益に関する事項
・特定負担の内容
・契約の解除の条件そのほかの契約に関する重要な事項
・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
・特定商取引法第34条に規定する禁止行為に関する事項
・契約締結後
・商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項)
・商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項
・特定負担に関する事項
・連鎖販売契約の解除に関する事項
・統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・契約年月日
・商標、商号そのほか特定の表示に関する事項
・特定利益に関する事項
・特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容
・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
・特定商取引法第34条に規定する禁止行為に関する事項
●このほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリングオフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字および数字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
●連鎖販売取引において、消費者が契約を申込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合にはその日)から数えて20日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)することができます。
●なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、クーリングオフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリングオフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリングオフできます。
●クーリングオフを行った場合、事業者は契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを請求できず、商品の引取り費用も事業者の負担となります。ただし、原状回復義務については、契約を解除する双方が負うことになります。事業者は支払われた代金、取引料を返還し、消費者は引渡しを受けた商品を事業者に返還しなければなりません。
●平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者(無店舗個人)は、クーリングオフ期間の経過後であっても、下記条件を全て満たせば、将来に向かって連鎖販売契約を中途解除できます。
・入会後1年を経過していないこと
・引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
・商品を再販売していないこと
・商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く)
・自らの責任で商品を滅失または毀損していないこと
※契約解除に伴う違約金の上限は、返品する商品価格の10%以内となります。
●平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売取引を行う者が、契約締結を勧誘する際、下記行為をしたことによって、消費者が誤認をし、それにより契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、取り消すことができます。
・事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
・故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
特定商取引 特定継続的役務提供
●「特定継続的役務」とは、政令で定める「特定継続的役務(役務提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務)」を、一定期間を超える期間に渡り、一定金額を超える対価を受け取って提供するものです。
●これには役務(サービス)提供を受ける権利の販売も含まれ、「特定権利販売」と呼ばれます。この要件に該当すれば、店頭契約も規制対象となります。
●現在、以下の6役務が特定継続的役務として指定されています。
・エステ(期間が1月を超えるもの)
・語学教室(期間が2月を超えるもの)
・家庭教師(期間が2月を超えるもの。または入学金、受講料、教材費、関連商品の販売など、契約金の総額が5万円を超えるもの)
・学習塾(2月を超えるもの。または入学金、受講料、教材費、関連商品の販売など、契約金の総額が5万円を超えるもの)
・パソコン教室(2月を超えるもの)
・結婚相手紹介サービス(2月を超えるもの)
※「家庭教師」および「学習塾」には、小学校または幼稚園に入学するためのいわゆる「お受験」対策は含まれません。
※「学習塾」には、浪人生のみを対象にしたコースは対象になりません。しかし高校生と浪人生が両方含まれるコースは全体として対象になります。
●事業者が特定継続的役務提供(特定権利販売)契約する場合、下記の書面を消費者に渡す必要があります。
・契約締結前
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・役務の内容
・購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
・役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の概算額
・上記の金銭の支払い時期、方法
・役務の提供期間
・クーリングオフに関する事項
・中途解約に関する事項
・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
・前受金の保全に関する事項
・特約があるときには、その内容
・契約締結後
・役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
・役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の額
・上記の金銭の支払い時期、方法
・役務の提供期間
・クーリングオフに関する事項
・中途解約に関する事項
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・契約の締結を担当した者の氏名
・契約の締結の年月日
・購入が必要な商品がある場合には、その種類、数量
・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
・前受金の保全措置の有無、その内容
・購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・特約があるときには、その内容
●もちろん、誇大広告は禁止されていますし、下記不当行為も禁止されています。
・契約の締結について勧誘を行う際、または締結後、その解除を妨げるために、事実と違うことを告げること
・契約の締結について勧誘を行う際、または締結後、その解除を妨げるために、故意に事実を告げないこと
・契約の締結について勧誘を行う際、または締結後、その解除を妨げるために、相手を威迫して困惑させること
●「前払方式」で5万円を超える特定継続的役務提供を行う事業者に対しては、消費者が事業者の財務内容などについて確認できるよう、その業務および財産の状況を記載した書類(貸借対照表、損益計算書など)を用意しておくことや、それを、消費者の求めに応じて、閲覧できるようにしておかねばなりません。
●特定継続的役務提供の際、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により契約(関連商品の販売契約を含む)をクーリングオフすることができます。
●なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリングオフをしなかった場合、上記期間を経過していても、消費者はクーリングオフできます。
●クーリングオフを行った場合、消費者がすでに商品もしくは権利を受け取っている場合には、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことおよび権利を返還することができます。
また、役務がすでに提供されている場合でも、消費者はその対価を支払う必要はありません。
消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、すでにに頭金など対価を支払っている場合には、すみやかにその金額を返してもらうことができます。
●ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる消耗品(健康食品、化粧品等)を使用してしまった場合には、クーリングオフの規定が適用されません。
※「関連商品」とは、特定継続的役務の提供の際、消費者が購入する必要がある商品として政令で定められている商品のことを指します。具体的には、下記が関連商品として指定されています。
エステ
健康食品、化粧品、石けん(医薬品を除く)および浴用剤、下着類・美顔器、脱毛器
語学教室、家庭教師、学習塾
書籍(教材を含む)、カセット・テープ、CD、CD-ROM、DVD等、ファクシミリ機器、テレビ電話
パソコン教室
電子計算機およびワードプロセッサー並びにこれらの部品および付属品、書籍・カセット・テープ、CD、CD-ROM、DVD等
結婚相手紹介サービス
真珠並びに貴石および半貴石、指輪その他の装身具
●消費者は、クーリングオフ期間の経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供など契約(関連商品の販売契約を含む)を解除(中途解約)することができます。
その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償などの額の上限は、下記に示すようになります。※それ以上の額をすでに受け取っている場合には、残額を返還する必要があります 。
<事業者から消費者への損害賠償額の上限>
・役務提供前に契約解除した場合
エステ 20,000万円
語学教室 15,000円
家庭教師 20,000円
学習塾 11,000円
パソコン教室 15,000円
結婚相手紹介サービス 30,000円
・役務提供後に契約解除した場合
(提供された特定継続的役務の対価に相当する額)に下記の額を足した額
エステ 20,000円、または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額
語学教室 50,000円、または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
家庭教師 50,000円、または一ヶ月分の授業料相当額のいずれか低い額
学習塾 20,000円、または一ヶ月分の授業料のいずれか低い額
パソコン教室 50,000円、または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
結婚相手紹介サービス 20,000円、または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
●平成16年11月11日以降の契約については、事業者が契約締結を勧誘する際、下記行為をしたことによって、消費者が誤認をし、それにより契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、取り消すことができます。
・事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
・故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
特定商取引 業務提供誘引販売取引
●「業務提供誘引販売取引」とは、物品の販売または役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって、業務提供利益が得られると相手方を誘引し、その者と特定負担を伴う取引をするものです。
例を挙げると、
・PCとソフトを購入したら、それを使ってHP作成を行い利益が得られるとするもの
・着物を購入したら、その着物を着て、接客業務を行い利益が得られるとするもの
・寝具を購入したら、モニターになれて、その感想を提供すれば利益が得られるとするもの
等です。
●業務提供誘引販売業者は、勧誘に先立って、消費者に対して、下記事項を告げる必要があります。
・業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)
・特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
・その勧誘に関する商品または役務の種類
●業務提供誘引販売取引業者が、契約の締結について勧誘を行う際、または締結後、取引の相手方に契約を解除させないようにするために、嘘をついたり威迫して困惑させるなどの不当な行為は禁止されています。
●広告表示義務事項は、以下の通りです。
・商品(役務)の種類
・取引に伴う特定負担に関する事項
・業務の提供条件
・業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号
・業務提供誘引販売業を行う者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法によって広告をする場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者の代表者または業務提供誘引販売業に関する業務の責任者の氏名
・商品名
・電子メールによる商業広告を送る場合には、業務提供誘引販売業を行う者の電子メールアドレス
●もちろん、誇大広告は禁止です。未承諾者に対する電子メール広告の提供も原則禁止です。
●業務提供誘引販売業を行う者には下記内容の書面提示義務があります。
・契約締結前
・業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
・商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
・商品名
・商品(提供される役務)を利用する業務の提供(あっせん)についての条件に関する重要な事項
・特定負担の内容
・契約の解除の条件そのほかの契約に関する重要な事項
・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
・契約締結後
・商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項)
・商品(提供される役務)を利用する業務の提供(あっせん)についての条件に関する重要な事項
・特定負担に関する事項
・業務提供誘引販売契約の解除に関する事項
・業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
・契約の締結を担当した者の氏名
・契約年月日
・商品名、商品の商標または製造者名
・特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容
・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
●このほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリングオフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字および数字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
●法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合にはその日)から数えて20日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)することができます。
●なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、クーリングオフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリングオフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリングオフできます。
●クーリングオフを行った場合、消費者がすでに商品もしくは権利を受け取っている場合には、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことおよび権利を返還することができます。原状回復義務については、契約を解除する双方が負うことになります。事業者は支払われた代金、取引料を返還し、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。
●平成16年11月11日以降の契約については、事業者が契約締結について勧誘をする際、下記のような行為をしたことによって、消費者が誤認をしたことにより契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、意思表示を取り消すことができます。
・事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
・故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合
●クーリング・オフ期間の経過後、代金の支払い遅延等、消費者の債務不履行を理由として、事業者から契約が解除された場合、事業者は、下記の額を超える損害賠償を請求できません。
・商品が返還された場合には、通常の使用料の額(販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常の使用料の額を超えているときにはその額)
・商品が返還されない場合には、販売価格に相当する額
・役務を提供した後である場合には、提供した役務の対価に相当する額
・商品をまだ渡していない場合(役務を提供する前である場合)には、契約の締結や履行に通常要する費用の額
※法定利率年6%(商法)の遅延損害金が加算されます。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
特定商取引 訪問購入
●「訪問購入」とは、購入業者が、一般消費者の自宅等の店舗等以外の場所で行う物品購入のことをいいます。
●ただし、自動車(2輪のものを除く)、家具、家電、有価証券(携行が容易なものを除く)、本、CDやDVDゲームソフト類は対象外です。
●また、消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場合、いわゆる御用聞き取引の場合、いわゆる常連取引の場合、転居に伴う売却の場合も対象外です。
●事業者は、訪問購入を行うときには、勧誘に先立って、相手方に対して下記事項を告げる必要があります。
・事業者の氏名(名称)
・契約の締結について勧誘をする目的であること
・購入しようとする物品の種類
●事業者は、勧誘要請をしていない者に対し、相手方の自宅等で売買契約の締結について勧誘をしてはなりません。また、勧誘を受ける意思の有無を確認してもいけません。いわゆる飛込み勧誘や、単に相手方から査定の依頼があった場合に、査定を超えて勧誘を行うことは違法です。
●事業者は、訪問購入を行うときには、勧誘に先立って相手方に勧誘を受ける意思があることを確認する必要があります。
●また、相手方が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続してはなりません。かつ、その後改めて勧誘することも禁止です。
●事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を結んだときには、下記事項を記載した書面を相手方に渡す必要があります。
・物品の種類
・物品の購入価格
・代金の支払時期、方法
・物品の引渡時期、方法
・契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項
・物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
・契約の申込み又は締結の年月日
・物品名
・物品の特徴
・物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
・契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
・そのほか特約があるときには、その内容
●このほか相手方に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載する義務がああります。また、クーリングオフに関する事項と、物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項についても赤枠の中に赤字で記載する義務があります。さらに、書面の字の大きさは8ポイント以上であることが必要です。
●事業者は、クーリングオフ期間内に売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、相手方に対して当該物品の引渡しを拒むことが出来る旨を告げる義務があります。
●訪問購入において下記不当行為は禁止されています。
・売買契約の締結について勧誘を行う際、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
・売買契約の締結について勧誘を行う際、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、故意に事実を告げないこと
・売買契約を締結させ、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること
・売買契約の対象となる物品の引渡しを受けるため、引渡し時期その他物品の引渡しに関する重要な事項について、故意に事実を告げない、事実と違うことを告げる、又は相手を威迫して困惑させること。
●事業者は、訪問購入取引の相手方から物品の引渡しを受けた後、クーリングオフ期間内に、第三者へ当該物品を引き渡したときは、下記事項を、遅滞なく、相手方に通知する義務があります。
・第三者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・物品を第三者に引き渡した年月日
・物品の種類
・物品名
・物品の特徴
・物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
・その他相手方が第三者への物品の引渡しの状況を知るために参考となるべき事項
●事業者は、訪問購入取引の相手方から物品の引渡しを受けた後、クーリングオフ期間内に、第三者へ当該物品を引き渡すときは、下記事項を、施行規則様式第5又は様式第5の2による書面にて、第三者に通知する義務があります。
・第三者に引き渡した物品が訪問購入取引の相手方から引渡しを受けた物品であること
・相手方がクーリングオフを行うことができること
・相手方がクーリングオフできる期間に関する事項
・事業者が相手方に対して法第58条の8の書面を交付した年月日
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・事業者が物品を第三者に引き渡す年月日
・物品の種類
・物品名
・物品の特徴
・物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
●訪問購入で、売買契約の相手方が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、相手方は事業者に対して、書面によりクーリングオフができます。
●事業者が、クーリングオフに関する事項につき事実と違うことを告げたり威迫したりすることによって、相手方が誤認・困惑してクーリングオフしなかった場合は、上記期間を経過していても、相手方はクーリングオフできます。
●クーリングオフを実行した場合、契約解除の効果は第三者にも及びます。
※ただし、第三者がクーリングオフされる可能性があったことについて善意かつ無過失であった場合には及びません。
●クーリングオフを行った場合、相手方は、すでに物品を事業者に引き渡していたり、代金を受け取っている場合には、事業者の負担によって、物品を返却してもらったり、代金を返却することができます。代金の利息を返却する必要はありません。また損害賠償や違約金を支払う必要もありません。
●売買契約の相手方は、クーリングオフ期間内は、事業者に対して契約対象である物品の引渡しを拒んでも、債務不履行に陥ることはありません。
●クーリングオフ期間の経過後、売買契約の相手方の債務不履行(物品の引渡し遅延等)を理由として、契約が事業者から解除された場合には、事業者は、以下の額を超えて損害賠償請求をすることは出来ません。
・事業者から代金が支払われている場合、当該代金に相当する額
・事業者から代金が支払われていない場合、契約の締結や履行に通常要する費用の額
※法定利率年6%(商法)の遅延損害金が加算されます。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
特定商取引法 指定商品 指定権利 指定役務 指定消耗品
平成21年12月1日より、原則すべての商品・役務の取引が、特定商取引法の対象となりました。
ただし、権利の販売については、政令で定める指定権利を取扱う取引のみが、同法の適用対象です。
商品
- 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く)
- みそ、しょうゆその他の調味料
- 犬及び猫並びに熱帯魚その他の観賞用動物
- 盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝並びに種苗を除く)
- 障子、雨戸、門扉その他の建具
- 手編み毛糸及び手芸糸
- 不織布及び幅が13センチメートル以上の織物
- 真珠並びに貴石及び半貴石
- 金、銀、白金その他の貴金属
- 家庭用石油タンク並びにその部品及び付属品
- 太陽光発電装置その他の発電装置
- ペンチ、ドライバーその他の作業工具及び電気ドリル、電気のこぎりその他の電動工具
- 家庭用ミシン及び手編み機械
- ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり及び血圧計
- 時計
- 望遠鏡、双眼鏡及び生物顕微鏡
- 写真機械器具
- 映画機械器具及び映画用フィルム(8ミリ用のものに限る)
- 複写機及びワードプロセッサー
- 乗車用ヘルメットその他の安全帽子、繊維製の避難はしご及び避難ロープ並びに消火器及び消火器用消火薬剤
- 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
- はさみ、ナイフ、包丁その他の利器及びのみ、かんな、のこぎりその他の工匠具
- ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器
- 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置及びアマチュア無線用機器
- 超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置
- 電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び付属品
- 乗用自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む)並びにこれらの部品及び付属品
- 自転車並びにその部品及び付属品
- ショッピングカート及び歩行補助車
- れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
- 眼鏡並びにその部品及び付属品並びに補聴器
- 家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器及び近視矯正器
- コンドーム、生理用品及び家庭用の医療用洗浄器
- 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)並びにかび防止剤及び防湿剤
- 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
- 衣服
- ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のものを除く)その他の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具、喫煙具及び化粧用具
- 履物
- 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用繊維製品及び壁紙
- 家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の住生活用品
- 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
- ストーブ、温風機その他の暖房用具、レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び湯沸器(電気加熱式のものを除く)、太陽熱利用冷温熱装置並びにバーナーであって除草に用いることができるもの
- 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備並びにこれらの部品及び付属品
- 融雪機その他の家庭用の融雪設備
- なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
- 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
- おもちゃ及び人形
- 釣漁具、テント及び運動用具
- 滑り台、ぶらんこ、鉄棒及び子供用車両
- 新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍及び地図
- 地球儀、写真(印刷したものを含む)並びに書画及び版画の複製品
- 磁気記録媒体並びにレコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
- シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印章及び印肉、アルバム並びに絵画用品
- 楽器
- かつら
- 神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具
- 砂利及び庭石、墓石その他の石材製品
- 絵画、彫刻その他の美術工芸品及びメダルその他の収集品
権利
- 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
- 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
- 語学の教授を受ける権利
役務
- 庭の改良
- 次に掲げる物品の貸与
- 家庭用ミシン
- 複写機及びワードプロセッサー
- 消火器
- 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
- 家庭用の医療用洗浄器
- ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具及び電圧調整器
- 電話機及びファクシミリ装置
- 電子計算機
- 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び近視眼矯正器
- 衣服
- 寝具
- 浄水器
- 楽器
- 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること
- 住居又は次に掲げる物品の清掃
- 家庭用石油タンク
- エアコンディショナー及び換気扇
- 床敷物及び布団
- 太陽熱利用冷温熱装置
- ふろがま
- 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
- 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと
- 墓地又は納骨堂を使用させること
- 眼鏡若しくはかつらの調製又は衣服の仕立て
- 次に掲げる物品の取付け又は設置
- 障子、雨戸、門扉その他の建具
- 太陽光発電装置その他の発電装置
- 家庭用の医療用洗浄器
- ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器
- 電話機、インターホン、ファクシミリ装置及びアマチュア無線用機器
- れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
- 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
- 融雪機その他の家庭用の融雪設備
- 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の組立て又は設置
- 次に掲げる物品の取り外し又は撤去
- 家庭用電気機械器具
- 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)並びにかび防止剤及び防湿剤
- 太陽熱利用冷温熱装置
- 浄化槽
- 結婚又は交際を希望する者への異性の紹介
- 易断を行うこと、または易断の結果に基づき助言、指導その他の援助を行うこと
- 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、又は観覧させること
- 家屋、門若しくは塀又は次に揚げる物品の修繕又は改良
- 障子、雨戸、門扉その他の建具
- 家庭用石油タンク
- 太陽光発電装置その他の発電装置
- 家庭用ミシン及び換気扇
- 履物
- 畳及び布団
- 太陽熱利用冷温熱装置
- ふろがま
- 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
- 神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具
- プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること
- 名簿、人名録その他の書籍(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む)をもって調製するものを含む)、新聞又は雑誌への氏名、経歴その他の個人に関する情報の掲載若しくは記録又はこれらに掲載され若しくは記録された当該情報の訂正、追加、削除若しくは提供
- 土地の測量、整地又は除草
- 家屋における有害動物又は有害植物の防除
- 住宅への入居の申込み手続の代行
- 技芸又は知識の教授
- 次に掲げる取引(商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引に該当するもの及び海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)第二条第二項に規定する海外商品市場における同条第一項に規定する先物取引に該当するものを除く。)またはこれらの取引の委託の媒介、取次ぎまたは代理を行うこと(いずれも当該取引の決済に必要な金銭の預託を受けるものに限る。)
イ 物品の売買取引(役務の提供を受ける者に当該物品が現に引き渡されることとなるものを除く。)ロ 物品についてあらかじめ約定する価格と将来の一定の時期における現実の当該物品の価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引ハ 商品指数(二以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値をいう。)についてあらかじめ約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該商品指数の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引ニ 当事者の一方の意思表示により当事者間においてイ、ロまたはハに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
消耗品
- 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く)…健康食品のこと
- 不織布及び幅が13センチメートル以上の織物
- コンドーム及び生理用品
- 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
- 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
- 履物
- 壁紙
- 配置薬(平成21年12月1日~)
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
通信販売でクーリングオフは出来ない!?
通信販売には、特定商取引法において、クーリングオフの適用はありません。
クーリングオフは、訪問販売等の「不意打ち」的な販売から消費者を守るための制度なので、通信販売のように自分の意思で冷静に判断できるような販売の場合は、保護する必要性が低いから、というのがその理由です。
しかし、通信販売は、特定商取引法で該当する取引形態なので、やはり消費者保護の道が設けられています。
それが返品特約の表示義務です。
通信販売事業者は、返品特約(返品の可否・返送期間等の条件、返品の送料負担の有無)に関する情報を、広告に記載しなければなりません。
インターネット通販の場合、この返品特約の表示は、広告だけでなく、最終申込み画面にも表示しなければなりません。広告と最終申込み画面に表示していて、はじめて返品特約の表示義務を履行したことになります。
※返品特約義務を履行している事業者は、クーリングオフ義務を免除される、という考え方です。
返品特約義務を履行していない通信販売事業者との取引の場合、消費者は、商品の受け取り後、8日以内(商品受領日が第一日目)に 返品(契約の解除)が出来ます。
しかしこれはクーリングオフ(無条件解除)ではないので、送料は消費者負担となります。
そしてこの場合、民法の規定にしたがって契約の取り消しや解除がなされるので、使用・消費したものや消費者の故意過失により破損した商品については原状回復義務が課せられ(事業者、消費者双方に課せられます)、事業者に損害を賠償しなければならない可能性があることに留意しなければなりません。
ネットも含めて通信販売事業者を選択する場合は、返品特約を十分に精査することが肝要です。
もちろん、通信販売であっても、契約した商品と異なる商品が納品されたり、商品が破損、欠損、故障していたり、広告内容と明らかに異なるような場合は、クーリングオフの問題とは関係なく、返品や交換、修理の要求、または代金減額請求、あるいは契約解除の請求が出来ます。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
消費者契約法で規定されている契約の取り消しと無効
「消費者契約法」は、消費者と事業者の力の格差を埋め、消費者と事業者が対等に契約できるように生まれたルールであり、消費者が事業者と締結した契約(消費者契約)を全て対象としています
消費者は、事業者の下記の不適切な行為により、自由な意思決定が妨げられ、誤認又は困惑を起こして結んだ契約は取り消すことができます。
(1)不実告知 重要な項目について事実と違うことを言う
(2)断定的判断 将来の変動が不確実なことを断定的に言う
(3)不利益事実の不告知
利益になることだけ言って、かつ重要な項目について不利益になることを故意に言わない
(4)不退去 帰ってほしいといったのに帰らない
(5)監禁 帰りたいといったのに帰してくれない
なお、消費者契約法上、取消ができるのは、誤認に気がついた時、困惑の行為の時から6カ月、または契約の時から5年以内です。
取消権を行使すると、事業者には代金全額を返還する義務が生じます。しかし、事業者は消費者に対して、損害賠償や違約金を請求することはできません。
一方、消費者も事業者に対して、受け取ったものは現物で返還しなければなりません。しかし、消費者がすでにサービスの提供を受けていた場合、消費したものの価値を金銭的に評価して返還する必要はなく、受け取ったものを消費してしまっていた場合、残っている分を返還するだけでかまいません。
また、消費者が事業者と結んだ契約において、下記に該当する消費者の利益を不当に害する一定の条項の全部又は一部が無効となります。
(1)事業者の損賠賠償の責任を免除する条項の無効(「消費者契約法」第8条)
事業者の債務不履行、不法行為や瑕疵担保責任による損害賠償を免除することは無効です
(2)消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項の無効(同第9条)
不当に高額な違約金や解約損金や、不当に高額な遅延損害金(年14.6%以上)は無効です
(3)消費者の利益を一方的に害する条項の無効(同第10条)
信義誠実に反して消費者の利益を一方的に害する条項は無効です
※契約と直接関係ない事項で事業者側に問題があっても消費者契約法に基づいては契約を取り消すことは出来ません。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
契約の取り消しと無効の基本
無効とは、法律行為の効力が初めから確定的に生じていないことをいいます。
初めから無効なので、追認(あとから認めること)も出来ません。
※無効な法律行為を追認すると、あらたな行為をしたものとみなされます。
無効の主張には原則、期間制限がありません。
取消しとは、いったん生じた法律行為の効力を、初めに遡って無効とすることをいいます。
ですから、取り消すまでは有効です。取り消す事により、初めに遡って確定的に無効となります。
取消しは取消権を有する者のみが主張できます。
追認すると、確定的に有効となります。
※追認したら、以後取消すことはできません。
取り消しの主張には、各法令における期間制限があります。
※詐欺又は強迫を原因とする取り消しの取消権者
・表意者本人
・表意者の代理人
・表意者の承継人
※行為能力の制限を原因とする取消権者
・制限行為能力者本人(未成年者、成年被後見人等)
・制限行為能力者の代理人(親権者、成年後見人等)
・制限行為能力者の承継人(制限行為能力者の相続人等)
・同意見者(保佐人、同意見を有する補助人等)
※法律行為を取り消すと、当事者双方は原状回復義務を負います。しかし、制限行為能力者は現存利益のみを負います。
※民法における取消権の期間制限は
・追認することが出来るときから5年間行使しないときに消滅
・法律行為のときから20年間を経過したときに消滅
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
民法における契約の無効 錯誤
民法を根拠として、契約の取り消しや錯誤が可能です。
しかし、民法の特別法である特定商取引法や消費者契約法と違い、その立証は難しいのが現実です(立証責任は被害者側にあります)。
ですので、まずは特別法での違反がないかを確認することが重要です。
<錯誤>
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は自らその無効を主張できない。
要素の錯誤とは、法律行為の主要部分のことです。もし錯誤がなければ意思表示をしなかっただろうし、かつ意思表示をしないことが、一般取引上の通念に照らし妥当なものを言います。例えば、A土地を買うつもりがB土地を買う契約を交わしてしまった、等です。
つまり、民法での錯誤無効を主張するには、要素の錯誤があり、かつ重大な過失がないという二つの要件を満たす必要があります。
(cf)動機の錯誤がある場合は、原則、錯誤無効を主張できません。しかし、「動機の内容が相手側に表示されており」、かつ要素の錯誤があり、かつ重過失がない場合は、錯誤無効を主張できます。
例えば、A本をB書店にて購入したが、無くしてしまったので、B書店にてA本を再購入した。しかし、家に帰ってみたら、A本が見つかったというケースでは、「A本をなくしたから再購入した」という動機の錯誤が存在します。この場合、その動機をB書店側が知っていれば(動機の内容を相手側に表示されていれば)錯誤無効を主張できます。知っていなければ(動機の内容を相手側に表示していない)主張できません。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
電子消費者契約法における錯誤
電子消費者契約法とは、ネットを使って行われる、事業者と消費者間における電子契約についての紛争を処理する規定です(ですから、事業者間での電子契約は対象となりませんのでご注意下さい)。
ネットでは、操作ミス等により、電子契約の申込みに関する紛争が発生しやすいことから、、電子消費者契約法では民法の規定を修正しています。つまり、民法の特別法です。
<電子消費者契約法における錯誤>
民法では、法律行為の要素に錯誤があり、表意者に「重過失」がなければ、錯誤無効を主張できるとあります。
一方、電子消費者契約法では、次のいずれかの場合に該当すれば、原則、民法での「重過失」の要件が適用されなくなります。
・申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかった場合
・申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき
つまり、操作ミスによる電子契約であっても、無効を主張することができます。
しかし、以下の場合のいずれかに該当すると、たとえ操作ミスによる電子契約であっても、民法での「重過失」の要件が適用されてしまい、操作ミスによる電子契約は有効となってしまいます(無効を主張できなくなります)
・事業者が、消費者の申込みまたはその承諾の意思表示を行なう意思の有無について確認措置を講じた場合(例:送信ボタンを押す前の最終画面に、確認画面をもうけているような場合)
・消費者から事業者に対して、確認画面を講ずる必要がない旨の意思表明があった場合(例:確認画面をスキップする場合はこちら、等の画面があり、消費者がスキップした場合)
ネットで物品を購入することは、もはや当たり前の作業となっています。
確認画面で、電子契約の中身をしっかりと確認することが肝要です。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
民法における契約の取り消し 詐欺
<詐欺>
・詐欺又は脅迫による意思表示は取り消すことが出来る
・詐欺による意思表示の取り消しは、善意の第三者に対抗できない。
善意とは、法律用語で「その事実を知らないこと」です。
(cf)対して悪意とは「その事実を知っていること」です。
例えば、Aさんは、Bさんの詐欺によって、自分の家を不当に安くBさんへ売ってしまったので、Bさんと交わした売買契約を取り消した。しかしBさんは、取消し前に、Cさんへ家を売ってしまっていた。
この場合、Cさん(第三者)が、詐欺の事実について知らなかったら、Aさんは、Cさんに対して、AB間の売買契約の取り消しを主張できません。
Cさんが詐欺の事実について知っていたら、Aさんは、Cさんに対して、AB間の売買契約の取り消しを主張できます。
ちなみにこの場合、Cさんは、詐欺について善意なら保護されますので、家屋の登記を備えている必要はありません。
<第三者詐欺>
第三者が詐欺を行った場合には、相手方がその事実を知っていた時に限り、その意思表示を取り消すことが出来る。
例えば、Aさんは、第三者Xさんの詐欺により、自分の家をCさんへ不当に安く売ってしまった。
この場合、Cさんが詐欺について知っていた(悪意)なら、Aさんは詐欺による取消しをCさんに主張できますが、Cさんが詐欺について知らなかった場合は主張できません。
※詐欺と錯誤の双方の要件が満たされている場合は、詐欺による取消しと、錯誤による無効のどちらも主張できます。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
民法における契約の取消し 強迫
<強迫>
詐欺又は脅迫による意思表示は、取り消すことが出来る。
強迫による意思表示は、無条件に取り消すことが出来ます。
この場合、詐欺と違い、善意の第三者にも、強迫による無効を主張できます。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
民法における時効
●民法における時効には下記があります。
・取得時効(時の経過により一定の権利を取得することができる)
・消滅時効(時の経過により一定の権利が消滅してしまう)
●時効は、当事者(時効で利益を受ける者)が援用(時効の主張)しなければなりません。
※時効の援用権者は、時効により直接利益を受ける者及びその承継人です。
●時効の効力は、はじめに遡って生じます。
●時効の利益は、あらかじめ放棄することはできません。
※しかし、時効完成後に時効の利益を放棄することは可能です。
※時効が完成しても、債務者が自ら進んで弁済することも可能です。
※時効完成後、債務者が債務を承認したり、弁済したりすると、時効の利益を放棄したこととなります(時効の援用が出来なくなります)。
<時効の中断事由>
・裁判上の請求(民事で訴訟を提起する)
・履行の催告(内容証明等)
・差押え等
・承認
※催告の場合、6か月以内に裁判上の請求をしなければ、時効の中断の効力を生じません。
※承認とは、債務者が債務を進んで認めることを指します。具体的には、債務者が債権者に対して「支払猶予を求めた」「利息を支払った」「債務の一部として弁済した」等が挙げられます。
※中断した時効は、中断事由が終了した時から、再び開始します。
<債権等の消滅時効>
・債権は、10年間行使しないときは消滅する。
・債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは消滅する。
・商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
●短期消滅債権
・利息債権、家賃、地代債権→5年
・相続回復請求権→5年
・退職金債権→5年
・不法行為による損害賠償請求権→3年
・医師、病院の医療債権→3年
・給料債権(退職金を除く)→2年
・大工、左官、植木職人などの賃金、理容師、クリーニング業者などの代金債権、商取引上の売買代金、学校、塾などの授業料→2年
・運送賃、ホテル、旅館等の宿泊料、料理店やバーなどの飲食代金、レンタカー等の(動産の使用)料金→1年
●不法行為による損害賠償請求権
・被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき
・不法行為の時から20年を経過したとき
<所有権の取得時効>
・20年間、所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する
→他人物を占有していることを知っている者、もしくは知らなかったことに過失がある者は、20年間の占有により取得時効が完成する。
・10年間、所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始時に善意でありかつ過失がなかったときは、その所有権を取得する。
→他人の物を占有していることを、その占有開始時において知らなかった者、または知らなかったことに過失がない者は、10年間の占有により取得時効が完成する。
※所有権は消滅時効によって消滅することはありませんが、取得時効によって、所有権が移転してしまうことがあるということです。
※取得時効は、前主の権利に基づかないでまっさらな新しい権利を取得することとなります。
※所有権以外の財産権(例:地上権等)や、土地賃借権にも、取得時効は認められます。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
時効を主張したいけど、どうすればいいのだろう?
時効は、時効の利益を受けるもの(債務者等)が主張します(これを時効の援用といいます)。
時効期間が過ぎても、債務者へ債務の履行を請求することは出来ます。支払督促や裁判も可能です。しかしそこで債務者が時効を援用したら債権は消滅してしまいます。
もちろん、時効期間後に債務者が任意に債務を履行することは構いませんし、債務者が債務を承認したならば時効は中断します。
債務者の債務の承認の例を挙げると、
・債務の一部支払
・支払誓約書へのサイン
等があります。
債務者が消滅時効を主張(援用)するには、やはり書面で確実にその意向を債権者へ伝える必要があります。その伝達方法は内容証明が適していると言えます。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
送り付け商法(ネガティブオプション)って何!?
事前に何の連絡もせず、一方的に商品をおくりつけて代金を請求する手口が「送り付け商法(ネガティブオプション)」です。
受け取った以上、購入しなければいけないと、消費者が勘違いして、代金を支払うことを待っているのです。
振込用紙を同封して、商品が到着したころを見計らい、強引な請求を電話などでしてくるのです。
また、代金引換郵便を悪用するケースも多発しています。
このような場合、購入申込みをしていないのですから、代金支払い義務はありません。商品を送り返す必要もありません。商品到着日から14日間は保管してください。その後は、商品を自由に処分できます。この場合、業者も返還請求できなくなります。
また、業者に商品を取りに来てくれと請求することも可能です。この場合、請求した日から7日間が過ぎれば、商品は自由に処分出来ます。この場合、業者も返還請求できなくなります。
「もし返品されない場合は売買契約が成立します」などという文句を並べる業者もいますが、こんな文語は法律上無効です。
14日以内に商品を使用したり消費したりすると、購入を承諾したとみなされる可能性が大きいので、絶対にしないでください。商品包装用のビニールをはがすことは、使用・消費にはあたりませんが、やめてください。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
敷金をきちんと返還してもらいたい!
敷金返還請求は、国土交通省住宅局から出されている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を根拠に、行ないます。
※ガイドラインは法律ではありませんので法的強制力はありません。しかし、裁判では、このガイドラインに沿った判例が出されています
そのガイドラインによれば、退去時において賃貸人(大家さん側)が負担すべきものは、
•毀損・汚損していない畳の裏返しや表替え
•家具などによるカーペットや床などのへこみ
•日照などによる畳やクロスの変色
•タバコのヤニ
•テレビや冷蔵庫などによる電気焼け
•壁などの画鋲や釘の跡
•専門業者による全体のハウスクリーニング
•台所やトイレの消毒
•浴槽や風呂釜の取り換え
•毀損や紛失していない鍵の取り換え
です。
対して賃借人が負担すべきものは、
•カーペットに飲食物などをこぼしたことによるシミ、カビ
•台所周辺の油汚れ
•結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ
•壁などの画鋲や釘の跡(不必要に過大な場合)
•飼育ペットによる柱などのキズ
•風呂、トイレや洗面台の水垢、カビなど
•日常の不適切な手入れもしくは用途違反による設備の毀損
です。
つまり、借主の原状回復義務には、時間と共に自然と古くなっていったものや(経年変化)、普通に丁寧に生活していて発生した汚れ、毀損など(通常損耗)は含まれないのです。
通常損耗とは、普通に使用している程度で生ずる損耗のことを指します。例えば畳の日焼けや壁にポスター等を張るためにとめた画びょうの跡や、家具類を置いてできたカーペットの凹みなどです。このような損耗についての原状回復費用は、貸主負担となります。
現状回復はリフォームとは全く異なります。リフォームは、次の顧客を開拓するため、部屋の価値を高めることであり、前の借主がその費用を負担するいわれはないのです。
また、ガイドラインでは、退去時に負担するべき修繕費等は、故意または過失により生じた傷や汚れだけとしており、通常損耗は貸主が負担するべきものであり、その費用は毎月支払っている家賃に含まれているとしています。
さらに、故意または過失による損耗がある場合でも、修繕範囲は最小単位にするべきであり、クロス・ジュータン・カーペットなどは、経過年数により修繕費の自己負担割合が軽減されます。
例えば、カーペットの場合、償却年数は6年で残存価値1円となるような割合で、経過年数により賃借人の負担を決定しています。つまり、年数が経つほど賃借人の負担割合は減少するのです。
賃貸物件によっては、通常損耗負担特約が付いている場合があります。この特約は「貸主負担」が原則の通常損耗を、「借主」に負担させる契約です。
このような契約が認められるには、特約の内容(通常損耗の原状回復の内容)やその金額等を借主に理解させる等の要件を満たすことが必要となります。※この特約は、消費者契約法施工後に契約更新をしていれば、消費者契約法を根拠として、不当条項としてつぶせる可能性があります。
では、敷金返還請求を行う際には、どのようなことに注意すればいいのでしょうか?
退去する際には、原状回復見積書(たいてい清算書なる題目)が送られてきますので、その内容を精査して、ご自分の負担部分に該当する部分、しない部分を主張することです。
それと、原状回復費の中で大きな部分を占めるのが、室内クリーニング費用です。
契約書に記載があるからという1点張りで請求されることが多いのですが、クリーニング代の請求を防ぐ手段としては、退去時に「大掃除」レベルの掃除をすることがあげられます。
※それでも契約書の内容によっては室内クリーニング費用を拒めない場合もあります。
ちなみに、敷金返還請求が出来るのは、賃貸借契約終了時ではなく、明渡時です。
ですから、退去時の現状をしっかりと把握しておいてください。
具体的には破損・汚損箇所等の写真を可能な限り撮っておき、書類としてまとめておくなどの処置を取っておいてください。
それをしないと、勝手に修繕されてしまい、後から相手側の都合のいい主張に屈せざるを得ない事態に陥りかねません。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
立退料って請求してもいいの?
建物賃貸借契約の更新拒絶通知(立ち退き通知)は、6カ月以上前にしなくてはなりません。
また、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物賃貸借契約は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了しますが、解約日まで6ヶ月に満たない突然の解約の申し入れは無効であり、賃借人は最低6ヶ月間においては居住できます。
そして、上記二例いずれの場合においても、更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、貸主側に正当の事由があると認められる場合でなければ、することができません。
では、貸主側における正当な事由とはどのようなものなのでしょうか?簡単に言えば、立ち退いてもらうのにどうしても必要な事情、ということです。以下に例をあげますが、その例は「正当な事由」に該当しないものを例示します。
・建物の老朽化
倒壊の危険が迫っているような切迫した状況でなければ、正当な事由とは言えません。
・賃貸マンションを分譲にしたいので買取ってほしい
貸主側の一方的な都合ですので、正当な事由とは言えません。
・貸主の家族が住むので出て行ってほしい
貸主側の一方的な都合ですので、正当な事由とは言えません。
・大家を廃業するので出て行ってほしい
貸主側の一方的な都合ですので、正当な事由とは言えません。
上記のような場合で立ち退きを請求されたなら、「正当な事由」を補完してもらうことが可能です。それが立退料の請求です。
では、立退料の算出はどのようにしたらよいのでしょうか?
よく、「家賃×(6~12ヶ月)」が相場などと言われていますが、ケースバイケースです。
立退きを要求する貸主側、立退きを要求される借主側、現在の賃料、住んでいる地域、住んだ年数、引越先、立ち退き要求の理由など全ての条件を考慮して、立退料は算出します。
借りている建物が住居の場合、新居契約にかかる費用、家賃差額等が立退料の範囲となります。
借りている建物が店舗の場合、営業保証や休業損害、新たな広告代や名刺作成代等も立退料の範囲となります。また、借家権の補償も金銭変換して立退料として請求できます。
※もちろん、立ち退き請求に借主側に過失があるような場合には、その過失も立退料には反映されます。
定期建物賃貸借契約の場合には、契約終了の通知を通知期間内に行った上で契約期間が満了したら、立退料は発生しませんが、定期建物賃貸借契約を結ぶには、契約内容を公正証書にする必要があり、かつ、貸主はその内容を書面にして借主に説明する義務があります。
通常の建物賃貸借契約の場合、その内容に、「契約が終了した場合、立ち退き料や損害賠償等一切の請求ができない旨」が書かれていたとしても、借地借家法第30条により無効です。
突然、賃貸物件から立ち退きを迫られた場合、安易に立ち退きに応じるのではなく、まずは立ち退きにおける法律関係を精査して、正当な補償を求められるのであれば請求するなどして、借主側の権利を守ることが賢明です。そのような場合はまず法務家に相談することをお薦めします。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
会社でセクハラにあっている・・・・
セクシュアル・ハラスメントとは、
職場における相手方の意に反した不快な性的言動や経験、それに対する反応によって仕事をする上で一定の不利益を与えられたり、それを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させること、と定義されています。
また、「職場」とは労働者が業務を遂行する場所をさし、オフィス等通常就業する場所以外でも業務を遂行する場所は職場に該当します。勤務時間が終わった後でも、 実質的に職場の延長線上における場所は職場に該当します。
性的言動については、原則、性的言動を受けた被害者が、それにより不快を感じた場合「セクハラ」となります。
しかし、常日頃から性的な会話をしていたが、その後の関係が悪化したことにより、その性的な会話がセクハラとなるか、については認められない可能性が高いです。もちろん、常日頃の性的な会話に不快感を感じ続けていたならば話は別です。
性的言動の内容が、「Aさんだから不快に感じたがBさんから言われたならば不快に感じない」等の場合にはセクハラに該当しません。
また、職場にふさわしくない露出度の高い服装等をしていて性的言動を受けた場合も、セクハラに該当しない可能性が高いです。
セクハラの場合、セクハラ当事者はなかなかセクハラ行為を認めません。
「合意があった」、「コミュニケーションだ」、「以前はセクハラなどと言わなかった」等と主張してきます。
ですので、セクハラを主張するにはその証拠が必要となります。
セクハラをされた日時やその内容を記したメモ、録音テープ、写真や、セクハラを受けた場所を証明する書類(領収書やタイムカード等)、第三者の証言、等を揃えておくことが必須となります。
それらで理論武装した後に、相手方に対して内容証明などを利用して、「セクハラをやめてもらう」こと、及び「損害賠償」を主張すべきです。
また、会社にそのまま勤務し続けたいのなら、内容証明などではなく、嘆願書等を用い、会社に対してセクハラを防止する措置を求めることも一つの手です。会社にはセクハラ行為に対しては適切な処置を講ずることが義務付けられています。勤務先に相談窓口があれば、まずはそこに相談するのも手です。
ちなみに、胸を触るもむ、お尻を撫でるもむ、抱きつく、無理やりキスする、下着に手を入れる等の行為は刑法176条(強制わいせつ罪)に該当する可能性が高いです。この場合、その行為の強弱は関係ありません。
また、名誉棄損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)、またわいせつ物陳列罪(刑法175条)等に該当する可能性があるならば、警察へ告訴することも視野に入れる必要があります。
ともかく、セクハラ被害にあった場合は、その事実関係をしっかりと記録し、その行為がどのような法律に抵触するのかを精査し、適切な主張方法を選択することが肝要です。
申述書、内容証明書、警察への告訴状などの作成は、やはり行政書士等の法務専門家に相談するのがベストだと思います。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
会社でパワハラにあっている・・・・
厚労省の提言によると、パワハラとは以下の通りとなります。
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為
ポイントは2つあります。
・職場内に優位性があるかどうか
上司から部下に対しての行為だけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるなどの様々な職務上の地位や人間関係の優位性を背景に行われるケースが含まれます。
・業務の適正な範囲内かどうか
個人の受け止め方によって不満に感じる指示や注意・指導があっても「業務の適正な範囲」内であればパワーハラスメントに該当しません。
さらに、パワハラの典型例として、以下の6つが挙げられています。
・足でけられるなどの暴行・傷害(身体的な攻撃)
・脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
・隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
・業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
・業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
・私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
※厚労省ポータルサイトより
パワハラにおける「職場」とは、労働者が業務を遂行する場所です。オフィスなど通常就業する場所以外でも業務を遂行する場所は職場になります。また、勤務時間が終わった後であっても、 実質的に職場の延長線上における場所は職場になります。
しかし、セクハラに関しては男女機会均等法により定義されていますが、パワハラに関しては現在、特別法での定義がありません。つまり一般法である民法の不法行為を法根拠として主張するしかないのが現状です(もちろん判例も根拠とします)。
もちろん、事案によっては傷害罪、暴行罪、名誉毀損罪、侮辱罪等も検討しなければなりませんが、そのためにはセクハラと同様、被害の事実関係や損害を立証することが必要ですので、証拠物件をいかに日頃から残しているかが大きなポイントとなります。
会社としても、従業員がパワハラ行為をしていた場合、共同不法行為責任を問われる可能性がありますので、就業規則でパワハラの禁止をうたうとか、管理者教育を徹底するなどの措置をとっておくべき時代といえるでしょう(労働契約法においても、労働者への安全配慮義務は会社に課されています)。
会社に勤務し続けたいのなら、内容証明などではなく、嘆願書等を用い、会社に対してセクハラを防止する措置を求めることも一つの手です。勤務先に相談窓口があれば、まずはそこに相談するのも手です。
ともかく、パワハラ被害にあった場合は、その事実関係をしっかりと記録し、その行為がどのような法律に抵触するのかを精査し、適切な主張方法を選択することが肝要です。
申述書、内容証明書、警察への告訴状などの作成は、やはり行政書士等の法務専門家に相談するのがベストだと思います。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
プロバイダへの情報開示請求
ネット等で誹謗中傷を受けたり、個人情報を掲載されて、個人の権利が侵害されるなどの事案が発生した場合、プロバイダ事業者や掲示板管理者などに対し、これを削除するよう要請できます。
また、権利を侵害する情報を発信した者の情報開示請求もできます。
しかし、発信者情報開示請求をするには、下記二つの要件を満たす場合に限ります。
① 当該情報の流通によって請求者の権利が侵害されたことが明らかなとき
② 発信者に対し損害賠償請求を行うなど、開示を受けるべき正当な理由があるとき
開示請求できる発信者情報は、下記の通りです。
・発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称
・発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
・発信者の電子メールアドレス
・侵害情報に係るIPアドレス
・前号のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻
開示請求手続きは、発信者情報開示依頼書を用います。
開示請求者が請求者の本人確認として、個人ならば住民票の写しや免許証の写し、印鑑証明書等を添付します。
開示請求者が法人でしたら代表取締役の印鑑証明書又は資格証明書等を添付します。
プロバイダ等が発信者情報を保有していないか、発信者情報の特定が著しく困難な場合は、開示不可能である旨が請求者へ回答されます。
請求者が自己の権利を侵害しているとする情報が存在しない場合、権利侵害が明らかでないとして、請求者に開示を拒否する旨が請求者へ回答されます。
発信者情報が特定され、かつ権利侵害情報の確認がされたならば、発信者情報開示の可否について発信者の意見を聴きます。
以上の手続きを経た後、プロバイダ等は請求者の主張の内容が法律に規定されている要件を満たしているかどうかを判断し、発信者情報の開示・非開示の判断をします。
最後に、プロバイダ等は開示・非開示の決定について、開示請求者に通知します。
当該請求の根拠法令はプロバイダ責任制限法です。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
手続きの流れ(内容証明書によるトラブル救済)
お電話やメールでのお問い合わせ(無料)

皆様から問題の概要をお聞かせいただき、アドバイスをさせていただきます。
※電話やメールですとどうしても実情が把握しずらく、どうしても一般的な解答になってしまうことをご了承ください。
面談(出張面談、OKです)

電話やメールでお問い合わせいただいた後、皆様がお望みならば実際にお会いして相談させていただきます。
皆様から実情を詳細にお聞きし、皆様が保存しておられる資料等を精査させていただきます。
そして弊所が作成した資料等を参照していただきながら、法律的観点に基づいて問題の本質をご説明させていただき、問題解決への戦略をたてさせていただきます。面談場所は問いません。
弊所でも構いませんし、皆様のご自宅でも構いませんし、皆様のご自宅近くの喫茶店でも構いません。
ただ皆様が保存しておられる資料等を参照したほうがより正確な戦略が立てられますので、皆様の利益のためにも出張面談を弊所ではお薦めしております。
※出張代は原則いただきません。車や電車で片道3時間以上かかるような場合に、高速料金や電車代をご請求させていただくことがあります。柔軟に対応させていただきます。
お見積書の提出

弊所が内容証明書を出すべきと判断させていただいた場合、内容証明書作成費用のお見積書を作成・提出させていただきます。
見積書の内容などにご納得がいかない場合は何度でもお問い合わせください。
お見積書を再提出させていただきます。
業務委任契約書の締結

提案させていただいたお見積書内容にご納得いただいたら、業務委任契約を結ばせていただきます。
内容証明書作成→依頼者様への確認→発送
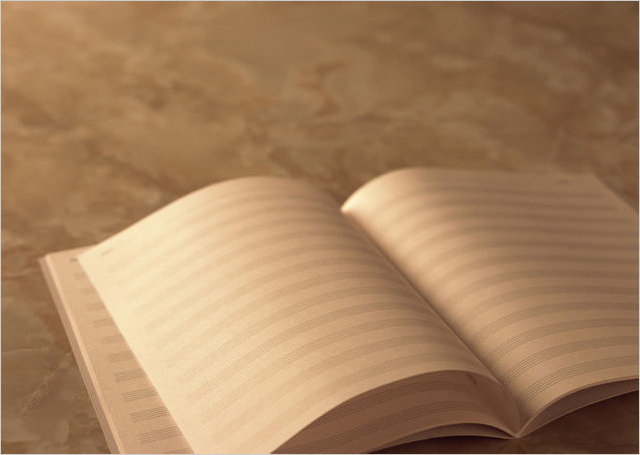
作成した内容証明書は、内容を依頼者様へご確認させていただいた後、発送いたします。
依頼者様へ発送完了のご案内
→内容証明の謄本及び配達証明のはがきを送付

依頼者様へは発送完了のご案内をさせていただきます。
また内容証明の謄本と配達証明のはがきを依頼者様へ提出いたします。
内容証明書発送後のご相談受付

内容証明書を発送した後も、ご相談に応じさせていただきます。
※3回まで無料です。
内容証明書作成によるトラブル救済についての詳細は、お役立ち情報→内容証明書作成をクリックしてください。
↓こちらをクリックして下されば、上記画面へ飛びます。
詳細はこちら
サービス内容 | 基本料金(税抜表記) | 備考 |
|---|---|---|
電話・メールでの | 無料 | 一般的な解答になってしまいます。誤解が生じないように、詳細な相談は面談で行わせていただきます。 |
面談 | 1回5,000円 | 時間制限はありません。 |
内容証明書作成における法務相談フルパック | 20,000円 | 本サービス契約後、一か月間は面談を何度行っても無料です。 |
内容証明書作成 | 25,000円 | 金額はご依頼内容や難易度により変動します。 |
※1 基本料金とは別に郵便代を実費としてご請求いたします。
※2 基本料金とは別に住民票や登記簿の交付代等を実費としてご請求いたします。
※3 片道1時間以上の場所への出張には、日当(10,800円/日)と交通費をご請求いたします。
※表示価格には消費税がかかります。
※本料金表はH26.3.26より適用いたします。
ご相談・お問合せはこちら
当事務所について、ご不明点やご質問などございましたら、
お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください
- 離婚協議書の作成で悩んでいる
- 遺言や相続の相談にのってほしい
- 農地に太陽光を設置したい
- 風俗営業許可をとりたい
- 建設業許可をとりたい
どんなお悩みでも構いません。
誠心誠意をもって対応させていただきます。
皆さまからのお問合せをお待ちしております。
お電話でのお問合せはこちら
059-389-5110
営業時間:9:00~18:00(年中無休)
電話受付時間:9:00〜20:00 ※土日祝祭日の電話は15時~20時の間のみ受付
メール受付時間:24時間年中無休 (2〜5営業日以内にご回答)
行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。
三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
出張面談実施中!

当事務所は出張面談を積極的に実施しております。
ご自宅やその近辺に私どもが出向き、直接お会いしてお話をおうかがいいたします。
各種資料をお渡ししたり、具体的な解決策を提示させていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。
059-389-5110
※面談サービスは予約が必要となります。
事務所概要

行政書士
佐藤のりみつ法務事務所
代表者:行政書士 佐藤則充
〒513-0809 三重県鈴鹿市
西条六丁目3番地の1 ポレスター西条四季の道402号
アクセス (地図) はこちら
主な業務地域
三重県(鈴鹿市・津市・
四日市市・亀山市・その他)、愛知県、岐阜県など
ご連絡先はこちら
事務所概要はこちら
営業日・時間はこちら