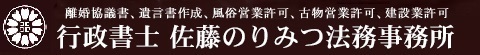遺言書の書き方 遺言書作成支援
遺言書作成実績多数有り!
公正証書にも対応!
平日18時以降面談対応!
土日面談対応!
まずはお電話ください!
遺言書作成全面サポートいたします!

守秘義務を持つ法務家の行政書士が、法的に有効な遺言書、円満な相続に導く遺言書の作成を全面サポート公正証書遺言の作成も全面サポートいたします!
また、尊厳死宣言書の作成エンディングノート作成及び支援も行います。
下記に遺言書の書き方についての詳しい記事があります。どうぞご覧ください。
遺言書作成に悩まれる方々へ・・・・
弊所がサポートする遺言書作成は、遺産のことだけでなく、付言事項に重きを置いています。遺言書には、遺産分割のことだけしか書けないわけではありません。
残しゆく家族への感謝や想いを、付言事項として書き残すことが出来ます。付言事項を書くことで、ご自身の人生を顧みることが出き、今後の人生をどうやって生きていけばいいのかを確かめることが出来ます。
弊所の遺言書作成サポートは、人生の振り返りとこれからの人生を生きる道しるべを探すこと、それが本質にあるのです。どうぞお気軽にご相談ください。
・戸籍等の公的書類の取得全面サポート!
・公正証書遺言書作成に必要な書類収集全面サポート!
・遺言書作成にかかる法務相談全面サポート!
・遺言書作成にかかる「遺言心理カウンセリング」無料実施!
・土日と18時以降の面談可能です!
・電話20時まで対応可能です!
遺言書原案作成に悩んだら、まずはお電話ください!
☎059-389-5110
(電話受付9:00~20:00 年中無休)
「遺言書を書いておくことの重要性がわかっていながら、なかなか書けない」
そんな相談を多数受けます。
遺言書の作成がうまくいかないのには理由があります。
・財産をしっかりと把握できていない
・誰に何を相続させるのかが決められない
・公正証書遺言に必要な書類(戸籍や登記簿等)の取得方法がわからない
・先代の相続手続きが未処理で困っている
・相続税のことが心配
弊所に遺言書原案作成をご依頼していただければ、法令に基づく法務相談と、誰に何を相続させるのかについての「遺言心理カウンセリング」を実施させていただき、上記の悩みを解決した上で、あなたにベストの遺言書完成を全面支援します!
弊所の遺言書作成でのメリット
・財産が把握できて、今後必要な資金がわかり、今後の生活に安心感が持てる
・誰に何を相続させるのかが明確になり、相続争いの心配がなくなる
・公正証書遺言書の作成がスムーズに行える
・先代の相続手続きが完了し、子ども世代に迷惑がかかることを防げる
・遺言書を作成することにより、これまでに人生を振り返ることが出来る
・今後の生活をあなたらしく過ごせる指針を手に入れることが出来る
遺言書原案作成に悩んだら、まずはお電話ください!
☎059-389-5110
(電話受付9:00~20:00 年中無休)
弊所の遺言書原案作成サポートとは
「遺言書の中身の決定をスムーズに行なう手助け」です!
<弊所の遺言書原案作成サポート>
1.まずは面談にて、ご相談者のご意向をお聞きします。
2.次に必要な書類をご指示させていただき、必要書類の取得を弊所がサポートします。
3.その後、法的チェックをして、ご相談者のご意向に沿った遺言書原案を作成します。
4.ご相談者様に確認いただき、遺言書原案を修正いたします。
5.ご相談者様が納得いくまで、修正し、遺言書原案を完成いたします。
6.公正証書遺言書の場合、公証役場との打合せも当職が代行いたします。
7.自筆証書遺言書の場合、遺言書の書き方、保管方法までご指示いたします。
三重県下トップクラスの遺言書作成相談件数を誇る弊所に、遺言書原案の作成はお任せください!
遺言書原案作成に悩んだら、まずはお電話ください!
☎059-389-5110
(電話受付9:00~20:00 年中無休)
遺言書原案作成のご相談
まずはお気軽にお電話ください!
行政書士・佐藤のりみつです
どうぞお気軽にご連絡ください
遺言書の作成・業務一覧
自筆証書遺言書の作成サポート
相続人の調査と相続財産の調査を行わせていただき、そして相談者様の想いを受けながら、財産分割の方法・割合・遺贈の有無等をうかがい、法定相続分や遺留分を考慮した上で遺言書の原案を作成・サポートいたします。
相談者様に遺言書を自筆していただく際も記入・訂正・封印等についての注意事項をご説明しながらご支援申し上げます。
公正証書遺言書の作成サポート
相続人の調査と相続財産の調査を行わせていただき、そして相談者様の想いを受けながら、財産分割の方法・割合・遺贈の有無等をうかがい、法定相続分や遺留分を考慮した上で遺言書の原案を作成いたします。
遺言書の原案を作成後、公証人との打ち合わせを行い、証人として公正証書遺言の完成までご支援申し上げます。
自筆筆証書遺言書のチェックサービス
相談者様の想いを受け、相談者様が自筆された自筆証書遺言書を拝見させていただき、相談者様がご用意された資料等(相続人確認のための戸籍謄本や不動産登記簿等)と照らし合わせ、自筆遺言書の内容をチェックさせていただきます。
また、遺言書をより良きものにするためのアドバイスもさせていただきます。
最後に報告書を提出させていただきます。
遺言書の書き方について
遺言書の書き方について知っていてほしいこと
文字の上でクリックしてください。題名の記事へリンクします。
・遺言書を書いておくべき人の例
・遺言書作成時の注意事項
(遺言できる事柄・遺言書が二通存在する・相続人が自分より先に死亡・負担付遺贈・生前贈与・代襲相続、等)
・遺言書の二つの形式
・遺言書の書き方
・公正証書遺言書について
(証人・手数料)
・遺言書には最後の思いも記せます
(付言事項)
・尊厳死宣言書について
・遺留分放棄と遺言書
・相続権を失うケース
(相続欠格・相続排除)
・事案ごとの遺言書作成に関する注意事項
(子がいない場合・内縁関係・再婚夫婦・お一人様・相続人が誰もいない・お世話になった方へ遺贈したい)
・遺言書の撤回・保管・開封・検認
・遺言執行者について
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
自筆証書遺言の書き方は?
自筆証書遺言の作成には5つのポイントがあります。
①全文自筆の必要
ワープロやタイプライターは使用できません。
(ちなみに、カーボン複写はOKです)
テープやCD、DVD等に記録した音声や動画は法的効力を持ちません。
病気等で字が上手く書けず添え手をしてもらったような場合は無効になる可能性がありますので注意が必要です。(この場合、「他人の意思が介入しない場合は効力が認められる」という判例があります)
②日付の記載が必要
暦上の日付でなくても客観的に特定できる日付であれば効力があります。
例)「70歳の誕生日」
しかし、「○月吉日」等の記載は法的に無効な遺言書となりますので注意が必要です。
③氏名
戸籍名でなくとも、遺言者が特定できればペンネーム等でも効力を有します。
④押印
実印の必要は必ずしもありません。どのような印でも有効です。拇印でも有効です。
⑤文面で気を付けること
相続人に対しては「相続させる」と書くことをお薦めします。
遺贈がある場合は遺言執行者を指定しておくことをお薦めします。
なお数字等の表記は算用数字(1・2等)でもかまいません。
(注意)
2019年1月13日からは以下の点が改正され施行されております。
自筆証書遺言については、『財産目録』については手書きで作成する必要がなくなり、ワープロ等で作成して、『自筆の遺言書に添付』することができるようになりました。
※ただし財産目録の各項に署名捺印をする必要はあります。
※遺言書の本文についてはやはり手書きで作成する必要があります。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
公正証書遺言の書き方は?
①遺言内容を事前に公証人へ送付しておく。
②公証役場に証人二名以上とともに出向く。※公証役場へ行けない場合は公証人に出張してもらうことも出来ます
③遺言内容を公証人に述べ、それに沿い公証人が公正証書遺言を作成する。
原本は公証役場で保管しますので紛失や偽造の問題はありません。一番確実な遺言と言えます。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
遺言書を書いておいた方がいい人の例
・家や土地を所持している
不動産は簡単に分割できないので、誰に相続させるのかを明確に遺言しておく必要があります。遺言しておかないと、不動産を争っての相続紛争が起きかねません。
・財産がほとんど不動産
現金預貯金があれば、遺留分をお金で解決することも出来ますが、現金預貯金が無いとそれもできません。この場合、遺言の付言事項で、なぜその相続人に不動産を相続させるのかの思いをしっかりと記載して、不動産を争っての相続紛争を予防する必要があります。
・賃貸アパート、マンション等を所持している
アパート経営を誰が行うのかを、遺言書にしっかりと明記しておかないと、アパートの家賃をめぐり、相続紛争の元となります。
・結婚しているけど子どもがいない
この場合の相続人は配偶者だけでなく、第一には直系尊属も相続人となります。直系尊属がすでにいない場合には、配偶者とともに兄弟姉妹が相続人となります。配偶者を守るためにも、配偶者にしっかりと相続財産が分配されるように遺言書を書くべきです。
・結婚していて二人以上子どもがいる
子どもが一人なら、子どもの総取りで事は済みます。しかし子どもが二人三人といる場合、やはり遺産をめぐっての相続争いが予想されます。ですので、遺言書で誰に何を相続させるのか、そしてその思いをきちんと記しておくべきです。
・親と同居している子どもとそうでない子どもがいる
同居している子どもは「私は親の面倒をみてきたのだから、より多く遺産をもらってもいいはずだ」という思いがどうしても生まれてきます。遺言書が無い場合、その不平等の思いから相続争いが起こる可能性がありますので、きちんとした遺言書を記す必要があります。
・子どもの経済状況に差がある
お金がどうしても必要な場合、理性を失うのが人間の業です。このような場合も遺産分割協議をしないですむような遺言書を書いておけば安心です。
・子どもたちの仲が悪い
このような場合も遺産分割協議をしないですむような遺言書を書いておけば安心です。また遺言書のなかで付言事項として「兄弟仲良くすることを最後に心から望む」と記すなどして、兄弟の仲を取り持つこともお薦めします。
・離婚した後再婚して、それぞれに子どもがいる
離婚した元配偶者は相続人ではありませんが、前婚での子どもたちはあなたの相続人ですので、その子たちが相続する分もよく考慮した遺言書を書いておかないと、相続紛争の元となります。
・内縁関係の相手がいる
内縁者は相続人ではありません。ですので、もし内縁者を守りたいのなら、内縁者にあなたの遺産が渡るような遺言書を書いておかなくてはなりません。
・配偶者とすでに死別している
この場合、子どもがいればあなたの遺産は子どもが総取りできますが、子どもがいない場合は直系尊属が第一の相続人となります。そして子どもがいないとなると、葬儀や埋葬等の段取りを誰が行うのかという問題もあります。死後の始末をきちんとつける意味でも遺言書を書いておくべきでしょう。
・会社経営者
会社経営を誰に任せるのか、きちんと遺言書で記しておかないと、会社の存続にかかわってきます。あなたの株式を誰にどれだけ相続させるのかによって、会社内での経営権の力関係が変わってきます。経営を任せるのならば、決定権が行使できるだけの株式数を相続させておくべきでしょう。相続人でない他人に経営を任せるのならば、なおのこと株式数を熟慮した遺言書を書いておくべきです。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
遺言書作成時の注意事項
遺言書は後述するように、正しい形式で作成しないと無効になりますので注意することが必要です。
相続人間で遺産争いが起こりそうな場合は自筆証書遺言書ではなく、公正証書遺言書を作成することをお薦めします。公正証書遺言書は家庭裁判所への検認が不要で迅速に執行できるからです。
また遺贈があるような場合は遺言執行者を指定しましょう。
配偶者・子・直系卑属には遺留分があります。遺留分に反しないような遺言書のほうが相続はスムーズに行われます。
一部の相続人に財産を生前贈与しているような場合は、特別受益分を相続分の計算時に含めるのか否かを遺言書に記載しておきましょう。
同様に寄与分を考慮した金額を相続分として定めておきましょう。
遺言能力(意思能力)を疑われるようなことは書かないようにしましょう。遺言が無効であると主張されかねません。
遺産の記載漏れには注意しましょう。
主だった遺産を記載し、あとは「その他の財産は○○に相続させる」という文語を入れておくといいです。
とにかく、正確にそしてわかりやすくがトラブルを防ぐポイントです。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
子がいない夫婦の遺言
全ての財産が一方配偶者に相続されるとは限らないので注意が必要です。
この場合、配偶者は常に相続人となりますが、直系尊属(被相続人の父母や祖父母)が生存している場合、法定相続人及び法定相続分は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3となります。
また、直系尊属が死亡している場合の法定相続人及び法定相続分は、配偶者が3/4、被相続人の兄弟姉妹が1/4となります。(ちなみに、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです)
子がない夫婦の相続で、直系尊属がいる場合は、遺言書で「妻に全財産を相続させる」という文語の遺言書を作っても、直系尊属には遺留分が残ります。
兄弟姉妹には遺留分はないので、遺言書で「妻に全財産を相続させる」という文語の遺言書を作れば、兄弟姉妹の相続権は喪失し、遺言書通りに相続されます。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
内縁関係の夫婦の遺言
内縁関係の夫婦においては、相続権は発生しません。
入籍するか、生前に財産の名義変更をしてもらうか、遺言書で遺贈の意思を意思を記してもらう必要があります。
内縁関係の一方に法定相続人が一人もいない場合、家庭裁判所に相続財産管理人の選定を申立てて、特別縁故者として相続財産の全部または一部を受け取る道もあります。
ちなみに、遺族年金受給者としての配偶者には内縁者も含まれます。
死亡退職金の受取については、企業の就業規則や賃金規則によります。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
再婚夫婦の遺言
離婚した前妻や前夫は、相続人にはなりません。しかし子どもは相続人となります。
では、子どものいる夫婦が離婚して、再婚し、再婚相手との間に子どもをもうけた場合の相続人はというと、再婚相手(配偶者)と再婚相手との間にもうけた子ども、そして前配偶者との間にもうけた子どもとなります。
この場合、前配偶者との間にもうけた子どもと、再婚相手との間にもうけた子どもの法定相続分は同じです。
しかし、それでは再婚相手の配偶者としては、すんなりと受け入れられる事実ではないかもしれませんので、前配偶者との間にもうけた子どもへの配慮として、遺留分を満たすか上回る財産を相続させる等の内容を記した遺言書を書く等の方法があります(遺留分だけは確保しておくことで、前妻との間に生まれた子と、再婚相手との配慮とするのです)。
再婚されたご夫婦は、将来のことを見据えて、遺言書を書いておくことをお薦めします。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
おひとりさまの遺言
独身で、子どももいなく、両親や兄弟とも疎遠であるような方も、最近ではめずらしくありません。
そのような方は、ご自分の将来に対して、とても不安であると思います。
そんな場合は、まずはエンディングノートにご自分の財産目録や家系図、介護が必要となったときの処置、葬儀方法の希望、埋葬について等々を記しておき、それを元に遺言書を作成されることをお薦めします。
死後事務を執り行なってくれる方が身近にいなければ、行政書士等の法務家に遺言執行者となってもらうよう、遺言書で指定しておくこともお薦めします。
また、判断能力があるうちに任意後見制度等を利用して、高齢になり身動きできなくなったら、財産管理や身上監護事務を任意後見人にしてもらうなどの処置をしておくのもいいでしょう。
※弊所では任意後見契約は作成します。また、任意後見人への就任も受けております。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
お世話になった方へ遺贈したい場合の遺言
遺贈には二種類あります。
①包括遺贈
遺産の全部または一定割合(1/3とか)を遺贈する場合
②特定遺贈
特定財産(不動産、預金、貴金属等)を遺贈する場合
包括遺贈の場合、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有することとなりますので、結局のところ、遺産分割協議が必要となります。また、包括受遺者は無限責任を負うので、債務も相続することとなります。それと、遺贈の放棄についても、相続人と同様に3か月以内に行わなければなりません。※遺贈の放棄はいつでもできますが、包括遺贈は除外されるのです。
対して、特定遺贈の場合は、相続債務は承継しません。
ですから、お世話になった方へ遺贈したい場合は、特定遺贈の遺言をお薦めします。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
相続人が誰もいない場合の遺言
相続人がいないと、相続財産の処分だけでなく、葬儀や家財道具の処理等を一体誰がとりおこなうかの問題があります。
そのような場合は相続財産管理人制度や特別縁故者の制度を利用するのですが、この制度はあまり使い勝手が良くなく、利用頻度はとても低いです。結果、身近な人が葬儀や家財道具の処置をすることになり、関係者に多大なる労力を割いてもらうことになります。
このような事態を避けるには、遺言書において、信頼できる人に全財産を包括遺贈する旨を記しておく方法があります。
包括遺贈とは、遺贈でありながらも、包括受贈者(遺贈を受ける人)は相続人と同一の権利義務を持つので、相続人不在状態とはなりません。※包括受贈者は、相続債務の承継には注意する必要があります。
相続財産全部の包括遺贈でも、名義変更などにおいては遺言執行者の選任が必要ですので、遺言執行者についても遺言書で指定しておきます。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
遺言できる事柄は法律で決まっている
下記以外の内容は法律的には無効となります。
・財産及び財産の処分について
・身分に関することについて
※認知や未成年者の後見人指定等
・祭祀について
※祭祀継承者の指定等
・遺言執行者の指定
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
複数の遺言書が出てきてしまったら!?
内容の異なる複数の遺言書が出てきた場合は、日付の新しいものが有効となります。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
相続人が自分より先に死亡した場合ってどうなるの?
遺言で指定した遺産の相続人が、被相続人よりも先に死亡するとその部分の遺言は無効となります。(相続人の子らは代襲相続できません。H23.2.22最高裁判例)
ですから、遺言書で遺産を相続させる子を指定するときは、その相続人が自分よりも先に死亡した場合についても記載しておくことをお薦めします。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
遺産分割の方法
遺産分割方法は、下記の3つの方法があります。
①現物分割
遺産をそのままの形で分割する方法。
不動産でしたら、法定相続分にそって共有持分としたり、土地と建物をそれぞれの相続人名義にしたりすることを、遺言書に記載します。
②代償分割
遺産そのものを取得した者が、取得しなかった者に対して相続分に対応する代償金を支払う方法。
不動産でしたら、評価額4000万円の土地を相続で取得した者が、取得しなかった相続人に対して相続分に対応する代償金(例えば2000万円)を支払うよう、遺言書に記載します。
③換価分割
遺産を売却して金銭に換えて、その代金を相続人が分割して取得する方法。
ちなみに、遺産分割方法は、遺言書で指定できますが、遺言書が存在しなかった場合は遺産分割協議で決定します。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
負担付遺贈
負担付遺贈とは、遺産を譲渡する代わりに一定の条件を受遺者に課すものです。
例えば、200万円遺贈する代わりに、ペットの世話をみてもらう、等の内容を遺言書に記載するのです。
この場合、条件は具体的明確に記載し、かつ遺留分に注意する必要があります。
さらに、遺言執行者を遺言書で指定しておき、負担が履行されているかどうかをチェックしてもらいます。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
生前贈与と遺言書の関係
生前贈与は、相続紛争を避けるのに有効かもしれませんが、相続開始後に、特別受益の問題や、遺留分の問題を生じさせる可能性もありますので注意が必要です。
そのような場合は、遺言書に「(贈与した財産を)相続財産に戻さない」という記載をしておきます。これを払い戻しの免除といいます。
しかし、この場合でも、遺留分の問題はぬぐいきれませんので、生前贈与に遺留分を弁償できるだけの分を含ませるなどの対処が必要です。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
「相続させる」という表記の注意点
特定された遺産、もしくは遺産全部を、特定の相続人に「相続させる」旨の遺言は、原則、遺産分割の方法を定めたことになり、相続開始と同時にその遺産は遺産分割されたこととなり、当然に所有権が移転します。不動産の場合だったら、その相続人が単独で所有権移転登記を行うことが出来ます(遺言執行者がいても協力は不要となります)。
対して、「○○に遺産の1/4を相続させる」という旨の遺言は、どの財産なのか不明なので、相続分の指定とされ、遺産分割協議が必要となります。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
「遺贈する」という表記の注意点
「遺贈する」旨の遺言は、相手が法定相続人でない場合に用いますが、この場合、遺言者の遺贈義務を受け持つのは全相続人となります。
ということは、「不動産を○○へ遺贈する」とした場合、相続人全員の承諾をもって相続登記をしなければなりません。
ですので、遺贈の場合は、遺言書に遺言執行人を指定しておき、遺言執行人に遺言を執行してもらうことをお薦めします。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
代襲相続と遺言の関係
遺産を承継させたい者が、被相続人より先に死亡してしまうこともありますので、遺言には、代襲相続させるのか否かを明確に記載しておく必要があります。
というのも、「相続させる」旨の遺言は、「遺言者が代襲相続させる意思を持っていたとみなすべき特別の事情がなければ効力を生じない」という判例があるからです。
ちなみに、遺贈の場合には、受遺者が遺贈者より先に死亡した場合は遺贈の効力は発生しません(民法994条)。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
公正証書遺言の作成に必要な書類って何?
①遺言者本人の印鑑登録証明書
②遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
③相続人以外の方に財産を遺贈する場合はその人の住民票
④財産の中に不動産がある場合はその登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産評価証明書(または固定資産税・都市計画税通知書中の課税証明書)
⑤証人予定者の名前、住所、生年月日、職業のメモ
等が必要です。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
公正証書遺言の証人になれない人っているの?
未成年者
推定相続人とその配偶者・直系血族
公証人の配偶者・公証人の4親等内の親族
公証役場の関係者
等は公正証書遺言書作成における証人になることが出来ません。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
公証人へ支払う作成手数料っていくら?
<目的財産の価額→手数料>
100万円まで→5,000円
200万円まで→7,000円
500万円まで→11,000円
1,000万円まで→17,000円
3,000万円まで→23,000円
5,000万円まで→29,000円
1億円まで→43,000円
1億円~3億円まで→5,000万円ごとに13,000円加算
3億円~10億円まで→5,000万円ごとに11,000加算
10億円~→5,000万円ごとに8,000円加算
※相続人の人数に応じて手数料は加算されます。
※これ以外にも費用が掛かる場合があります。
※公正証書遺言書における公証人へ支払う正確な金額については、公正証書遺言書の原案が完成した後に、公証人より通知されます。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
遺言書の付言事項って何?
先に記したように、遺言事項は、実は法定されています。
・認知
・後見人の指定
・後見監督人の指定
・遺贈
・遺留分減殺方法の指定
・寄付行為
・相続人の廃除及び廃除の取消し
・相続分の指定及び指定の委託
・特別受益者の持ち戻しの免除
・遺産分割方法の指定及び指定の委託
・遺産分割の禁止
・共同相続人間の担保責任の指定
・遺言執行者の指定及び指定の委託
・信託の設定
・祖先祭祀主宰者の指定
・生命保険金受取人の指定
上記以外の事項を遺言書に記しても、その部分に限り法的効力を持ちません。
しかし、法的効力はもちませんが、残し行く家族に、遺言書の中で、あなたの想いを伝えることもできます。
それが付言事項です。
葬儀内容や法事の仕方、散骨の希望等が代表的な記載例ですが、相続人に対する感謝の気持ちや、親が子に対して最後に残す言葉や想い、そしてなぜこのような遺産分割の指定をしたのかの真意を愛情を持って記すのです。
また、家族が仲良く暮らしていってくれることが誰しもの真意でありましょう。そのような場合は遺留分を行使することなどのないようにと、付言事項に記しておくのです。
あなたが遺言書に込めた、あなたの人生における最後の思いが相続人に伝わることで、相続人たちの心をほぐし、無益な相続紛争を予防することも出来るのです。
そのためには、付言事項に込める思いは、あなたの人生哲学が反映されている必要があります。難しくはありません。あなたが生きてきた人生をそのまま言葉に記せばよいのです。
付言事項を記す事、それはあなたの人生を振り返ることだけでなく、これからの最後の人生をどう生きていくべきなのかをも見据えていく作業となります。
弊所では、この付言事項に重きを置いて、遺言書作成の支援をさせていただいております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
尊厳死宣言書について
日本には、尊厳死につていの法律がありません。
しかし判例で、尊厳死をむかえるために医療行為の中止が認められる要件は示されています。
①現代医学では治療不可能な病気で回復の見込みがなく末期状態にあること
②自然死を迎えさせる目的にそっていること
③延命治療中止について本人の意思表示が認められること
③のケースで代表的なものが、尊厳死宣言書です。
わたしは尊厳死を進めているのではありません。
例えば、私の親が尊厳死宣言書を書いていたとして、その存在を私が知っている場合、いざその時になって「チューブを外してください」と、言えるのかどうか、自信がありません。
親の意思だから、私の決断で、親の命を切ってもいいのか?
今の私には答えが見つかりません。
しかし、もしかしたら、そんな困難な状況にあって、親の尊厳死の意思表示が、私の自責の念を救ってくれるかもしれないのなら、あなたが尊厳死宣言書を残す事にも、意味があるのではないでしょうか?つまり、尊厳死宣言書は、愛する家族の心の負担を和らげる可能性があるのではないか? そうも思います。
人が死ぬということは、周りの人間に多大なる影響を与えます。
それが、死を自ら選択するような場合、手を尽くして存命させたいと望む家族のきもちを振り切ることにもなります。
尊厳死宣言書は、よく考えてから書いてください。
そして、尊厳死宣言書には、なぜ延命治療を拒むのか、その理由もきちんと記載しておくことをお薦めします。
人の死は荘厳です。重々しく立派なのです。
延命治療の判断の際に、つまりは死の間際に、なぜ尊厳死を望むのか、そこにあなたの人生における哲学がこめられて、あなたの人生における荘厳な最後の瞬間に、あなたの人生哲学が子どもたちに伝えられるのならば、それは子どもたちにとっても喜ばしいことではないでしょうか?何の言葉もなしに永遠の別れをすることは、寂しすぎやしないでしょうか?
尊厳死宣言書に、決まったフォームなどはありません。
あなたの命に対する想いを記すのです。
尊厳死宣言書は、命に対するあなたの人生哲学そのものです。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
遺留分放棄と遺言書
全財産を他人に与えるような遺贈がなされていても被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺産の一定部分を必ず受け取る権利があります。この一定部分の事を遺留分といいます。
遺言書で遺産分割について記す際に、気を付けなければならないのが遺留分です。
遺留分を無視した遺産分割の指定は、相続紛争を引き起こす可能性が無いとは言えないからです。
その遺留分ですが、実は、被相続人の生前中に放棄することができるのです。
※相続放棄は、被相続人の生前中に放棄することはできません。
被相続人の生前中に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。
その要件は下記の通りです。
・遺留分を放棄する本人の自由意志であること
・遺留分を放棄する理由に合理性、必要性、妥当性があること
・遺留分の放棄と引き換えに贈与等で代償してもらっていること
妻だけに全ての財産を相続させたいような場合、他の相続人に、遺留分放棄の制度を利用してもらうよう頼むのです。
しかし、遺留分の放棄は、相続権の放棄ではないので、相続が開始すると、遺留分を放棄した人も法定相続人になります。
ですから、遺言書で、妻だけが相続人であることをきちんと記しておくことが重要です。
さらに、なぜそのような相続にしたのかを、付言事項に、愛情と感謝の気持ちを込めて記しておくのです。
遺言書を作成するときの一番重要なことは「遺産分割協議の余地がない」内容とすることです。あなたが記した遺言書通りに相続手続きがなされれば、相続紛争が起きる余地もありません。そのためにも、遺留分について熟慮することは、遺言書作成のなかでもとても大切な部分です。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
相続権を失う場合・相続欠格
相続欠格とは、相続人にふさわしくない事由(欠格事由)を持つ相続人が、相続開始時に当然に相続権を失うことです。
欠格事由は下記の通りです。
・被相続人、または先順位か同順位にあるほかの相続人を殺そうとしたりして刑に処せられた
・被相続人が殺害されたことをしっているのに告発または告訴しなかった(ただし、判断能力がなかったり、殺害者が自分の配偶者または直系血族であった場合を除く)
・詐欺又は脅迫によって遺言することや遺言の撤回、取消しまたは変更することを妨げた
遺言書を偽造、変造、葉木、隠匿した
相続欠格者が勝手に相続手続きをしても、他の相続人はその手続きの無効を主張できます。
ちなみに、相続欠格となっても、代襲相続は認められます。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
相続権を奪う場合・相続廃除
相続開始前でも、一定事由があれば、遺留分のある相続人の相続権をはく奪する請求を行えます。それが相続廃除です。
廃除事由は「被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人に対してその他著しい飛行があったとき」です(民法892条)
相続廃除の請求は、被相続人が生前中ならば家庭裁判所へ請求します。
遺言書で請求することもできます。その場合は、遺言執行者を遺言で指定して、遺言の効力が発生したら、遺言執行者に執行(家庭裁判所へ請求)してもらいます。
相続廃除された者は、相続権を失い、かつ遺留分を主張することも出来なくなります。
しかし、代襲相続は認められます。
被相続人は、生前の請求もしくは遺言により、相続廃除を取り消す事もできます。この取消しも、家庭裁判所への申立てが必要です。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
遺言書の撤回について
遺言書を撤回したい場合は、遺言書の方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)にしたがい、新しい遺言書を作成すれば足ります。
ちなみに、新しい遺言書と、古い遺言書の内容で、抵触しない部分が残っていたら、その部分に関しては古い遺言書の効力が残りますので、記載には十分留意する必要があります。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
遺言書の保管につてい
自筆証書遺言は、原本が一通だけですので、なくさないように注意して保管しなければなりません。
また、自分がどこに保管したのかを忘れてしまうことも多々あります。
保管だけでなく、遺言書を見つけた相続人に書き換えられたり、等という心配もないとは言えません。
では誰にも誰にも見つからないような場所に保管すればいいのかというと、それはそれで問題があります。というのも、相続が開始した時に、遺言書自体が見つけられない可能性があるからです。
解決方法は、金庫や銀行の貸金庫に保管することをお薦めします。もしくは、信頼できる第三者で、相続の開始を絶対に知ることのできる人物に預ける、または遺言執行人を指定しているのなら、その人に預ける、等です。
対して公正証書遺言の場合は、原本一通を公証役場で保管されて、遺言者には正本と謄本(写しです。法的効力はありません)各一通が交付されます。遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が正本を、遺言者は正本を所持することが多いです。ちなみに、正本や謄本を封室しても再交付は可能です。
しかし、紛失の恐れのない公正証書と言えども、相続人が公正証書遺言の存在を知らなければ意味がありませんので、公正証書遺言の存在を相続人に伝えるか、正本や謄本の保管場所を知らせる等しておく必要があります。(公正証書遺言なので、書き換えられる恐れはありません)
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
遺言書の開封について
封印してある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人立ち合いの元、開封しなければなりません。
「封印してある」とは、封に押印がしてあることであり、単なる「封入」ではありません。
封印してある遺言書を開封した場合、5万円以下の過料に処せられます。また、遺言書自体が無効となる可能性もあります。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
遺言書の検認手続き
公正証書以外の遺言書(自筆証書遺言と秘密証書遺言)を発見した者、もしくはその保管者は、相続開始後、遅滞なく、家庭裁判所へ遺言書を提出して「検認」を請求しなければなりません。
検認の請求は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所に行います。
検認手続きを経ると、検認証明書が発行されます。
検認とは、あくまでも遺言書の外形的な状態を確認するだけの手続きであり、遺言書の有効無効を判断するものではないことに注意が必要です。
つまり、遺言書の効力を争うような場合は、別途訴訟を提起する必要があるのです。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
遺言執行者について
遺言執行者とは、遺言の内容そのままを執行する者のことです。遺言による認知、推定相続人の廃除やその取消し等は、相続人は執行できません。必ず遺言執行人に執行させなければなりません。
相続開始後に就職した遺言執行人は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利義務を持ちますので、相続人の協力なしに遺言内容を実現できます。相続人は遺言執行者の遺言執行を妨げることは出来ません。
遺言の内容に遺贈が記されていた場合、その執行は相続人全員の協力が必要となりますが、全員の協力が得られるとは限りません。となると、裁判か遺言執行人の選任を家庭裁判所へ申し立てることになります。
不動産の遺贈については、移転登記手続きに相続人全員の協力が必要ですので、やはり遺言執行人を選任する必要が出てくる可能性があります。
遺言内容を確実に実現させたいのなら、遺言執行人を指定しておくべきです。それも、共同相続人のうちの誰かではなく、利害関係のない第三者で、守秘義務があり、かつ専門知識が豊富な行政書士等の法務家を指定することをお薦めします。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
遺言執行者の解任について
遺言執行人には、就任後遅滞なく(就任後2~3か月)、相続財産目録を作成して、法定相続人に交付する義務があります。
遺言執行人は相続人の代理人とみなされますので、相続人に対して善管注意義務を負い、事務処理内容や状況について報告する義務もあります。
遺言執行人が任務を怠った時、その他正当な事由がある場合、、相続人や利害関係人は、家庭裁判所に遺言執行人の解任請求をすることができます。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
料金(遺言書の作成)
サービス内容 | 基本料金(税抜表記) | 備考 |
|---|---|---|
電話・メールでの | 無料 | 一般的な解答になってしまいます。誤解が生じないように、詳細な相談は面談で行わせていただきます。 |
面談 | 1回5,000円 | 時間制限はありません。出張面談は片道1時間以上の場合に高速代や電車賃等の実費をご請求させていただきます。 |
自筆証書遺言書の 作成サポート | 50,000円~※1 | 相談者様の想いを受けながら、財産分割の方法・割合・遺贈の有無等をうかがい、法定相続分や遺留分を考慮した上で遺言書の原案を作成いたします。※8 |
公正証書遺言書の 作成サポート | 100,000円~※1 | 相談者様の想いを受けながら、財産分割の方法・割合・遺贈の有無等をうかがい、法定相続分や遺留分を考慮した上で遺言書の原案を作成いたします。 ※8 ※9 ※10 ※2 ※11 |
自筆証書遺言書の チェック | 30,000円 | 自筆された遺言書と相談者様にてご用意していただいた資料(戸籍謄本や不動産登記簿等)を確認し、遺言書の内容をチェックさせていただきます。その際、遺言書をより良きものにするためにアドバイスをさせていただき報告書へまとめて提出いたします。 |
相続人の調査 | 50,000円~ | 相続人が3人より1人増えるごとに10,000円プラスされます。※8 |
相続財産調査 | 50,000円~※4 | 相続財産を証明する書類(不動産謄本、預貯金の通帳、株券、借用証書等)を収集し、債権・債務を調査し、財産目録を作成します。預貯金の通帳、株券、借用証書等)を収集し、債権・債務を調査し、財産目録を作成します。※8 |
エンディングノートの 作成支援 | 30,000円 | 依頼者へヒアリングをさせていただき、エンディングノートのフォームをもとにして、人生の振り返りとよりよい幕引きへと導くエンディングノートの作成を支援いたします。 |
※1 基本料金は財産を残したい方がお一人の場合です。財産を残したい方が一人増えるごとに10,000円が加算されます。
※2 公正証書の手数料
※遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、3①の方式により、4万3000円です(なお、下記のように遺言加算があります。)が、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となります。ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しているので、7万2000円に1万1000円を加算した8万3000円が手数料となります。
次に祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円です。
遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。
がそれぞれ加算されます。
注)上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。
- 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して当該遺言書全体の手数料を算出します。
- 遺言加算といって,全体の財産が1億円以下のときは、上記1によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。
- さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
- 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が病院・ご自宅・老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記1の手数料が50%加算されるほか,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。
- 具体的に手数料の算定をする際には、それぞれの公証役場で確認する。
※4 相続財産の内容によって、基本料金が増減する場合があります。
※5 片道1時間以上の場所への出張には、日当(10,800円/日)と交通費をご請求いたします。
※6 表示価格には消費税がかかります。
※7 本料金表はH26.3.26より適用いたします。
※8 調査費用や取得費用などは別途必要となります。
※9 弊所による公証人との打合せ費用は含まれております。
※10 公正証書費用は含まれておりません。別途ご請求申し上げます。※2
※11 証人を弊所が手配させていただく場合、証人一人につき10,000円が加算されます。
ご相談・お問合せはこちら
当事務所について、ご不明点やご質問などございましたら、
お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください
- 離婚協議書の作成で悩んでいる
- 遺言や相続の相談にのってほしい
- 農地に太陽光を設置したい
- 風俗営業許可をとりたい
- 建設業許可をとりたい
どんなお悩みでも構いません。
誠心誠意をもって対応させていただきます。
皆さまからのお問合せをお待ちしております。
お電話でのお問合せはこちら
059-389-5110
営業時間:9:00~18:00(年中無休)
電話受付時間:9:00〜20:00 ※土日祝祭日の電話は15時~20時の間のみ受付
メール受付時間:24時間年中無休 (2〜5営業日以内にご回答)
行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。
三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
出張面談実施中!

当事務所は出張面談を積極的に実施しております。
ご自宅やその近辺に私どもが出向き、直接お会いしてお話をおうかがいいたします。
各種資料をお渡ししたり、具体的な解決策を提示させていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。
059-389-5110
※面談サービスは予約が必要となります。
事務所概要

行政書士
佐藤のりみつ法務事務所
代表者:行政書士 佐藤則充
〒513-0809 三重県鈴鹿市
西条六丁目3番地の1 ポレスター西条四季の道402号
アクセス (地図) はこちら
主な業務地域
三重県(鈴鹿市・津市・
四日市市・亀山市・その他)、愛知県、岐阜県など
ご連絡先はこちら
事務所概要はこちら
営業日・時間はこちら